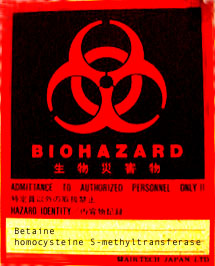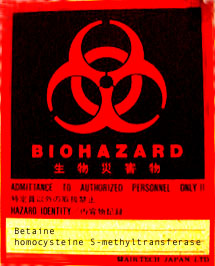最終的に――僕が、その悪魔の作業に手を貸すことを決意したのは、―――真宮氏の論文に、かつて大いに啓蒙を受けたせいもあったからだと思う。
彼は、進化とは、異なる種の相互作用によってのみ引き起こされる――という、進化の相互作用論を説いておられた。
「これもひとつの進化の過程なのだ」
博士は、こう言っておられたように思う。
「新しい種を撒くことが、確実に我々人という種を進化させる。考えてみたまえ、あらゆる生態系の生物の中で、縄張り、食べ物、メスの捕獲――それ以外の理由で争い、かつ争いを止めるルールを持たない生命は、私たち人類だけだ」
何の意味もなく同胞を殺すのは我々の種だけだ――。
躊躇する私に、博士は強い口調で仰られた。
「人という種は進化しなければならない。プロジェクトの目的である外宇宙で生きられる肉体的な進化――そんなものは、なんの意味もないことだ。ただの兵器と同じで、使用者の意図ひとつで、いくらでも危険な用途に用いられる可能性がある」
僕もそこまでお人よしの莫迦じゃない、薄々は気づいていたよ――このプロジェクトに潜むもう一つの暗黒面をね。
これは、ある種の生物兵器の開発なんだ。
考えてもみたまえ。
絶対零度にも高温にも、高気圧にも真空にも耐え得る生物。さらにいえば、高レベルの放射能さえ耐え得る生物。
しかも頭脳は天才的で――空中を高速で移動可能だとしたら。
こんな恐ろしいものが、軍の意のままに使われるようになったとしたら――君はどう思うかね。
真宮博士も、その程度のことは察しておられたのだと思う。そして、その上で、プロジェクトへ参加することを決意されたのだ。
「この地球に人という種が誕生してわずかな間に――人はどれだけ沢山の同胞を殺戮してきたことだろう。そしてそれは、今でも世界各地で絶えることなく続いているのだ。人が争うことを止めなければ、終局的には種は滅びる。太陽膨張を待つまでもない。それは一年先の未来かもしれないし、明日かもしれない」
そう。
彼には彼なりの信念があった。
進化だよ。進化の相互作用だ。
博士はね、人という種の精神を進化させようとしていたんだ。
「人は進化しなくてはならない。この種を絶滅から救うには、精神的な進化が必要不可欠だ。いいかい、第二次世界大戦で初めて核が使用された時から、我々種は、常に滅亡の淵に立たされている。いや、自らの意思で立ち続けているのだよ。わずかな波紋であっさりと深淵に飲み込まれてしまう。そんな危うい状況なのだ、一刻の猶予も許されないのだ」
精神的な進化――それを促すために、彼は人と異なる種を、生態系に誕生させる道を選んだのだ。人よりさらに優れた種を、この地上に誕生させる道を選んだのだ。
今、米国を騒がせている、突然大量発生した天才少年たちのことは、――君も噂程度に聞いたことはあるだろう。五〜七歳児にして平均値を遥かに超える知能を持つ天才たち。
DNA検査をすれば、その塩基配列が、わずかに人類と異なる新しい種だ。
もう――判るだろう。彼らは、707R遺伝子胚から誕生した子どもたちなのだ。
真宮博士は、新しい人種と、従来の人種――その二種の間に、やがて決定的な争いが起きると予言しておられた。その争いを超えたところに救いがあると仰っておられた。
「彼らの存在は、来るべきカオスの時を早めることになるだろう」
カオス――それは、核を使用した世界大戦のことを言っていたのだろうね。
「カオスは早ければ早いほうがいい。あらゆる国が核を持ち、最新兵器を装備するようになれば、カオスは直結して種の破滅に結びつく――そうなる前に、人は目覚めなければならない。進化しなければならないのだ」
長々と書いたが、僕が何故、真宮博士の手助けをするようになったか――理解していただけただろうか。
どんな理由があろうと、進化に人の手を加えるなどもっての他だ。
人為的に手を加えられた進化など、組換え生物と同じで、真の進化ではない――君ならそう言うかもしれないね。
ただ、博士はこう言っておられたのだよ。
「707R遺伝子は、意図的にできたものではない。ラボで囁かれているように、決して喜屋武さん一人が作りあげたものでもない。……人知を超えた何かが偶然を導き、そして完成させた。――私には、そうとしか言いようがない。これは、紛れもなく自然発生した種なのだ。宇宙の意思によって誕生した新種なのだ」
・
・
むろん、喜屋武リーダーに遺伝子注入を命じた者たちは――それが誰だかまでは聞かされてはいないがね、間違いなく、米国防総省以下、米国立衛生研究所も絡んだプロジェクトだったと思うがね――、真宮博士のような大いなる意図を持って、707R型の遺伝子注入を命じたわけではないと思うよ。
あくまで実験過程の応用だったのか――もしくは、意図的に天才児を生み出そうとしていたか――。
選ばれた卵子は、白色人種のものが一番多く、二番目が黄色人種だった。――しかし、この遺伝子はね、どうも黄色人種のそれと一番相性がいいようなのだ。
絶対数こそ少ないが、真に優秀な遺伝子を持つ子どもは、おそらく日本か――中国、そのあたりに集中するのではないだろうか。これは僕の個人的な憶測だがね。
多少の不安を感じないではなかったよ。なにしろ、米中の緊張状態は、この百年エスカレートする一方だ。この芽が、いずれ米国に牙を剥かないとも限らない。
が、白人至上主義ってヤツはやっかいなもので、上の連中は、そんな単純な事実にさえ目を向けようとはしないのさ。
誕生した子どもの男女比率は、圧倒的に男性が多かった。女性は一割に満たないくらいだ。
707R型を注入した場合、何故か染色体配列が男性のままで固定されてしまうんだ。
これには、喜屋武リーダーも最後まで首をひねっておられたがね。
・
とにかく第一世代は順調に誕生したんだ。
なのに――ある時突然、真宮博士はこの研究から手を引くと言い出した。
707R型遺伝子には、真宮博士でさえ知らされていなかった、ある特殊な生物学的封じ込めがなされていたんだ。
僕もその全容までは知らない。
真宮博士もはっきりと明言はされなかった。
判っているのは、喜屋武リーダーが――最終的に、出来上がった遺伝子に何かの手を加えていた、ということだけだ。無論、それも上の命令だったのだろうがね。
「この計画は中止しなければならない」
ラボから姿を消す前日だった。
真宮博士は、僕がはじめて観るような――激しい憤りを露わにしておられた。
「私は間違っていた。もう手遅れだ、―――最悪のバイオハザードだ。常に生きようと変化していく遺伝子を封じ込めるなど、そもそも人の手では不可能なのだ。奢った考えだ、しかし私自身も、彼らと同類でないとどうして言えよう」
「私は、自信が神になろうとしていたのか、――――私は――どうすればいい。すでにこの世に生を受けた数百の命に、私はどう責任を取ればいいのだ」
何が不満なんです、何が心配なんです。
僕は問うた。
軽蔑してくれ、唾棄してくれ。
僕はその時、自らが神となる己の役割に酔いしれていたのだ。
施された生物学的封じ込めが何を意味するかは分からない――が、おそらく不妊に関する遺伝子操作だということは察しがついた。
誕生した子どもたち――、彼らの遺伝子には、自然界に拡散されないよう、何らかの操作が施されていたのだろう。
残酷なようだが、それは遺伝子組み替えを行う際の常識であり、基本だ。
組換え遺伝子は、自然界には存在しない異種のものだ。まかり間違えば生態系そのものを滅しかねない諸刃の剣だ。
作物であれば発芽しないよう――人間であれば妊娠できないよう――生殖できないよう――操作を加えて、一体何が悪いというのだろう。
私がそれを力説しても、真宮博士は力なく首を振るばかりだった。
「私はこの研究から手を引く――いや、もう再生チームの役割は終わったのだ、研究はほぼ完成の域に入った、……もう、喜屋武さんにはついていけない。これ以上―――私は罪を重ねたくない」
何を言ってるんです、そんなのは卑怯だ、逃げだ。
僕は激しく糾弾したよ。憔悴しきったあの人を罵倒し、叱咤した―――励ましたかったのだ。だって、プロジェクトの本来の目的は全く達せられていないのだよ。
ただの失敗作が――偶然天才を生み出す遺伝子となっただけなのに。
僕がそう言うと、彼は苦く笑んで首を横に振った。
「707R遺伝子は、あれで完全なものなのだ。あれ以上手を加えても無駄だし、あれ以下にしてもダメだ。言っただろう――あの遺伝子は、神の手に導かれて完成したものなのだと。喜屋武さんも、上の連中も――多分それは知っている。おそらく、今後の研究は、707Rで誕生した子どもたちの遺伝子を用いた、複製実験にシフトしていくことだろう」
僕は――意味が判らなかった。
そして翌日、真宮博士の姿はラボから消えた。
彼の予言どおり――その翌年から、再生チームは著しく縮小された。
その代わり、707R遺伝子を持つ子どもたちから取り出した遺伝子核を受精卵に核移植して――彼らのクローン遺伝子を持つ二世代目が生成された。
僕を軽蔑してもかまわないよ。
その時点で、僕は完全に理性も良心も失っていた。
二世代目の一部は、一世代目のクローン体なのだ。むろん手を加えてはあるが、基本的には同一遺伝組織を持った個体なのだよ。
この受精に係る人選は厳密に――行われたはずだ。
統計を取ることが可能であれば、二世代の大半が、施設育ちだということが判るだろう。……可能であれば、ね。
・
・
こんな神をも畏れぬ計画を推し進めたのも、707R遺伝子を持った新人類が、決して自然増殖しないという、確たる自信があったからなのだろうか。
けれど、プロジェクトは先月、唐突に中止を言い渡された。
喜屋武リーダーの自殺と共にね。
郊外の家にガソリンを撒いて、自ら火を点けての焼身自殺だ。全て焼け落ち、何一つ残らなかった。――――信じられなかった。何を考えているのか理解不能の人だったが、どう考えても死にそうには見えなかったから。
彼の死に起因して、何か――致命的なトラブルが生じたのだと、―――僕が判り得たのはそれだけだった。
僕を含む研究員は、一人一人、名前も身分も名乗らない黒服の男たちに尋問を受けた。彼らの質問の意図は明らかだった。R707遺伝子は、どのような過程を経て完成したのか。そして、知りえる限りの――卵子提供者の名前を書かされた。
しかし、記憶している名前なんて殆んどない、だって僕らは――卵子を記号で管理していたのだから。個人情報までつぶさに見れていたのは、おそらくチームでは喜屋武一人だけだ。いや、今思えば、彼はあえてその情報を一人で握っていたように思う――今、思えばだがね。
この質問から察せられるのは、ひとつだけだった。
喜屋武リーダーは、死の間際、R707遺伝子精製に関する全ての情報と――そして、その遺伝子を注入した卵子提供者の情報を、なんらかの方法で、全て消去してしまったのだ。
僕はその想像に慄然とした。
ばらまかれた遺伝子の行く末を把握できなければどうなるだろう。
そうでなくとも、人口受精で生まれた子どもと言うのは、奇異な人生をたどりやすい。
愛されないまま棄てられる子もいるだろう。―――さらに言えば、臓器移植の献体として闇に葬られる子どももいる。
闇のマーケットに流れた子どもの行方を追うのは、想像以上に困難なのではないだろうか。
彼らの臓器を移植された者は、どうなるだろう。
血液輸血が、どういう変化を起こすだろう。
すぐには影響がなくても、それが次世代へ何ら遺伝子的な影響を及ぼさないと――誰が断言できるだろう。
こんな状況で、――増殖し続けるR707型遺伝子を、人の手によって制御することができるのだろうか?
そんな不安を抱いたまま、僕らは後始末――証拠隠滅とも言うがね、そんなくだらない作業に追われ続けていた。
・
・
失意のまま、荷造りに追われていた僕のところに――真宮博士から連絡があったのは、昨夜のことだ。
彼は忙しない口調で言った。
「J200850rtop-2の行方を知りたい」
その記号は、人口受精時に使用した遺伝子のコードを差す。彼が指定したのは、一世代目に誕生した子どものことを指していた。
「一体何が起きてるんです」
僕は聞いた。
「それは知らない方がいい、私もつい先日まである機関に拘束されて取り調べを受けていた――無事に日本に戻りたければ、余計なことに首をつっこまない方がいい」
博士の口調はそっけなかった。
僕は直感した。博士は間違いなく、僕らの知らない事実を知っているのだ――だからこそ、一年以上も前にチームを抜け、にも係わらず身柄を拘束されていたのだろう。
だから僕は、重ねて聞いた。
「j200850rtop-2と、喜屋武リーダーの自殺は、何か関係のあることなんですか」
「ないと言っても信じないだろう。君に――僕らのチームが生み出した生命への尊厳の気持ちがあると信じて、私は、君を頼ることにした。何も聞かないでくれ、そして誰にも漏らしてはならない。私は喜屋武さんの遺志を護らなければならない。それが――私の犯した罪の唯一の贖罪なのだから」
「教えてください、喜屋武さんはなんで自殺なんかされたんです。遺志ってなんなんですか。研究は――まだ、未完成だったのに」
「だから研究は完結したのだ、……喜屋武さんは、自らの死でそれを証明した。それが彼の良心だと僕は信じる」
そして、真宮博士は――僕に、あるコードを教えてくれた。
それは、ラボの倉庫中にある、廃棄処分用のパソコンを開くためのコードだった。
パソコンは処分したまえ――博士は強い口調でそう仰られた。
「そして、君も見た事は全て忘れるのだ、そうでなければ、一生日の当たる場所は歩けないぞ」
僕は――言う通りにした。
倉庫の片隅に、カバーの掛けられたノートパソコンがあった。起動しても何もない、一見空っぽのパソコン。けれど、暗証コードを入力すれば、ある記録が呼び出される仕組みになっている。
喜屋武さんのしたことだ。僕には察しがついた。喜屋武さんは、こんな風に、自らのパソコンにいくつものトラップを仕掛けることが好きだったからだ。
出てきたのは、プロジェクトの卵子提供者と、それによって誕生した者たちの追跡データだった。僕は息を呑んだ――それは、あの黒服の男たちが、喉から手が出るほど欲しがっていた情報だったからだ。
震える手で、僕は真宮博士に言われたナンバーを検索した。
?
検索結果:該当者1
J200850rtop-2 ヨハネ・アルヒデド 男性
?
出てきたのは、該当者の氏名と生年月日、誕生した病院名、そして現住所だけだった。
ロシア在住となっている。病院も名称から察するに、その国のものなのだろう。
Jが頭文字につくというとは、卵子提供者が日本人――生まれた子どももまた、黄色人種か、もしくはハーフであることを意味する。
とすれば、両親のどちらかが黄色人種だったのだろうか――そんなことを考えながら、僕は指示どおり、大慌てでその記録を手帳にメモした。
おそらくこのデータは、数秒後には自動的に削除される仕組みになっているからだ。喜屋武さんという人は、コンピュータープログラミングに精通した人だったからね。そんな仕掛けくらい朝飯前でやってしまうんだ。
メモして……そして気がついた。
真宮博士の言う「行方」というのは、J200850rtop-2の所在ではないのだ。 博士は――J200850rtop-2の複製遺伝子の行方を知りたがっていたのだ。
そう、一世代目の子どもたちは――全員クローン遺伝子が作られていたのだからね。
真宮博士は、J200850rtop-2ヨハネ・アルヒデドの複製された遺伝子がどこで誕生したか、その行方を知りたがっていたのだよ。
こんな基本的なことに気づかないほど、僕は焦って緊張していたわけだ。大急ぎで再度検索を試みたが、結果はno objectだった。―――僕の検索の仕方が悪いのか、そもそもデータが入力されていないのか。
落胆しながら諦めかけようとして――僕はふと、―――メモした番号に眼を止めた。J200850rtop-2。
−2というのは、同一人の受精卵を用いたことを意味する。
一人の女性から、二つの受精卵を取り出し、別々の精子と体外受精を行ったとことを意味する。
とすれば、J200850rtop-2というのは枝番だ。枝番ではなく、J200850rtopとして一括してデータを呼び出してみれば、関連項目として目的の情報も出てくるかもしれない。
僕はキーを叩いた。
頭文字がJ、というのは、前記したが、日本人女性の卵子を用いた事を意味する。
卵子提供者である女性が、単に卵子のみを提供したのか、母体も併せて提供したのか――それは不明だが、少なくとも、その日本女性は、立て続けに二度、卵子を提供したことになる。
卵子提供がビジネス化しているアメリカでは、早々珍しい事例ではないが、体外受精に関する法改正ができて間もない日本では、それはレアなケースだった。
数秒後、データはいきなり画面に姿を現した。
・
検索結果:該当者1
卵子提供者 喜屋武聖美 age22
詳細は以下をクリックしてください。
J200850rtop-1
J200850rtop-2
喜屋武。
僕は凍りついていた。
沖縄では珍しい名前ではないのだろう。しかし――これは、ただの偶然なのだろうか。自殺した喜屋武さんは独身だった。この人は――喜屋武の何に当たる人なのだろうか。
喜屋武、聖美という女性は、提供した翌々年には死亡していた。病死、とだけ記されている。
時期的にみて、彼女が提供した卵子が人として誕生した直後に死亡した――ということだろうか。いや、この件に関しては、君の方がよく知っているのかもしれないが。
J200850rtop-1。
彼女の卵子によって誕生したもう一人。
僕は、そのコードをクリックした。
直後に現れた名前を見て、喜屋武清美から誕生したもう一人の名前を見て、僕は、雷に打たれたように、全ての動きを止めていた。
それが――君の苗字と同じだったからだ。
先日遭ったおり、君が嬉しそうに話していた、今年七つになる娘さんと同じ名前だったからだ。
時間切れだった。わずかな瞬きと共に、画面はそこで暗転した。
僕は――動くこともできなかった。息をすることさえも。
・
J200850rtop-1 右京奏 女性 日本東京都在住
・
潤一郎、それは、君のたった一人のお嬢さんの名前だったのだ。