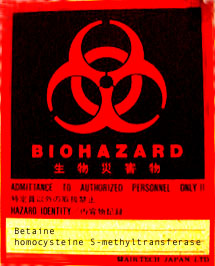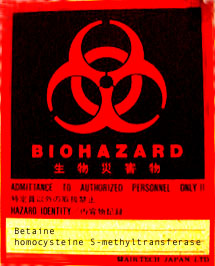ひさしぶりにメールをしている。
あれだけ苦楽を共にした仲なのに、君とは大学以来会っていなかったな。研究ひとすじだった君が、まさか政治家へ転身していたなんて思ってもみなかった。本当に驚いたよ。
僕は日本の世情にうとくてね、それに、こちらの生活環境は、なかなか外の情報に触れることができない特殊なものなんだ。本当に先日は失礼した。
先日再会して、話ができたのは――何かの因縁というか、運命のようなものだったのかもしれない。筆不精の僕が、何年かぶりにメールを送る理由は、最後まで読んでいただければ判ると思う。
こうしてパソコンの前に座って指でキーを追いながら、僕は今、後悔と懺悔と苦衷で息苦しいほどなのだ。
このメールは、ある施設のホストをいくつも経由して、発信元がわからないようにしてある。内容を理解したら、すぐに削除してほしい。ことは国家機密に係わるものだから。
こんな形で、日本の政治家である君に、情報を漏らしたことが発覚すれば――僕は生涯ペンタゴンに拘束され、生きて日本に帰る事は難しくなるだろう。
大げさな言い方ではないよ。それだけまずいことが起きている――いや、僕自身がそれに係わってしまったんだから。
・
・
僕が大学時代、変わり者だと嘲笑されながら、ずっとクマムシの研究を続けていたのは覚えているだろう。
当時のあだ名もクマゲだった。もっともそれは、僕の外見からきたものかもしれないがね。
君も知ってのとおり、クマゲノムの解析は、二千年の初めからちょっとしたブームになった。が、予算の割りには実用化が難しいということで、すぐに立ち消えとなってしまった
けれど僕は、クマムシという脅威の生命種の存在を知り、天啓に近い感動を覚えた。僕はずっと提唱し続けてきただろう。
クマムシは、神の域に達した生物の末裔だと。
生命が何故、この地球上に突如現れて繁栄したか――その原始細胞は何処から来たものなのか。
地球誕生に伴うカオスの中で自然発生的に誕生したというのが、定説だがね、そんなものは憶測だ。
他の可能性がないものだから、その説だけしか残らなかったという消極的な理由にすぎない。
なぜなら、宇宙から飛来したものだとすれば―――その生命体は人知を超えた技術によって運ばれてきたか、もしくは真空状態で、何百年も生息することが可能な細胞を持っていなければならないことになるからね。
そう――SF的な発想をしないと無理なのだ。
しかし、クマムシならどうだろうか。可能なんだよ、―――彼らの能力をさらに進化させれば――それは理論上可能になるんだ。
・
・
むろん、今いる種では無理がある。現実家の君ならそう言いそうだ。
が、太古の系統樹には、今と全く異なる種のクマムシがいたと考えても不思議じゃないだろう。
絶対零度にも、高温にも、真空にも高気圧にも――そして、高レベルの放射能にも耐え得る生命体だ。まさに、奇跡の生命体なんだ。彼らが何万年も前、今よりさらに優れた能力を持っていたと――そう仮定したってかまわないはずだろう?
君はよく笑っていたね。
発想は敬意に値するが、複雑さがまるで違う、ヒトへの実用は不可能だよ、と――。
そう、僕も内心では諦めていたさ。
僕の目指す研究を実現するには、実に何十億もの予算と、何世代にも渡る交配、動物から始まって、人体の許可が得られるまで――……気の遠くなるほどの長期的な観察が必要とされるからね。
少なくとも生きてる間には無理だ。だったら山のようにクマムシの論文を書いて、少しでも世間にその必要性を認めさせてやる――僕はそんな理想に駆られ、手当たり次第に論文を書いては発表したよ。
ほとんど無視されたがね――ただ、それが最終的には効をなした……と言うべきか。
あれは、僕が二十歳の夏だった。……いきなり届いた一通の手紙が全ての始まりだったんだ。
・
・
それは、アメリカに本社を持つ、ジェイテック社というバイオテクノロジー関連の会社からの採用通知だった。
貴殿の発表されたクマムシの研究成果におおいなる関心を持つ、この分野において、我々は全く未知のバイオ製品が生成できると信じている。是非貴殿を研究員の一名として我が社に招聘したい――。
そして、面接の日時と航空チケットが同封されていた。
驚いたよ、しかし正直、小躍りしたいほど嬉しかった。会社の概要も同封されていたがね、名前は初めて聞いたが、大資本の会社だし、どうやらバックには政府の援助もあるらしい。創始者の一人が、米国立衛生研究所の元所長だったからね。
その週の終わりには渡米し、……翌月には、社員としての契約を交わしていたよ。
全てを理解した上でね。色んな誓約書にサインして――その時思ったよ、僕はもう、二度と日本には戻れないんだってね。
・
・
以下の内容は――君の胸ひとつにしまっておいてくれたまえ。
君も知ってのとおり、ジェイテック社は、先月会社更生法の指定を受け、僕をはじめとする研究員は全て解雇され、政府の研究施設に配属された。
僕は――上司の強い勧めを蹴って、帰国する道を選んだ。
おそらく日本で、僕は自由な発言を禁じられ、しばらくは監視される日々が続くだろう。
無論、向こうで何度も宣誓したように、知りえた秘密は、生涯口にするつもりはない。
しかし――僕は、……ジェイテック社の誰もが、おそらくペンタゴンでさえ知り得ない秘密を、僕は知っているんだ。
僕に不慮の事故があれば、この秘密は永久に闇に葬られてしまうだろう。
それだけは許されてはならないと思う。―――切に思う。
僕は君に伝えたい。許しを請うつもりはない、ただ、伝えなければならないのだ。
僕が犯してしまった罪の全てを。
・
・
結論から言うよ。
ジェイテック社で、僕が与えられたのは、――宇宙から飛来した――と言われる、ある生命体のDNAを、人体に組み込む、トランスジェニックプロジェクトだった。
プロジェクト名は、Human beings' hope……人類の希望。
素晴らしい名前だ、僕は激しく感動した。皮肉なものだ、その名前が、同時に絶望を招くことになると、当時は誰が想像しただろう。
プロジェクトの目的は、僕が唱えていた理想と同じ――人という種を、宇宙空間で長期に渡って生存させること。
人という種のタネを、この宇宙に広く散布すること。
<彼ら>の持つ特質が、あまりにクマムシのそれと似ていたから、僕の論文と研究成果が米国政府の眼に留まったんだろう。
<彼ら>―――Them、それが、未知の生命体を呼ぶ時の、我々の間の通称だった。
僕の推論が正しかったのか、それとも全く異種の系統樹なのか――僕が実際触れることが出来たのは、保存状態の極めて悪い、DNAの断片にすぎなかったからね。だから、<彼ら>がクマムシとどう関連するのか、正直に言えば全く未知だ。
ただ、判っているのは、
・
<彼ら>は二体の雌雄であり、1970年代の終わりごろ、アメリカ政府があるルートを通じて極秘に入手したものであること。
体型、器官、機能、細胞、DNAは人類のそれに極めて近く、同じ系統樹の生命体だとみなせる範囲であること。
全身を厚い細胞壁で覆われ、体内の水分を自由にコントロールできること。
変体時には、体水分の九割以上を自然放出し、皮膚を硬質化させることにより、超低代謝状態で、長期に渡って生命を維持することが可能となること。
変体時、細胞の変化により、雄は赤黄色に、雌は青白色に発光、体高、体表も膨張すること。
感情のあるなしは確定できないが、雄体の死亡と同時に雌体も死亡したことから、精神的な部分で同調している可能性が強いこと。
記録によれば、彼らは捕獲後、解剖途中に変体を起こしたものの、雄体が途中で死亡。雄体の死亡後、雌体も変形を解いて死亡した。となっている。
さらに、発見時の記録によると、彼らは発光状態のまま、空中を猛スピードで移動していた……という証言もある。これは信用おけるものではないだろうが。
・
・
多分……当時の研究者たちは、彼らが仮死状態であることを見抜けずに、死んだものとみなして解剖しようとしたんだろうね――莫迦な奴らだよ。
当時の記録がずさんだからね。画像も荒くて――八ミリフィルムで、もう見られたものじゃないんだ。保存も悪くてね、再生も不可能らしい。
僕の推測なんだが、<彼ら>は捕獲時、クマムシで言うところの包のう状態だったんじゃないだろうか。
細胞壁が厚いっていうのが、その状態に酷似しているし、捕獲してすぐに解剖に回されたのも、死んでいると見なされたからだろう。
要は冬眠状態だったわけだ。
残念な話だよ、慙愧に耐えない。
そのまま生かしておけば、間違いなく、生きた彼らに会うことが出来たのに。
・
・
実験データはなかったが、彼らがクマムシと類似したものなら、当然高気圧にも、高レベルの放射能にも耐えられることになる。
真空状態でも生延びることが可能だろう。
そう、まさに人類の希望だよ。
人類が、それと同じ能力を身につけることができら――まさに希望だ、夢の実現だ。
僕は燃えた。
がむしゃらに研究した。寝食を忘れ、ひたすらラボに閉じこもり、―――僕のように、世界各地から呼び寄せられた10名のプロジェクトメンバーと共に、この神をもおそれぬ行為に没頭した。
むろん、上手くいくはずはない。最初の数年は――ここで記すのもはばかられるほど、それはひどいものだったよ。乾ききった砂でバベルの塔を建てるようなものだ。
何しろ高等生物のさらに上を行く生物の遺伝子DNAだ。君も知っていると思うが、そうそう宿主DNAの形質転換は起きやしない。加えて<彼ら>のDNAは信じられないほど劣化しているのだ。
最初は保存状態が悪かったのではないか、と思ったがそうではない。おそらくそういう仕組みなのだ。そういう性質なのだ。外気にさらされた途端、体内の細胞はあっという間に死滅してしまう――地球外生命体であるがゆえの特質なのか。いずれにせよ、扱いは慎重の上にも慎重を期さなければならなかった。
1980年代から遺伝子の解析は進められていたらしいがね――残念ながらその過程が、逆に現存する遺伝子の9割方を死滅させてしまったのだよ。
この研究が、何年にも渡って頓挫していたのはそのせいもある。現存遺伝子は塩基配列があちこち抜け落ち、そのままでは再生さえできないありさまだったからだ。
そういった状態だったから、僕らのチームは、概ね二つに分かれていた。
遺伝子再生チームと、トランスジェニック実験チーム。
再生チームが、DNAの欠けた部分に様々な種の遺伝子を組み込んで複製し、コンピューターシュミレーションで再生させる。
僕ら――実験チームは、その試作品を実際にマウスを用い、トランスジェニック実験を行う。
気が遠くなるほど沢山のマウス胚に、組換え遺伝子を注入したよ。実際、マウスアレルギーになる寸前だったね。笑い事でなく。
最初の二年は、全てのマウスが拒否反応を起こして死亡した。
再生チームは、次々と試作遺伝子を作り出したが――それをマウスに用いる僕らは、正直憂鬱な作業の繰り返しだった。
最初の異変が起きたのは、ラボに入ってから五年目のことだ。そしてそれは、劇的な変化だった。石ころが、ある日突然宝石の原石に変化した――そんな感じだ。
B−707型と命名された試作遺伝子を使った結果、成長ホルモンと右脳の一部に異常な発達が見られるマウスが誕生したんだ。その意味は判るだろう――?そう、いわゆる天才マウスの誕生だよ。
経過観察の結果、さらに驚くべきことが判った。新型マウスの生殖率は、従来種の約五倍だったんだ。ネズミ算どころの騒ぎじゃない。
こんなものが、まかり間違って施設から漏れてしまえばどうなると思う?最悪のバイオハザードだ。どんなに駆除しても追いつくものじゃない。
幸い、ジェイテック社のラボはP4レベルの封じ込めが可能だったから、問題はないと――信じてはいたがね、それにしても、背筋が寒くなるような光景だったよ。
一匹でも生態系に紛れ込んだら――取り返しのつかない、系統樹の破滅に繋がりかねないからね。
とにかく、今回の707型も失敗だったわけだ。ただし成果はあった。次へ繋がる希望はできた。―――僕はそう思ったし、実際、707型は廃棄された――はずだった。
ところが、そうじゃなかったんだ。
いや、正確には僕らには何も知らされていないところで、―――707型遺伝子は<試用>されていたんだよ。
猿どころの騒ぎじゃない、ダイレクトに――人体に、だ。
ジェイテック社が抱える精子バンク会社が合衆国全土にいくつかあり、社が有する附属病院で体外受精を行っているのを知っているだろうか。
保存精子を使った体外受精の――その過程の中で、707型――正確には、再生チームのリーダーである喜屋武涼二という男が――繰り返し改良を加えた<707R型>という組換え遺伝子を、受精卵に注入したんだ。いや、していたんだ。
喜屋武の指示で、実際に注入作業に従事していたのは、同じく日本人で、喜屋武と共に、再生プロジェクトに従事していた――真宮伸二郎という新鋭の科学者だった。
僕は、真宮博士とは非常に親しい間柄だった。ラボにいた日本人が少なかったせいもある。よく二人で食事をしたり、飲みに行ったりしたものだ。
実際、米国各州に分散するジェイテックの関連会社で、どれだけ人間が、その忌わしい作業に与していたのかは判らない。が――少なくとも、プロジェクトチーム内でその事実を知っているのは喜屋武リーダーと真宮博士の二人だけだったと思う。
おそらく――上から、ペンタゴンの上の人物から、喜屋武が直接指示され、真宮がそれを手助けしていたのだろう。
彼らニ人が、ジェイテック本社に附属してる病院で、―――培養中の受精卵に707R型遺伝子を組み込む作業の全工程を――たった二人でこなしていたんだよ。
彼らは、自分の手助けをしてくれる、信用のおける人材を探していたんだ。
僕が全てを打ち明けられたのはそのせいだと思う。
・
・
真宮伸二郎――名前は聞いたことがあるだろう。
東京大学理工学部出身で、以前、ネイチャーに、遺伝子と進化の相互作用という論文を発表されていて、僕もおおいに感銘を受けたことがあったからね。
実際会ってみると、まだ若い人だが、寡黙でね。
大人しそうに見えてどこか怖いところのある人だった。しかし、自説のこととなるとこれがまたよく喋る人なんだ。秘めた理想に燃える若き科学者だ。僕らはすぐに親しくなった。いや、親しくなったというのも僭越だな。
僕にとって、博士は目標のような――尊敬すべき存在だったから。
・
・
喜屋武涼二のことは僕も全く知らなかった。
まるで女のような、綺麗な顔をした男だった。華奢なくせに、見上げるほどの長身で、目つきが怜悧で――性格も相当きつかった。
チーム内では常に孤立し、結構嫌われていたと思うよ。
ただし、その頭脳には、誰もが敬服して逆らえなかった。
飛び級でメソポタ大を出たのが驚くなかれ、16だよ。ジェイテックに入る前は、軍の研究所でずっと生物兵器の開発に携わっていたらしい。だから科学者としては、全く無名の存在だったのだ。
正真正銘の天才だよ。
あのプロジェクトは、間違いなく喜屋武の頭脳が成功させたものだ――そう、それを成功と呼べるのならね。