|
4
「ユーリは、……強い人なのね」
夜がゆっくりと更けつつある。
夕食に誘うと、男二人は慌てた態で手を振った。コーヒーのお代わりを淹れながら、志津子は微笑して呟いた。
「ユーリが、ですか」
永瀬が不思議そうに瞬きをする。
「ええ」志津子は席に座りなおした。
「上手く言えないけど、どんな境遇でも生きる術を知っているような気がする……。一見、ひどく憐れなように見えて、色んな人に護られている。逆に強かな気がするのは私だけかしら」
「……強か……」
コーヒーを持ちあげると、永瀬は、少し心外そうな顔で首をかしげた。
「確かに、ユーリは、幼少時代はフレグを、 十代になってからはグレシャムを頼って生きていますけど……。なんていうのかな、誰かに依存したいというよりは、とにかく、愛されたいと切望しているような気がするんです」
「愛されたい……」
繰り返して、志津子は呟く。
「ユーリは寂しいんです。すごく寂しい……。両親に愛されなかった分、自分を本当に愛してくれる人を、常に探し求めているような気がします。だから、誰かに依存せずにはいられない そんな感じじゃないのかな」
「でも、グレシャムという人は、ユーリを虐待していたんでしょう」
「うん、そうです。でも」
永瀬は、もどかしく首をひねった。
「ユーリという人は グレシャムに対してでさえ、愛してほしいと切望していたんです。そんな気がする……。彼が死んだ時、ユーリはひどく取り乱して、我を忘れてクシュリナ姫にすがろうとしたくらいですから」
「……それは…」
言葉を途切れさせながら、やはり退行催眠はこれで最後にしよう、と志津子は内心決意していた。
永瀬はすでに、門倉雅の残した<文章>を読んでいる。あの中には、グレシャムの名も、そして死のことも書かれている。永瀬に、それを再体験させるのは、余りに残酷すぎる気がした。
志津子がそう言うと、永瀬はそうかなぁ……と、残念そうな顔をした。
「俺自身は、この続きが知りたくてたまんないっスけどね。それに、前も話したと思うけど、グレシャムの死んだ後の夢なら、一回見てるんですよ、俺」
「グレシャムさんのこともそうだけど、他にどんな爆弾がでてくるか予想がつかないじゃない」
志津子は苦く笑って見せた。
「あなたが、催眠の最後にみた得体のしれない怖いもの。その正体だって判らないままだわ。なんにしても、しばらく様子を見たほうがいいと思う」
「様子?」
「また、怖い思いをさせるかもしれないけど、君の夢にそのあたりの情報が出てくるまで、待ってみましょうということよ」
「うーん……」
永瀬は軽く息を吐き、なんとも残念そうな顔になった。
「なんていうのかなぁ、一人で夢を見てた時は、それが俺自身の経験っていうか……過去というか、前世かもしれないっていう怖さがあったんですけど」
「うん」
考え込んだような永瀬の言葉の続きを、志津子は待った。
「今日の感じは、なんだか違って。なんていうのか、確かに俺はユーリと同調してるんだけど、結局は、別のところからそれを見てるって言うか……俺自身がユーリなんじゃなくて、ただ、ユーリの思考が俺に被さってくるだけって言うか」
もどかしく言葉を捜す青年を、志津子は驚きを隠して見つめていた。
私が、感じた感覚と 同じだ。
「だからかなぁ、すごく深いところでは、俺、結構平気なんですよね。確かに怖かったり、嫌だったりしたけど、……俺のことじゃないって感覚が、今回はすごく強かったから」
あ、意味わかんないですよね。すみません。
そう言って苦笑する青年を、やはり志津子は感情を抑えたまま、見つめていた。
彼の感覚が何を意味するのかは、今の時点で計りようがない。
「ま、そんなことはさておいてですね。俺が知りたいのは、俺と クシュリナ姫のその後なんですよ。夢の断片で見た……その、俺が、彼女と、その」
「セックスした、という部分ね」
「は、はっきり言いますね」
永瀬は少し顔を赤くした。
「そこんとこは、もう怖くて思い出せないです。だって俺にしてみれば、相手は、あの門倉雅ですからね。あれこそ、タカミヤユーリの悪夢であってほしいと思ってるくらいですよ。マジで」
「永瀬君は、彼女が怖いの?」
「彼女?」
「雅ちゃん」
「………」
相手の言葉を返す当たり前の質問なのに、その刹那永瀬は、実に奇妙な顔つきになった。
「まぁ……、さほど面識があるわけじゃないけど、……琥珀をいじめてた頃の記憶が強烈なのかな」
なるほど。
志津子は少しずつ、自分が冷静さを取り戻しつつあるのを感じていた。その部分は永瀬の感覚、というより、ユーリにとっての思い出したくない過去ということになるのだろう。
「ユーリは……クシュリナ姫の信頼を裏切ってしまうのね」
「…………」
永瀬は軽く息を吐き、気を紛らわすようにコーヒーを飲みほした。
「あと気になるのは……アシュラルって奴のことですね」
目をすがめ、空を睨むような眼差しになる。
「アシュラルっていうのは、琥珀にうり二つなんですよね? 俺の夢の中には、まだ出てきていないと思うんだけど……名前だけなら何度も出てきてるんですよ。俺、 いや、ユーリは、そのアシュラルって男をものすごく憎んでいる。 というより、激しい敵対意識を燃やしている」
「そうなの?」
志津子は、先日、病室で、琥珀を見下ろしていた永瀬の横顔を思い出していた。
その部分は、おそらくだが、同調している。
「……その理由は、単にアシュラルがクシュリナ姫の婚約者だからという……そんな単純なものじゃないような気がするんですよ。なんだろう、なんか……もっと、別の理由があるような」
しばらく無言で空を睨んでいた永瀬は、やがて困惑した風に、頭を掻いた。
「すみません、見当もつかないや」
志津子もまた、緊張が緩んだように失笑していた。
「まぁ、今の情報だけで考えても仕方ないわ。 とにかく、不本意かもしれないけど、君の次の夢を待ってみましょう」
「えっ、じゃあ、もう催眠はやってくれないんですか」
「今の段階では、ね」
立ち上がった志津子は、不満げな永瀬の背を軽く叩いた。
「危険すぎるし、再々風間さんにご出動願うわけにはいかないから。でも、催眠の代わりに、今夜から、君が例の世界に関する夢を見たら、すぐに私に電話しなさい。何時でもいいし、何時間でも相手になってあげるから」
「すぐにですか?」
永瀬は驚いた顔になる。
「だって、瀬名先生だって、仕事とか……色々」
「朝の九時以降はメールにしてくれる? 時間がとれたら私のほうから掛け直すわ。夢の話を聞いて、もしそれが必要だと思ったら、今日みたいに、催眠で思い出せない部分を探って見ることにして……。当面はそれでいいかしら?」
「……いや、僕はいいですけども」
永瀬はそこではじめて、不審そうに部屋の中を見まわした。
「先生は本当にいいんですか、ご家族とかのご迷惑にならないでしょうか」
「いいのよ」
志津子は笑顔で肩をすくめた。「実は昨日、離婚届を出してきたばかりなの。私のご家族は、入院しているあさとだけだから」
5
「離婚、ですか」
永瀬が帰った後、風間は待ちかねていたように切り出した。
「今までだって、実質離婚していたようなものだけどね」
志津子は手早く、テーブルの上を片付け始める。
「別に立ち入ったことを聞くつもりはありませんが、どうして、また」
風間は言いにくそうに語尾を濁した。 こんな時に、と言いたいのだろう。娘の意識がまだ、戻らないのに、と。
「……あさとが、危篤に陥った時、彼、北海道にいたのよ」
思い出すだけで、眩暈がするようだった。あの時の ICUでの娘の姿。緊迫した掛け声。電気ショックの響き。
けれど娘は、それから数分後、奇跡的に脳と心臓の機能を回復させ、自発呼吸も取り戻したのだ。
意識は戻らなかったが それでも、また以前と同様、穏やかに眠り続けている。
「愛人と旅行中だったというわけ。……ようやく思いきりがついたの、これまで迷っていたのが嘘みたいにね」
風間は何も言わない。
「とにかく、私のことは気にしないで。かえってすっきりしたくらいだから」
「次に、永瀬君をご自宅に呼ぶ時は」
やがて、溜息まじりに風間は言った。
「必ず僕も同席させてください。正直、あんなに危険なものだとは思わなかった。退行催眠を掛けられた人間の……喜怒哀楽というのが」
泣いたり、わめいたり、そして怒ったり。催眠中見せる人の表情には、ひどく生々しいものがある。例えて言うなら、一種の憑依に似たものなのかもしれない。
「いいんですか、風間さん」
驚きを飲みこみながら、志津子は男を見上げている。
「一応警察関係者としては、あんな危険な現場に先生一人きりにはさせておけませんよ」
憮然と言い切り、風間は立ち上がって上着を羽織った。
「………感謝してますよ」
「え?」
「僕は、多分、眼を逸らそうとしていた……見たくないものから逃げようとしていた。先生の言う通りです。小田切の心の底にあるものなんて、本当は何も判ってはいなかったのに」
顔をあげ、今日、初めて彼は、彼らしい笑みを見せた。
「永瀬君みたいな子供が頑張って耐えている姿を見たら、心底恥ずかしくなりましたよ」
「…………」
そのまま一礼し、風間はソファの上の鞄を取り上げる。
「帰ります。少し、気になることが出てきましたから」
「何か、ありましたか?」
「永瀬君というのは、頭のいい青年ですね。さきほど、先生が台所に立たれた際、少し話をしたんです。門倉雅の残したノートのことで」
「……ああ」
門倉雅が暗号めいた文字で書き残した前世の記録。
それを 志津子は、雅の中の別人格が、他の人格に読ませるために創作したものだと推理した。自らのトラウマを「記憶の書き換え」によって治癒させるために。
スーツの襟元をそろえながら、風間は続けた。
「彼、言っていましたね。もし 別の人格に読ませるために<文章>を残したのなら、なんていうのかな、交換日記のような形式のものが残っていてもいいんじゃないかって」
「……交換日記、ですか」
「だって、彼らは暗号を使って会話していたわけでしょう。なのに、一方的に書かれた文章しか残っていないのは、不自然じゃないですか」
志津子はわずかに眉を寄せる。
「まぁ、そうですけど、結局、別人格者同士の会話が成立しなかった可能性だってありますし……」
「いや、それにしても、何か どこかに、意思の疎通のきっかけとなった文章が残っていないと、おかしいとは思いませんか。だってそもそも彼らは、一人の人間なんですよ。会話で意思疎通なんてできやしないんです」
そうか……。
確かに、そうだ。
「門倉家から押収した資料を、もう一度調べてみます」
風間はわずかに白い歯を見せた。
「僕が見せてもらったものは、ほんの一部にすぎませんからね。一課の横谷君に協力してもらいます。では!」
慌ただしい足音と共に、扉が閉まる。
なんて単純な人だろう。志津子は半ば唖然としている。では風間は とことん付き合ってくれるつもりなのだろうか。
志津子は苦笑し、そしてようやく安堵していた。
本当は、風間にここで引いて欲しくなかった。だから今日、彼を騙し打ちのように呼び出して同席させたのかもしれない。
心に傷を負ったままになっているのは、小田切だけではない。
高校時代、返すことのできない大きな負い目を抱いたまま 動けなくなってしまった風間もまた同じだと、志津子はそう思っていた。
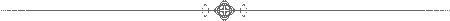
風が……吹いている。
冷たくて、寒い。
ここは、何処だろう 。
俺は灰色の空を見上げる。嫌な場所だ。初めて来た場所のはずなのに、胸がざわついて仕方がない。山際に連なる低い家々は、みなくすんだ灰色で、吹けば飛ぶようなテントみたいな布に覆われている。
真昼間だというのに、行きかう人は誰もいない。死者の……集落。灰色の邑。
俺は、ひどく苛ついている。
そう、何かを……気にしている。時間? そうだ、時間だ。夜になるのを畏れている。怖いんだ、そう 夜になると、あいつらが出るから。
いや、違う。それだけじゃない。ひどく不安で、むかついている。一言で言えば、面白くない。
何故だ?
そうだ……。
俺は誰かを、待っているんだ。
小汚いテントみたいな小屋の前で、寒さに震えながら、……待っている。
あの女が出てくるのを。
饐えた扉が、軋みながら開いた。女が 深くケープを被りなおして、ようやく小屋の中から姿を現す。
「……終わったわ」
「随分時間がかかるんだな」
「………」
「それで、手に入れたのか」
「ええ。マリスの秘伝中の秘伝の媚薬よ。もう、これで失敗はないわ」
「………」
「帰るわよ。いつまでそんな所に立っているつもり?」
女はそう言ってきびすを返す。
俺はその後を追い、待たせていた馬車に、女と共に乗りこんだ。
隣に座る女の身体から、熱の余韻が伝わってくる いや、俺の身体が冷えているせいかもしれない。
「……馬鹿げた取引だな、そのためにお前は、自分の身体を売ったのか」
皮肉をこめて俺は言った。女の横顔が微笑している。
「下品な言い方ね。性戯は、秘伝を手に入れるための儀式なのよ」
「……お前は」
俺は、苦渋の溜息をつく。
「馬鹿だな。本当に馬鹿な女だよ。今までもそうやって、麻薬やら毒薬やら、その処方を手に入れてきたのか」
「そうよ。それがどうかして?」
女は呆れたように眉を寄せた。
「何を怒っているのか知らないけれど、誰のためにこの薬を手に入れたと思っているの」
「怒っている? 俺が?」
俺は言葉につまり、ますます苛立つ気持ちを、拳を握って押さえつける。
「全てはあなたを助けるためじゃないの。マリスの皇子様」
「………」
含んだ笑いがして、冷たい指が頬に触れた。
「まだお判りにならないの? そのために私は生まれ、私たちは出会った……」
そうだろうか?
「私はね、ずっと、あなたが金羽宮にやってくるのを待っていたの……。私たちの予言を、実現させるために」
そうだろうか? 本当に?
全てが俺のためだとは、どうしても思えないどす黒い感情が、女の中で蠢いている。
今までの女の行動全てを振り返った時、どうしても理解できない不思議な執念を感じずにはいられない。
それは……例えて言えば。
「どうして、そんな目で私を見るの?」
柔らかな女の眉が、不思議そうに寄せられた。
「判っているの? あなたがどうして、こうも簡単にナイリュの王位を手に入れることができたのか。あなたのために、クロウが影で何をしていたか」
ケープの下からのぞく、けぶるように美しい眼差し。
「三鷹家に養子として入りこめたのも……反対していた親族が、都合よく死んでくれたのも、対立候補だったサライ将軍が病に倒れたのも……」
女は、楽しい出来事でも思い出すかのように、ゆっくりと指を折る。
「あの純情可憐な京極レイア様のご婚約者、ミュール様があっさりとご病死なされたのも……それがどうしてだか、あなたはよく、ご存知のはずでしょう?」
「……ああ、 ああ、知っているさ。だからどうした、それがどうした!」
言われるまでもない。よく知っている。王位継承の最後のライバルだった白川家の嫡男、ミュール。突然の病死が発表されて、必然的に、王位はたった一人残された王族の血を引く者が継承することになった。
それが 俺だ。
「言ってみろ、それを俺が望んだとでも言いたいのか。俺がそうしてくれと一度でも頼んだことがあったのか、お前に、お前らに!」
「……では、望まなかったとでも?」
憐れむような冷笑が返される。
「あのまま、蒙真族の血を引く穢れた子と、笑われて蔑まれ、そうして、謀殺されてしまうことがお望みだったとでも?」
「………」
「あなたは、そんな結末を望んじゃいないわ。……ユーリ」
そう……望んでは、いなかった。
俺は、眉を寄せたままで女と自分の足元をみる。
では、俺は何を望んでいたのだろうか。
ナイリュにあって、史上初めて忌わしき銀髪と灰の目を持つ王になることだろうか?
幾多の血と反対を押して、王位につくことだろうか。
いや……違う。
「クシュリナを取り戻したいんでしょう」
女の囁きが、俺の闇を蠢かせる。
「……それは」
「あなたが連れていかなかったばかりに、彼女があの後どんな目にあったか、もう一度最初から説明してあげましょうか」
俺は、何も言えずに目を逸らしている。それを言われたら、沸き起こる嫉妬で、息ができなくなるほどに、苦しい。
「アシュラルが」
「よせ」
「……どんなひどいやり方で、彼女をものにしたか思い出させてあげましょうか?」
「やめろ!」
「雨音がひどかったけど、私の耳にも、彼女の悲鳴がはっきりと届いたわ」
「いいかげんにしろ」
「助けを呼ぶ声と、すすり泣きが途中で途切れて、後は、衣擦れと息遣いだけが」
「やめろと言ってるんだ やめろ!」
目の前の女のケープを掴み上げていた。怒りで、視界に映る光景が歪んで見える。
女のケープがはだけて、艶やかな黒髪と……抜けるように白い肌、妖しく輝く瞳が現れる。
俺は そうだ、最初から、この女の正体を知っていた。
金羽宮で俺を助けてくれた、杏の匂いをまとった女。
豊満な胸の間に、血色の首飾りが揺れている。
クシュリナ……。
悲しみと絶望が胸を満たし、俺は、ただ、うなだれている。
君を……君の言葉を信じていたのに……。
君だけが、俺の希望の全てだったのに。
揺れる男の内心を見透かしたように、女は胸元の首飾りを持ちあげて、闇にかざした。
「……アシュラルの妻になったあの女は、あなたからもらった贈り物など一顧だにしなくなった」
「………」
「女って憐れね。あんな乱暴なやり方で、身体だけでなく心まで開かされてしまうなんて。すっかりアシュラルの虜になったあの女は、あなたの思いも純情も、全て、踏みにじってしまったのよ」
「もう……やめてくれ」
冷たい手が、そっと俺の頬を包みこむ。
「今度はあなたが、アシュラルからあの女を取り戻す番なのではなくて? それがどんなに卑怯で汚い手であっても、あなたにはそうするだけの権利があるのではなくて?……」
もう、逆らう気持をなくしたまま、俺は女のなすがままになる。
揺れる馬車の屋根を見上げたまま、俺はぼんやりと呟いた。
「君の言う通りにするから、……約束してくれ」
「なにを?」
「クシュリナは俺のものだ……俺の許可なしには、絶対に君の勝手にはさせない」
「それはどういう意味かしら?」
からかうような、含んだ笑いが返される。
「エレオノラのことを言っているの? 皇都ではあなたを散々慰みものにした女よ。だから今度は、あなたの奴隷にしてあげたんじゃないの」
「両目を潰して、舌を引き抜いてか。お前の残虐さには反吐がでる。いったいどうしてあんな真似ができるんだ」
「わからないの? マリスの皇子である、あなたを穢したからじゃないの」
「………」
「あなたを穢す者は、すべからく罰を受けなければいけないわ。……それが、たとえイヌルダの女皇であろうと、法王様であろうと……」
重なった身体の熱が、やがて二人の呼吸を乱していく。が、それでも女は厭きることなく、一人言葉を繋ぎ続ける。
「ヴェルツはまだ、地下牢で生きているわ。あの男は、アシュラルへの憎悪だけで、かろうじて正常を保っている。……今に、きっとあの男が役に立つ時がくるわ」
俺を見下ろし、女は、唇の端をくっきりと上げて冷笑した。
「あの男が、どんな形でアシュラルに報復するか。私は、それが楽しみで仕方ないのよ」
ぞっとした。
この女は アシュラルを愛しているのではなかったのか。
「ユーリ、……そして世界は、あなたのもの。あなたが支配する闇たちのもの……」
すっと見上げる、氷を抱いた女の眼差し。傲慢で、なのにぞっとするほど美しい唇。
俺は……女の髪を掴み、白い顎をあげさせる。
その眼が俺を誘惑するのか、それとも俺が誘っているのか。
「言っておくが、俺は、吐き気がするほどお前が嫌いだ。身体の芯まで腐っている。顔を見るだけで反吐がでる」
「私は……」
甘いくちづけ、毒を含んで、濡れた唇。俺は冷めた気持のまま空を見ている。揺れる馬車、重なる女の身体も、同じように振動している。
「あなたが好きよ、あなたがお姉様を愛して……お姉様もあなたを信頼している。それたけで、ぞくぞくするほど興奮するの」
わからない、何故この女は、実の姉を追い詰めるのに、こうも執念を燃やすのだろうか。
頬をなぞる指、首にかかる吐息。
不思議な気持だ……。鼓動が高鳴り、胸が痛むほどに昂ぶっている。
こんなに嫌いな女と、寄り添っているのに。
「抱いて……ユーリ」
「サランナ……」
俺は呟き、彼女の動きに身を任せる。
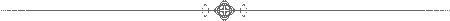
「それは……今の話は、真でございますか」
膝をついたままの男は、唸るような声をたてた。
「この憂うべき事態を、なんとかしなければなりませんわ」
女は、うちひしがれた声で言う。
蝋燭明かりだけが揺れる、暗い室内。いったいここは何処だろう。
ああ 俺は、またあの夢を見ている。
「一度はアシュラルを信じた、この私にも罪はあるのです」
悲しげな、いかにも悲痛な口調で、女は続けた。
「けれど、欺瞞を知った今は、どうあっても法王庁の野望を止めなければなりません。法王庁と、現法王アシュラルは、予言を恣意的に解し、シュミラクールを我がものにせんとしています。それだけでも許しがたい罪だというのに、……なのに、あの男は」
潤んだ瞳に、真珠よりも美しい涙が零れた。
「アデラ女皇を殺害し、蛇薬を使って甲州公の口を封じました。全ては皇室を乗っ取りたいがための法王庁の陰謀。このままでは、いずれ世界は、法王の元に統一されてしまうでしょう」
「むぅ……ルーシュめ」
きりきりと、男の口から呪詛の歯ぎしりが聞こえてくる。
「きゃつはそのために、そのためだけに、先の陛下に」
「いえ、真に憎むべき敵は、ルーシュの息子、コンスタンティノ・アシュラル」
女は、自らが神のように宣言した。
「彼の男の陰謀に気づいた私は、金羽宮で命を奪われるところを、こうしてナイリュの三鷹家にお救いいただいたのです。ミシェル様のご慈悲がなければ、今頃私も、どうなっていたか知れません」
しおらしい眼が、俺にしか判らない光をひそめ、そっと向けられ、また逸らされる。
「ご存じのとおり、皇都には、まだお姉様が残っておいでです。イヌルダの統一がなされれば、あの男にとってお姉様が用済みとなるのは必定。お姉様が、お母様やお父様と同じ運命を辿る前に、なんとしても、 なんとしても御救いしなければ」
「いかにも! いかにも!」
狼のたてがみのような髪を持つ男は、猛々しく頷いた。
「よくぞ、このフォードを信頼し、何もかも打ち明けて下された。ご案じめさるな。休戦などそもそもきゃつらを一網打尽にするための時間稼ぎ。いかな手を用いようとも、このアッシュ・ウルフが、魔王アシュラルめを討ち果たしてみせまする」
「なんと……お心強い言葉でしょう」
そっと扇で目許を隠す女の顔が、会心の笑みを浮かべていると知っているのは、隣に座る俺だけだろう。
「ただし、クシュリナ様だけは、ご無事に御救い申し上げねばなりませぬ。あの方は……私にとっても大切なお方の忘れ形見ゆえ」
「フォード様が」
扇を下ろしたサランナは、涙で潤んだ瞳で、目の前にかしづく男を見つめた。
「お姉様を、実の娘のように大切に思っていらっしゃるのは、よく存じておりますわ。……ゆえに、フォード様におすがりするのです。お心がすすまぬことはよく存じておりますが、今は奥州薬師寺家と手を組み、彼の悪魔を皇都から引きずり出さねばなりません」
「……ヴェルツは、私との盟約を破り、こともあろうに姫様を罪に陥れ、ダンロビンなどと結婚させようとした」
当時の憤りを思い出したのか、フォードの紺碧の目に、燃えるような怒りがよぎった。
「赦しがたき男ですが、今はもう、そのヴェルツもいない。乱れた奥州を法王庁に奪われるくらいなら、この私が進んで逆賊となりましょう」
サランナは、かすかに笑った。
「ウラヌスへは私が参ります。直によい知らせを、フォード様にお届けすることができるでしょう」
「クシュリナ様のことは」
それでもなお、不安を目に浮かべる灰色狼に、サランナは優しい笑顔を返した。
「ご安心なさいませ。アシュラルさえ皇都から引き離してしまえば、お姉様は、必ず私とミシェル様がお救い申し上げます。どうぞ、ミシェル様をお信じになって。これからはナイリュと薫州は、手を携えて大きな敵に向かっていかなければならないのですから」
「……三鷹家はマリスを信仰すると聞き及んでおります……。私は、邪教徒と同盟を結ぶ気はござらん。が」
ぎりっと歯ぎしりした男の目に、燃え滾るような色彩が滲んだ。
「それが法王家を打ち果たすためであれば、私は、マリスであろうと手を組むでしょう。いかな理由があろうとルーシュだけは許せない。きゃつも、きゃつが拾い育てた悪魔の寵児も、必ずや私の手で、死の制裁を加えましょうぞ」
|
|