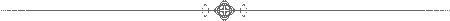 |
「気持ちを楽にして……」
瀬名志津子はゆっくりと、指に絡めたペンダントを振った。
リクライニングシートに仰臥したまま、永瀬海斗は小さくうなずく。少し、その表情が緊張している。
「さぁ、この石に意識を集中して」
永瀬は素直に視線を上向け、志津子の手の先 揺れる石を、右へ左へと追い続ける。
「あなたは、どんどんリラックスしてくる……呼吸に意識を集中して、一息吸うごとに、身体全体が柔らかくなっていくから。……そう、ゆっくり、ゆっくり眼を閉じて」
男にしては長すぎる睫。それが、瞬く度に、頬に影を落としては揺れる。
綺麗な顔をしている子だ、と志津子は改めて思っていた。
こうして薄闇の中で見ると、目を閉じた様はますます女性のように見える。
「筋肉がだんだんリラックスしてくる……思い描いて、頭の中で。顔……顎、首……腕……背中、そう、順番にゆっくりと緩めていって、さぁ、どんな感じ?」
「……身体が、沈んで行く感じがする……」
永瀬は低く呟いた。
「そう、次は頭の上に、白い光をイメージしてみて。それが……広がって行くのをイメージして、ゆっくりと……あなたの身体全体に広がって行く……」
囁くように志津子は言った。こうやって時間をかけて、<患者>のイメージを広げて行く。
「そう……。では、数を数えるわ、ひとつ数えるごとにあなたの意識はどんどん安らいで、私の声しか聞こえなくなる……十、九、八、七」
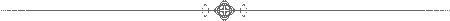
第二章 三鷹ミシェル
1
「永瀬海斗に、退行催眠……ですか」
その話を切り出した途端、風間潤は呆れたような顔になった。
「しかし、前世ってのはひとつじゃなくて、人によってはいくらもあるそうじゃありませんか。退行催眠をかけたとしても、……鷹宮ユーリとしての前世が、そうも都合よく出て来るものですかね」
そう言いながら、明らかに疑わしそうな眼で志津子を見上げる。
「永瀬君の前世を探るわけではないんです」
志津子はコーヒーを煎れながら言った。
夕暮れが迫り、少し部屋の中が暗くなりかけている。瀬名家のリビング 志津子は照明の光度を上げた。
「……じゃあ、どういう?」
はじめて上がる他人の部屋のせいか、風間はどことなく居心地が悪そうに見える。
靴を脱いだ最初も、家人やお手伝いがいないことを気にしていたようだったが、少なくとも今の志津子には、外聞について憂う必要は何もなかった。
志津子は、風間の前に淹れたばかりのコーヒーを置いた。
「そんな硬くならないでくださいよ。何も、取って食おうって言うんじゃないんですから」
「そ、それを先生が言いますか」
ようやく風間の表情がほぐれる。
志津子も微笑して、その前に腰を下ろした。
「だめですね。警察の人が、いちいち他人の部屋にあがるのにためらうようじゃ」
「だから僕は事務員であって、刑事とは違うんですよ。むしろ先生のほうが、人を扱うのに慣れていらっしゃるから……」
確かに風間の言う通り、密室で男女二人というのは、志津子には慣れっこのシチュエーションである。それが診療室であっても、自宅であっても変わらない。
「外聞を気にしてらっしゃるなら、むしろ病院のほうが困りものですわ。看護師たちは口さががないから」
「まぁ、そうですね」
風間は困ったように笑って、コーヒーを口に運んだ。
むろん、約束の場所に自宅を選んだのは、そんなくだらないことが理由ではない。今日だけは恩田佳織を始めとするスタッフらに、自分のしようとしていることを知られたくなかったからだ。
が、風間の表情の硬さは、何も女性の部屋に上がったことだけが理由ではないような気がした。部屋に入った最初から いや、電話で会う約束を取り付けた最初から、彼の態度は、いつになくぎこちない。その理由を、志津子は薄々察しているつもりだった。
「彼の前世ではなく、<夢>を探ってみるんですよ」
志津子は、自身もコーヒーカップを持ちあげながら切り出した。
「夢、ですか」
風間は少し、驚いた眼差しになる。
「あさとや、雅ちゃん、それから永瀬君の見ている夢が、本当に彼らの前世なのかどうか……、私もう、そこには踏みこみたくないんです」
言葉を切って、腕時計を横目で見る。もうすぐ、永瀬が訪ねてくる時間だ。
「踏みこめば余計に混乱するだけですからね。風間さんも仰っておられた通り、あの世界は雅ちゃんの頭の中だけに存在するんです。現実の前世ではありません。言ってみれば」
妄想が創り上げた仮想前世。
志津子がそう言うと、風間はかすかに苦笑した。
「なるほど、仮想前世とは言い得て妙ですね」
そして、不思議な微笑を浮かべて志津子を見つめる。
「先生の発想には、いつも驚かされますよ。門倉雅が、自らの精神疾患を治癒するためにバーチャル前世を創り上げた。そして、そこに小田切が取り込まれてしまった 」
「そう。小田切君だけでなく、あさとや琥珀君もです」
言い足して、志津子もまた、苦く笑った。誰かがこの話を立ち聞いたとしたら、恩田佳織でなくとも、休暇を取るように薦めるだろう。志津子にしても、これが精神科医として実績を積んだ、自身の発想とは思えない。
「……それもまた、私個人のバーチャルな妄想なのかもしれませんわ。人の脳の働きは、未知な部分が多いですから、あくまで、可能性のひとつとして想像してみたんです。言いましたよね、私自身がクシュリナになった夢を見たと」
「ええ」
わずかに眉をあげて、風間が頷く。
「あの時の感じ……あれは、私自身がそれと感じた、というよりは…… まるで、他人の思考に私自身が同調したような、そんな不思議な感覚だったんです。その時に思いました。誰かが……思念を、私や、あさとや、そして永瀬君に送っているんじゃないかって」
「……門倉雅が、 ですか」
風間が静かにその後を継いだ。
「ええ」
コーヒーの香りが、ゆるやかに立ち上る。
「……だから、その思念が……永瀬君の夢に現れるというのなら、彼の見た夢の記憶を探ってみればどうかと思ったんです」
「なるほどね」
頷きながらも、風間の目は冷めていた。次の言葉を口にするのを逡巡しているようにも見える。
今日、話の合間合間に彼がそんな態度を見せることを、志津子は最初から気付いていた。 が、気付かないふりで続ける。
「人が通常記憶している夢とは、覚醒前のレム睡眠時に見るものだと言われています。でも本当は、もっと深い眠り いわゆるノンレム睡眠時でも、夢自体は見ているはずなんです。深い睡眠時にいきなり覚醒させれば、ある程度夢の記憶が残ると言いますからね」
眠り続ける小田切直人や真行琥珀、そしてあさとも だから、きっと、長い夢を見続けているはずなのだ。
「ひょっとしたら、永瀬君が認識している以上のことを、夢の記憶は教えてくれるかもしれない。その部分を催眠療法で探って見ようと思うんですよ」
そこまで言って、志津子は立ちあがり、窓の傍に立った。
車のエンジンの音がする。玄関前に停車した見慣れないボックスカー。永瀬が来たのかもしれない。
「実は、今から永瀬君が来るんです。いきなりで申し訳ないですけど、風間さん、退行催眠の間、お付き合いしていただけますか」
「えっ」
ようやく、招待された理由を知った風間は、心底驚いた風に顔を上げた。
「今からですか」
「今からです」
「いや……、しかし、それは」
迷うように逸らされた風間の目は、多分、断るための最もらしい理由を探している。いや、そもそも最初から彼は、今日、この件から正式に手を引くと そう告げに現れたのだ。
「騙し打ちみたいでごめんなさい。でも事前に相談したら来てはくださらなかったでしょう?」
「…………」
答えない風間は、わずかに眼だけをすがめる。
僕はもう降りる、無駄だった あの電話以来、風間の執念は急速に冷め、連絡さえ途切れたままだった。
風間の気持は判る。志津子でさえ賀沢が東京を去ったいきさつを聞いた時は、全身に血がたぎるような怒りを覚えた。もうこれ以上関わりたくない、知りたくない。それは志津子も同じである。
が 当の小田切は逃げなかった。結局は東京に戻り、あさとや門倉雅と関わり続けていた。
志津子は思う。この壁の向こうに何かがあると、小田切はどこかで 心のどこかで信じていたのではないだろうか。待っていたのではないだろうか。それが何なのかと問われれば、具体的には何一つ言葉にできないのだが。
「風間さんがこれ以上関わりたくない気持ちは、よく判ります。でもあなたが乗せた船じゃないですか」
黙る風間に、畳みかけるように志津子は続けた。
「私は、娘を……いえ、琥珀君と小田切君を目覚めさせてあげたい。彼らが目覚めるきっかけを、どうしても探しだしてみたいんです」
「きっかけ……」
翳ってしまった男の横顔が小さく呟く。
「鍵です。どこかに鍵があるはずなんです。それはきっと、雅ちゃんの心のどこかにしまってある。それが判れば 雅ちゃんを目覚めさせることができたら きっと、あさとも、琥珀君も、小田切君も、つながれた闇から解き放たれる。少なくとも、覚醒のきっかけにはなるはずなんです」
「門倉雅の、心の中ですか」
風間は、どこか皮肉な口調で呟いた。
「言いかえれば、彼女が作った仮想現実の中にという意味ですね。……先生のお考え全てを否定するわけじゃないですが、僕は、それは違うと思います」
彼には珍しく、きっぱりと断言するようないい方だった。志津子は少し驚いて、男の顔を見返している。
「それは門倉雅を癒す世界であって、小田切の心とは関係ない。奴が心を閉ざした原因とは、無関係ですよ」
「…………」
どうして、そう 言い切れるのだろうか。
「原因って、じゃあなんですか」
心の警戒を解いて初めて、志津子は風間への不信を覚えていた。
「それが何だか、お判りにならないからこそ、風間さんは雅ちゃんと彼の繋がりをお調べになっていたのではないんですか」
「…………」
風間の横顔は動かない。
「賀沢修二との諍いが原因なら、小田切君は警察になる前にはもう心を閉ざしていたわけですよね。それでも彼は警察官を目指し、そして門倉雅ちゃんの事件を調べ出したんでしょう?」
「いや……だから、それと門倉雅の夢の話は」
「夢の世界で得た心の修復は、必ず現実世界にも影響してくるはずなんです。世界に同調している小田切君が無関係のままでいられるとは思えない。意味がないなんて、今の段階で言い切ることはできないでしょう」
「先生は、判っておられないんです」
知りあって初めて、風間の声に苛立ちが滲んだ。「判っておられない……だから、そんな夢みたいなことが言えるんだ」
「風間さんは、判られたんですか」
自分でそう口にしながら、志津子の脳裏にはっと閃くものがあった。
「最初には判らなかった、でも今は判っておられる。私に言えない何かを、風間さんは今ご存知なんですね」
「…………」
多分、そうだ。
賀沢修二の身辺を洗う過程で、風間は何かを知ったのだ。 。
激しい動悸が胸を刺した。それはもしかして、私と小田切君の間に起きた過ちのことだろうか。あの夜 小田切の妻が殺された夜。……
「確かに、そうです」
志津子にとっては、死刑判決を待つにも似た沈黙の後、風間は苦々しく肯定した。
「賀沢の行方を追っている過程で、僕は……以前、彼を庇護していた人物を特定することができました」
庇護……?
賀沢修二を庇護していた人物?
「小田切も、当然そこに行きついたでしょう。おそらく、三年前、奴が大分に異動になる前後です。……でも、それは門倉雅や過去の事件とは全く関係ない、全くお門違いの人物でした」
誰だろう……。
その人物が、小田切の心を壊してしまったと そういうことだろうか。
「教えてはくださらないんですか」
「…………」
「卑怯だわ。あれだけ互いに、色々なことを暴露しておいて。どうしてそれだけを隠そうとするんですか」
志津子は、やや感情的になっている自分を感じた。が、風間の沈んだ表情は動かなかった。
事件とは、まるで、関係のない話だったんです。
風間はそう繰り返した。
「本当に申し訳ないと思っていますが、それだけは僕の口から打ち明けることはできない。故人の、尊厳に関わるからです」
苦しい、胸の懊悩を絞り出すような口調だった。
「…………」
故人 それは、静那さんのことだろう。
しばらく互いの心を探り合うような沈黙が続いた。
先に折れたのは志津子だった。根負けしたというより、自身が年上で、精神的に上の立場だという自負から、そうした。
「全て話してくれとは言いません。警察の方ですから、より強い守秘義務があるのも理解しています」
「…………」
「それでも私は、自分の考えを改めるつもりはありません。雅ちゃんの夢の基礎は、必ずこの現世にあるんです。小田切君と繋がっているんです。確かに無意味かもしれないし、何の役にもたたないかもしれない。でも、それでも」
知らず口調が激しくなる。はっと、涙が零れる予感を覚え、志津子はあえて顔をあげたまま、視線だけを逸らしていた。
「それでも、……諦めたく、ないんです。何もしないで諦めるなんて、できません」
いや、違う。
初めて感情を吐露する不安定な高揚を味わいながら、志津子は一点、冷めた目で自分を見つめている自分を感じていた。
私は……ただ、知りたいのだ。娘が今どうしているのか。どんな世界に生きているのか、わずかでも、その片鱗でも、……知りたくて、たまらない……。
もしかすると私は、ただの母親として、精神科医の立場を利用しようとしているのではないか?
それでも瞬くような迷いの後、志津子は冷静さを取り戻していた。
「風間さんに、何かを求めているわけじゃないんです」
見あげた風間は、不思議な表情で押し黙っていた。
さきほどの沈黙と打って変わって、ひどく居心地の悪そうな、ばつのわるそうな眼をしている。男の表情の変化を不思議に思いながらも、志津子は続けた。
「若い大学生を自宅に呼んで、催眠術をかけるなんて、まかり間違えばどんなことになるか判りません。警察関係者の方に同席してもらいたいんです」
「………」
「お願したいのはそれだけです。決して迷惑はかけません。風間さんだって、私を犯罪者にしたくはないでしょう」
そこまで言うと、もう脅迫である。
風間は、さすがに困惑した態で顔を上げたが、わずかな間の後、 諦めを浮かべた目で頷いた。
「わかりました」
「本当ですか」
そのあっけなさに、逆に志津子が戸惑っている。
風間は、腹をくくったような眼で再度頷き、残ったコーヒーを全て飲みほした。
「すみませんでした」
「え?」
「いや、僕は、少し勘違いをしていたのかもしれないから」
わずかに咳払いをする。静かな目色には、彼らしい落ち着きが戻っていた。
勘違い……?
眉を寄せた志津子に、風間はもう一度咳をしてから、少し気まずそうな微笑を返した。
「先生を、烈女か完全無欠のスーパーマンのように思っていたのかな。僕が先生の強さに甘えていたんです。勝手だった。……本当に失礼しました」
「…………いえ」
即座に謝られた意味を悟った志津子は、むしろ自分が動揺しながら、卓上のカップを持ちあげた。
そして思った。もしかすると彼は、志津子の本音の部分を暗黙の裡に悟ったのもしれない。精神科医ではない 母としての、断ち切りがたい未練と執念。それが判ったから、……ここに残ると言ってくれたのかもしれない。
そう考えた途端、なんとも言えない面映ゆさと居心地の悪さを同時に感じ、志津子は男から視線を逸らしていた。今日を機に、自分と風間の立ち位置が微妙に変わって、何故かそれが、この先も修復できないだろうという、不思議な不安も感じている。
玄関のチャイムが鳴ったのはその時だった。
|
|