|
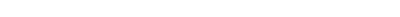
3
「一体何をやっていたんだ、貴様らは!」
久々に訪れた緋薔薇オルドの空気は、触れれば斬れそうなほど、張り詰めていた。扉の隙間からは、何人かのバートル隊士の紫紺の制服が窺える。
アシュラルの自室の前で 元々母が使っていた応接間の前で 足を踏み入れようとしたあさとは、躊躇して立ち止まっていた。
空気を振るわせるほど激しい怒声はアシュラルのものである。どうやら、ひどく機嫌が悪いらしい。
「面倒なことになりましたな、どうします」
ジュールの声がする。あさとは何故かほっとしていた。
ジュールとは、あの政変以来言葉を交わしていない。彼は誰よりも熱心なアシュラルの信奉者で、決して自分の味方ではないと知っているし、ユーリを死に追いやったことも許せない。
が……。
地下でダンロビンに襲われた時、自分を護ってくれた短剣は、今も大切に所有している。
その意味で、確かにあさとはあの長髪美髯の男を信頼していたし、今も、声を聞くだけで、心は自然に落ち着いていた。
アシュラルの姿が垣間見える。彼は椅子に座し、苛立たしげに唇に指を当てていた。そして言った。
「仕方がない、ダンロビンはどうした」
「先日、地下牢でご病死なされました」
アシュラルは、眉を無感動に上げただけだった。
ダンロビンが、死んだ。
あさとは、さすがに驚いて息を詰めていた。あのダンロビンが 死んでしまった。
病死。ではアシュラルは、彼を言葉どおり八つ裂きにしなかったのだ。
ダンロビンがダーラにしたことは絶対に許せないし、あさと自身が八つ裂きにしても飽き足らないとさえ思っている。が、何故かその刹那、あさとはわずかにほっとしていた。
ヴェルツ公爵はどうなったんだろう。エレオノラは。……
そういった表に出てこないことを含め、一体、今、この国がどういう形で動いているのか、あさとにはまるで分からない。
「法王様、奥方様がお出ででございますが」
扉の前で、なかなか言葉を掛けられなかったノエルが、ようやくそう切り出した。
「ご帰還のご挨拶にとのことでございます」
「 あら、お姉様が?」
部屋の中から華やかな声がした。
サランナが、来ている……。
あさとは嫌な気持ちになった。もともと気が乗らないまま、アグリやノエルに急かされるように訪れた夫の部屋だった。「これが、宮廷のしきたりですから」優しい目鼻立ちが、少しだけラッセルに似た青年は、あさとにそう繰り返した。
「……入れ」
アシュラルの不機嫌そうな声がした。あさとはうつむいたまま、部屋の中に足を踏み入れた。
母の専用間だった部屋 子供の頃、拝謁のために何度か訪れた記憶がある。
「奥州攻めが、順調に進んでいるとお聞きしております」
サランナやジュール、そしてその場にいるバートル隊士と法王騎士の見守る中、あさとは作法通りにアシュラルの前に立ち、用意された言葉を読み上げた。
「……ご戦勝のほど、お祝い申し上げます」
言葉を切り、ゆっくりと、嫌なものでも見るように顔を上げる。
母の肘掛椅子、女皇の座るべき座に、轟然と肘をかけて座っている男を見る。
少し日に焼けた肌に、伸びた黒髪が零れている。鋭い瞳、固く引き結ばれた唇。
琥珀……。
あんな夢を見たからだ。
「………」
悔しくなって顔を背ける。
私は馬鹿だ。この男の顔が琥珀に見えるなんて、本当にどうかしている。
彼の背後には、ジュールが苦虫を噛み潰したような顔で控えている。彼もまた日に焼けて、もともと浅黒い肌が、いっそう黒くなっていた。その隣で、どこか楽しげに微笑しているのはサランナだ。
「何をしに来た」
アシュラルはそれだけ言い、眉宇をしかめて顔を背けた。
眼をあわせようとさえしない。その反応に驚いたあさとが呆然と立っていると、
「型どおりの挨拶なら、時間の無駄だ、さっさとうせろ!」
冷酷な、そして吐き棄てるような口調だった。
ひどい。
屈辱で、一瞬頬が熱くなった。 こっちだって、好きで来たわけじゃないのに。
あさとはすっくと背筋を伸ばした。一秒でも、こんな所には居たくない。
「奥方さま、ご祝辞なら、夜の戦勝会でお願いいたします」
気遣うように眉をひそめ、抑揚のない声で言い添えたのはジュールだった。
夜の?
あさとは、訝しくジュールを見返す。
戦勝会。今夜、そのような催しがあるなど聞いてはいない。
「 お前、知らないのか」
アシュラルの声に剣が滲んだ。
「あら、お姉様、私ちゃんとお伝えしたでしょう」
涼しい顔で、サランナが笑う。
「色々ご準備があるのではなくて? 女皇陛下様」
サランナ……。
もう、あさとにも、サランナの敵意ははっきりとわかっていた。
あの政変の夜から、妹の態度は明らかに変わった。理由はわからない、あんなに優しかった いや、少なくとも表向きは優しかった妹が、何故 とも思う。
おそらくアシュラルの「妻」という立場を得た自分が、許せないのだろう。それが例え愛のない行為だとしても、自分が愛している男が他の女を抱く運命にある 確かに、平静でいられる方がどうかしている。
だから、あさとはサランナを憎むことができなかった。彼女の露骨な嫌がらせにも口を挟むことなく耐え続けた。なのに 。
サランナの敵意は日に日に増していくばかりだ。
「クシュリナ」
苦々しく嘆息して、アシュラルは立ちあがった。
「お前、一体、今日まで何をしていたんだ」
何をって。
鋭い目が、高みから突きつけられる。
「まさか、ひがな一日、可哀想なお父様を想って、泣いていたんじゃないだろうな」
「………」
うつむいて唇を噛んだ。悔しくて言葉が何も出てこない。
「お前は馬鹿か、そんなことをして、ハシェミ公がこれ以上よくなるわけでもあるまいし、何かの役に立つわけでもない」
「放っておいて」
さすがに、かっとした。父を侮辱されることだけは、我慢ならない。
「私や父のことで、あなたに、いちいち指図は受けません」
「なんだと?」
靴の音が荒々しく近づく。あさとは身体をすくめた。殴られる、そんな気がした。何があったか知らないが、今日のアシュラルの機嫌は相当に悪い。
「お前は何のためにここにいるんだ」
けれど、アシュラルはあさとの目の前で足を止めた。顔を上げられないあさとの目には、彼の広い肩先ときれいな鎖骨だけが見えていた。
「めそめそするだけで、何の役にもたたん女など、俺には必要ない。もともと俺は終末の書など、信じてはいない」
「………」
だったら、なんで。
「お前と、お前の産んだ子供には政治的な価値がある、そう思ってお前を俺の妻にした。だがな、美しいだけで何もできない女には用はない」
恐ろしいほど、冷淡な声だった。
あさとは彼の顔を見上げた。
冷たい眼、傲慢な眼。嫌い……大嫌い。
「それが判ったら、とっとと、出て行け!」
あさとはたまらず、きびすを返した。
「女皇陛下」
ノエルが慌てて追ってくる。
ドレスの裾が足に絡むのにも構わず、小走りに歩きながら、 途中、涙が出そうになった。
大嫌い。
あんな奴、大嫌い……。
4
法王軍が、奥州の約半分を制圧したとあさとが聞いたのは、戦勝会の直前になってからだった。
なによ、だったらなんで、あんなに機嫌が悪かったのよ。
まだ悔しさを引きずったまま、支度を済ませたあさとは、大広間に設けられた自席についた。
眼も覚めるほど美しい紫紺の法衣に身を包んだアシュラルは、その下に黒の騎士服を着るという奇抜さで現れ、場内の注目を一身に集めていた。
漆黒の髪色、焔を宿した野性の瞳、それでも優雅に 気高ささえ漂う立ち姿は、彼が微笑し、何かを発言するだけで、居並ぶ全ての人々の心を掴み、虜にしてしまっている。
あさとはようやく、今夜の戦勝会が、単に奥州での戦況を祝したものではなく、皇都の新たな主を明確にするためのものだと理解した。
法王、コンスタンティノ・アシュラルが、皇都の新しい主だと、 誰もが無言のうちに了承するしかない空気が、最早できあがっているようだった。
フォード公の……危惧されたとおりに、なったということなのだろうか。
あさとは、かつて、自分を訪ねてくれた薫州の松園公爵が、法王家が政治に干渉してくる危険と、そしてカタリナ修道院の脅威について、熱心に語ってくれたことを思い出していた。
あの時は、まさかと思った。が、結局全ては、公爵の杞憂どおりになってしまっている。
むろん、この大広間に、フォード公の逆立つ灰色の髪は見えない。
それどころか、今宵招かれた諸侯の多くは、あさとの全く知らない顔だ。
理由は漠然と察しがついた。イヌルダ最大勢力を誇ったヴェルツ公爵の追放により、彼の者の傘下にいた領主はのきなみ消え、代わって、アシュラルの賛同者らがその職についたのだ。 。
「クシュリナ様」
一人の諸侯が、青百合サロンに訪れた。
甲州春日に領地を持つサディル男爵。以前青百合サロンの取り巻きだったナタルの父親である。
サロンには、今、ノエルやアグリら、青百合オルドの侍従たちしかいない。
サランナの周りに花輪のように広がる婦人たちは、あさとの傍には、型通りの挨拶にしか訪れなかった。
「陛下の即位式の折には、ご挨拶が叶わず、失礼いたしました」
実直な男は、苦渋を顔に浮かべて生真面目に一礼した。
彼の妻と娘が、サランナの傍にいるのだから、彼が抱く気まずさも理解できる。
が、甲州の領主の殆どが、一斉にサランナサイドに寝返ったのだから、サディル男爵の立場もおのずと定まってくるのだろう。
「アデラ様ご逝去の折には、陛下に御助力することも叶わず……まことに、申し訳なく思っております」
「かまわないわ。私のことは、お気になさらないで」
サディルの領地、春日は甲州にある。ハシェミ派の筆頭だったサディル男爵は、ハシェミとクシュリナが捕縛された後、自らの領土に振りかかる火の粉を払うので精一杯だったろう。
むしろ、サディル公爵の真面目さに同情を覚え、あさとは優しい声を掛けている。
「……まるで、金波宮ではない、別の場所のようですな」
立ち上がったあさとを見下ろし、サディル男爵は囁くように呟いた。
男の視線は、大広間の中二階に向けられている。
そこには、黒衣に竜を刻んだ騎士たちが、ずらり、と雁首を並べていた。
黒竜軍。
今宵発表された、近衛隊の新しい名称である。
今まで、プレミア、カナリー、カーディナル、フラウ、バートルに別れていたパシクは統合され、隊服は黒碧色に統一された。紋章には黒竜が刻まれ、名称はドゴン。そのものものしい姿は、今も大広間の二階に陣取り、広間の客を見下ろしている。
黒竜軍の司令には、当然のごとくジュールが就いた。彼はまたアシュラルの側近として、法王軍をも指揮している。
「陛下は、即位後もフラウオルドに留まることを希望されたとお聞きしました」
「ええ、慣れたオルドですから」
むろん、それらの処遇は全てアシュラルとサランナが決めたことだ。が、自分の立場では、そう答えるしかないことを、あさとはよく知っている。
「……そうでございますか」
サディルは、寂しげに微笑すると、視線を広間の中央のほうに向けた。
「私はこたび、貴族院を辞去するつもりでおります。……ハシェミ公が囚われになった後、甲州はコシラに荒らされ、いまだ戦の只中にございます。法王様の御助力により、春日の地だけは無事に取り戻しましたが」
「サディル様」
「ご存知ですか? こたび新しく貴族院の長に就かれたのは、三笠ジョーニアス卿……法王庁の枢機卿だった男です」
サディルの言いたいことを察し、あさとは黙って視線を下げた。
アシュラルの手を取ってしまった時から、自分はすでに彼側の人間なのだ。が このまま、ただ、人形のように与えられた椅子に座っていていいのだろうか。
「ジョーニアス卿だけではございません。武官長、文官長も、みな、カタリナ修道院出の者に替えられたと言う話です。陛下もご存知でございましょうが」
そこまで、あさとは知らなかった。
が、金波宮に暮らす者として、すでに皇都が法王庁に統制されている空気は察している。
「……皇都のありようは変わってしまった。もう、私のような古い人間は必要ないのやもしれませんな」
サディルが去った後、あさとは黙って、広間の踊りの輪を見つめていた。
皇都を襲った政変は、あさとの予想を遥かに超えた大規模なクーデター……。元の世界でいえば、明治維新かその規模の政変に等しいものなのかもしれない。
それまで、奥州公ヴェルツと甲州公ハシェミが、それぞれ後ろ盾となることでかろうじて保たれていた皇室中心の政治が、両頭の失脚により、完全に法王家に持っていかれてしまったのだ。
中央の輪の中心では、サランナが花のほころぶような微笑を湛え、来賓の応対に務めている。
あさとは、アグリが用意した衣装で出かけたが、どう贔屓目にみても、サランナの方がより美しく、より豪奢なドレスを身にまとっていた。
主賓はアシュラルであり、ホステスはサランナである。
今夜はそれを イヌルダの社交界にアピールするための催しといってもよかった。
主役の二人は、寄り添うようにして広間の中央に立っている。
一度退出したアシュラルは、今は深紅のクロークを羽織り、薄絹のスカーフと金刺繍の細身の上着を身に着けている。肩までの波打つ黒髪が見事に艶めく美男ぶりは、居並ぶ婦人たちの心をますます虜にしてしまっている。
「本当に、あのアシュラル様が戻ってきたのでございますねぇ」
「また一段と凛々しくおなりになって。あれほどの男ぶり、他に見たことがございませんわ」
囁きと溜息。そして、彼の隣に当然のように侍る、サランナの姿。
あさとは溜息をつき、憂鬱な顔を上げた。
こんな光景にも、慣れて行かなければならないのだろうか。いや、慣れる前に、自分はこの城から追い出されてしまうのかもしれないが。
あさとは気持ちを切り替えて、立ち上がった。 別に、黙って座っていろと言われたわけではない。
昼間、アシュラルにあんな厭味を言われたせいかもしれないが、咎められるものなら、咎めてみろという開き直りにも似た気持もある。
戦勝会の直前、アグリに出席者リストを見せられて、初めて知ったことがある。今夜は、青州公が皇都入りしているのだ。
新たに青州公となった鷹宮ダーシー。
彼の口から、ユーリの死の真相を、あさとはどうあっても聞く気でいた。
|
|