|
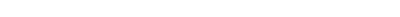
1
琥珀……。
「……クシュリナ様」
呼び声で目を覚ましたあさとは、一瞬傍に、夢で見たばかりの男がいてくれるような錯覚を感じた。
うっすらと輪郭を浮き上がらせる天蓋付きの寝台。朝日を浴びて、ひそかに揺れるレースの帳。
再度、女の囁き声がした。クシュリナ様……私の、名前。
夢、だった……。
「起きたわ」
帳の向こうで膝をつく女官たちに、あさとは短く告げて身体を起こした。
涙がまなじりにたまっていた。
零れる前にそれを払い、あさとは小さく深呼吸した。
哀しいほどリアルな夢だった。本当に琥珀がいて、抱き合って、触れ合っていたような そんな温みさえ残る夢だった。
夜着からのぞく自分の足首に、あさとは指先でそっと触れた。
この足は、あの夜のものではないけれど、ここに……琥珀が、誰よりも気高くて美しい人が……唇をあててくれた……。
「お起きになっておられるなら、出てきてくださいませ、女皇陛下」
ざらざらした耳障りな声が、幸福の記憶を遮った。
ああ、そうか。
あさとは自分の顔が曇るのを感じながら、寝台の下に足を降ろした。
イヌルダ一の権勢を誇っていた五公の一人、薬師寺ヴェルツ公爵が捕縛されてから約一月がたっていた。
以来、宮中の政治のあり方は一変し、細かい決め事に至るまで、その一切が新法王 アシュラルの統治下におかれるようになっていた。
彼は旧勢力に加担した者たちを容赦なく断罪し、捕縛し、追放した。それは侍従や女官のような、身分さえ持たぬ者の身にも及ぶという徹底ぶりだった。
その結果、わずか一月の間で、政変以前に宮中にいた殆どの文官、武官、女官、侍従が、入れ替わった。むろん、あさとが暮らす青百合オルドも例外ではない。
もともとヴェルツの手によって、大きく変えられていたオルド内の人事である。それが再び、アシュラルの手によって一新された。昔馴染みの女官も侍従も一晩のうちに姿を消し、翌朝には見知らぬ者が当然のような顔で傍に侍っていた。 何もかも、あさとの知らない間にアシュラルが行ったことだ。
いや、アシュラルと……。
あさとは、うつむき、結婚して以来一度も夫の訪れない大きな寝台を見つめた。
そして、サランナが。
「さぁ、急ぎ、お着替えを。いつもよりご起床の時間が遅れております」
事務的な口調でそそくさと朝の支度をはじめる女は、アグリと言う。
あさとは、五十絡みのその女のことをよく知っていた。元々は、カナリーオルドのサランナ付き女官である。舞踏会の折など、いつもサランナの傍についていたのはこの女だ。
今は そのアグリが、青百合第一女官なのだった。
アグリだけではない、その他、クシュリナに従う女官、侍女は、全て、元カナリーオルドの面々である。以前のカナリーとフラウの敵対関係を知るものには、にわかに信じがたい変化である。
が、女皇の立場など一切無視した改革は、それだけではなかった。
即位した女皇のオルドは、代々緋薔薇オルドと決まっていたが、あさとはそのまま、青百合オルドに留め置かれた。
代わって、アシュラル一派が緋薔薇オルドを占拠したのである。
三オルドの中で、唯一本殿と繋がっている居館である。政治がやりやすい、それだけ理由で、皇室の伝統はあっけなく覆されたのである。
むろん、緋薔薇オルドにはサランナが再々泊まりに行っている。留守がちなアシュラルの指示を受けてかどうかは知らないが、宮中の奥向きの人事は全て実質的な法王夫人 サランナが取り仕切っているようだった。
琥珀……。
夢で会えた。現実には決して会うことの出来ない人と 。それだけで、いい。それだけで嬉しい。
この、先の見えない闇の世界で、もう一度頑張ろうという気になれるから。
私、あきらめないよ。
琥珀に巡り逢うまでは、何があってもあきらめない。
「アシュラル様、夕べ遅くに、ご帰還されたとのことでございます」
髪を整えられるあさとの背後で、アグリが事務的な口調で報告してくれた。
「早々にご帰還のご挨拶に行かれなさいませ。法王様におかれましては、数日の内には、また他方へご出陣されるとのことですから」
「戦は……奥州と、甲州はどうなっているのかしら」
あさとは気になっていたことを問ってみた。
アシュラル率いる法王軍は、ヴェルツ捕縛後、当然のごとく奥州 薬師寺家の領地になだれこんだ。潦州の久世家、青州の鷹宮家がその同盟となり、奥州と、そしてヴェルツによって奪われた甲州で、連日、凄まじい攻防戦を繰り広げているという。
なにしろ、イヌルダ一の勢力と軍事力を誇っていた薬師寺家である。当主ヴェルツが捕われ、女皇殺害の罪により薬師寺家の爵位が剥奪された後であっても、依然、奥州の主である薬師寺家の力は変わらない。
確かに皇都からヴェルツ勢力は一掃された。が、イヌルダにあって、深く根付いた薬師寺一族の勢力はあまりに強大であった。その一族、庇護下にあった小領主らが、一斉に法王軍に対して叛旗を翻したのである。
杞憂は、もう一つある。政変後における薫州松園家の立場である。
あさとが皇都に戻った時、松園家の者たちはすでに金波宮から消えていた。妻子 松園ルシエが暮らしていた城下の宮殿からも、侍従を含め、一人残らず姿が見えなくなっていた。
最後まで、それが嘘か、誤りだと信じたいあさとだったが、松園フォードが、ヴェルツと手を組み、法王家と皇家の婚姻を阻んだのは、もはや間違いのない事実のようであった。
が、その後において、フォード公はヴェルツと決裂したらしい。あさとが推測するに、その理由は かりそめにしろ、ヴェルツがアシュラルと手を組もうとしたことが原因だろうと思われた。
皇都を引きはらい、自領薫州にたてこもるフォード公は、今は沈黙を護っているが、今後アシュラルと対決するのは必然である。
あさとは何度もフォードあての手紙を書いたが、それが届いているかどうかさえ、今のあさとには知る術がないのだった。
「法王が戻ってきたということは、奥州での戦が、一息ついたということかしら」
誰も答えないので、あさとは再度、アグリに答えを求めて訊いた。
「アグリ、奥州の戦のことだけど」
「戦のことは、私は、何も存じ上げません」
それきり、次の質問を拒むかのように、アグリは女官らに何事か指示しながら、別の部屋に消えてしまう。あさとは唖然としつつ、周囲を振り返った。
「みんな……何か、聞いていない?」
朝の支度のために、部屋には沢山の女官がいたが、答える者は誰もいなかった。
これ以上何かを尋ねる気力をなくし、あさとは嘆息して鏡に向き直った。どうせ皆、サランナに言い含められているのだろう。そういう意味では、あさとは常にサランナに監視されているのだし、情報すら、妹の許可を得たものしか届かないようになっているのだ。
あの男、帰ってきてたんだ。
無感動にあさとは思った。
政変後、すぐに皇都から出立したアシュラルとは、金波宮で行われた出陣式で別れて以来、あさとは一度も会っていない。
ふと、虚しくなって、あさとは苦笑を漏らしていた。
私の立場って、……昔と全然変わってないみたい。
意に沿わぬ婚約者の帰還を、帰ってこなければいいと願い それでも待つしかなかった少女時代。結局、その男と結婚して、今、また同じ思いを味わっている。
が、全てが昔のままではない。
……私の周りは……何もかもが、変わってしまった。……。
辛い思い出がこみあげ、あさとは目を伏せていた。
かつて「クシュリナ」を、愛情と信頼を持って護り続けてきてくれた三人 ハシェミ、ダーラ、ラッセル。その三人は、もういない。
あさとは孤独だった。本当に 今、孤立無援の一人きりだった。
「……政務の前に、お父様の所へ行って来るわ」
身支度を整えたあさとは、そう言って立ち上がった。咎めるようなアグリの視線が背中に注がれる。
「お一人の外出はお許しできませんよ」
「わかってる、……ノエルを連れて行くわ」
それだけ言って、逃げるように部屋を後にし、隣室へと急ぎ足で向かった。
ノエルとは、半月前に青百合第一騎士としてオルドにやってきた青年騎士である。
もともと法王庁の騎士だったというから、アシュラルかサランナが手を回したのだろう。すらりとした痩身で、髪は黒く、憂いを帯びた瞳をしている。
少し……ラッセルと雰囲気が似ている。
が、むろん彼はラッセルではないし、アシュラルの息がかかった男だと思うと、実際少しも信用できない。
「陛下、馬車の御用意が」
差し出されたノエルの手を、あさとは知らないふりでやりすごした。
「お父様のオルドに行くだけだから、私一人でも大丈夫なのよ」
「いえ、私は姫様の第一騎士ですから」
優しいが、どこか茫洋としたところのあるノエルは、自分がうとまれていると知っても、少しも動じないふてぶてしさがある。今も、平然とあさとの隣に座し、にっこりと笑顔を向けてくる。
決して悪い男ではないのだが その無神経な鈍さというか、掴みどころのない雰囲気が、どことなく、あさとには苦手だった。
「ウテナは、元気でいるのかしら」
「いずれ外出の御許可も出ると思いますので」
「私、ウテナのことを聞いているのよ」
「さぁ、馬のことでしたら、私には判りませんが……」
溜息をついて、あさとは窓の外に目を向けた。
2
ハシェミの身柄は、以前鷹宮家が逗留していた白蘭オルドに移されていた。
公には、病気療養中ということにされている。
が、ごく少数の者しか知りえないことだが、その実、蛇薬を身体から抜くための治療が、人知れず行われているのである。
むろん、サランナの口添えがあったからだろうが 憐れな父の処遇についてだけは、あさとはアシュラルに感謝していた。
(ダンロビン様がどのようなことを申されたかは存じ上げませぬが、毒を抜く薬というものは、現在シュミラクールには、存在しないのでございます)
父専属の御殿医は、申し訳なさそうにあさとに説明してくれた。
(彼の薬は、邪神、マリスが作り出したものと言われております。その数は百種を超え、どのように調合され、どのような毒を持つかは、マリス教秘伝中の秘伝と言われており……、今でも、殆どが解明されてはおりませぬ)
それは、絶望的な宣告であったが、とりあえずハシェミは小康を取り戻し、半ば……廃人のようではあるが、禁断症状は完全に収まったのだと言う。
私の世界で言うと、覚醒剤とか……そういう感じなのかな。蛇薬って。
似たようなものだとしたら、毒消しの薬など、そもそも存在しないだろう。
身体に取りこんだ薬の成分が、自然に外に出るのを待ち、蝕まれた身体と心が、ゆっくりと回復するのを待つほかない。
あさとは、父の寝室に入り、その傍らに腰を下ろした。
「お父様……私よ」
金波宮で、あさとが法王の許可なく自由に動き回れるのは、フラウオルドと、この白蘭オルド間しかない。必ずノエルを従えていかねばならないが、それでも窮屈な青百合オルドにいるよりはずっとましで、あさとは日課のように、連日父のもとを訪ねている。
「今日、あの男が帰ってきたのですって。……お父様のお気に入りだったコンスタンティノ家の御子息よ? 憶えていて?」
寝台の上の父は、答えない。
目を虚ろに開いたまま、時折、しわがれた唇をわずかに動かす。溢れた涎を、あさとは拭った。
お父様……。
かつての、美しい父の姿を知っているあさとには、それは無残としか言いようのない姿だった。言葉も、記憶も、意思さえも失った父は、今は寝台から起き上がることもできず、ひがな虚ろな目で天井を見上げている。
「姫様、おいででございましたか」
背後の扉が開き、見慣れた男が現れた。 保科ガイ。
父の侍従で乳兄弟、あの政変の折、最後まであさとを護ろうとした義侠の騎士だ。
ハシェミが倒れて後、ガイは騎士を引退し、今は一侍従として、献身的にハシェミの傍に仕えている。
後ろに束ねられた髪は、ますます白く、細くなり、この一月のガイの心労が窺えるようだった。
「姫様……いや、陛下」
薬を持ってきたらしいガイは、あさとを見下ろし、どこか言いにくそうな表情をみせた。
「ハシェミ様のお傍に陛下がいてくださると、私もどれだけ嬉しいかわかりません。が……、陛下には、お立場があるのですから」
「…………」
「公務にお戻りくださいませ。そのほうが、ハシェミ様も、お喜びになることでしょう」
わかっている。 が、実際のところ、この金波宮で、あさとには他にすることが何もないのだった。
諸侯が挨拶にくれば、応対に出る。儀式があれば、表に立つ。いってみればそれだけだ。
宮内のことは、全てサランナが取りしきっている。
情報も指示も、全てが彼女を通る仕組みになっており、あさとには、口をはさむ余地さえない。
それどころか、宮中の誰もが、いずれアシュラルが「クシュリナ」と離婚してサランナと結婚するのだろうと、内心確信し、 それを前提に二人の姫に接しているようなのだった。
皇族の離婚の許可は法王だけが握っている。言いかえれば、アシュラルは自由にあさとと離婚できる。
アシュラルは今、彼の私設軍とも言える法王軍、そしてシュミラクール各国に分散する教会軍の全権、さらに近衛隊を完全に掌握している。その力を用い、ヴェルツの領地、奥州を略取しようとしている。 イヌルダ最大の広さを誇る奥州を手中におさめれば、彼にとって、「女皇の夫」という地位は、ほんの飾りにしかすぎなくなるだろう。
きっと、彼にとって一番都合のいい展開は……。
その想像をするだけで、あさとはぞっと身震いしたい気分になる。
彼にとって一番都合のいい展開は、あさとが子供を産み、その子に皇位を譲り渡して退位することなのだろう。そうすればアシュラルは、幼い女皇の後見人として、いや女皇そのものとして、国政を自由に操れる。
多分、サランナはその日を心待ちにして、全ての準備を整えているのだ。
子供を、産むためだけの道具……。
それがあさとの……いや「クシュリナ」の、この世界での役割だった。
余りにも虚しすぎる、役割だった。
ラッセル。
帰途の車中、あさとはそっと目を閉じた。
むろん、ラッセルは全てを承知していたに違いない。今なら彼の行動、言葉……その全ての意味が理解できる。彼もまた、父と同じで、アシュラルが何をしても庇い続けていたからだ。その理由は 。
何が何でも、アシュラルと「クシュリナ」を結婚させようと思っていたからなのだろうか。
「……そうなの? ラッセル…」
落ちていくような底なしの虚しさにかられ、あさとは思わず呟いていた。
これがあなたが、私にしてほしかったことなの? これが高貴なる者の義務だとでも言うの?
閉じた目に涙が滲んだ。
あなたさえ、生きていてくれたなら。
傍で支えてくれたなら。
きっと、どんなさだめも乗り越えて行けるのに。
|
|