|
第四章 闇を照らす光
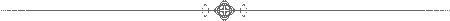
夜の果て、遠い彼方でかすかな汽笛の音がする。
きれいだね、また来ようね。
そう言いかけてはやめ、やめてはまた言いかける。
月と星が、夜の海に反射している。吐く息が、闇に白く滲んでは溶ける。
そろそろ戻らなきゃ、 みんなが心配してるし、きっと変に思われる。
あさとはそっと、隣に立つ男の横顔を窺った。
まっすぐな彼の眼は、漆黒の闇を滲ませて、いつもよりひどく不機嫌そうで 何かを憂いているようにも見える。
苦しくなって、あさとは琥珀から眼を逸らした。
車を降りてから、一言も喋ろうとしない琥珀。
判っている。きっと、今、こうして二人きりで 夜の海辺に立っていることに気まずさを感じているのだ。
それでも、この場所から動きたくない。未練にようにあさとは思った。このままでいたい、あと少し、琥珀の横に立っていたい。
「……瀬名」
かすれた声で不意に呼ばれた。
あさとは驚いて顔を上げる。鼓動が、痛いほど高まった。彼に名前を呼ばれると、いつも必要以上に緊張してしまう。
「足、もう大丈夫か」
見下ろす眼差しは、丁度月で逆光になっていた。声は優しい。でも琥珀の表情は判らない。
「え、……あ、うん」
あさとは戸惑いながら曖昧にうなずいた。
十二月 。
忘年会を兼ねた恒例のクリスマス合宿、その二日目の夜だった。
あさとの所属する白鳳堂大学剣道部の部員たちは、千葉にある大学の合宿所に、強化合宿の名目で宿泊していた。
その日、あさとは、午前の稽古で足首を痛めた。転倒した際、倒れ方が悪かったのか、ひどくひねってしまったのだ。傍にいた男子部員がすぐに手当てをしてくれたが、夜になってから痛みがひどくなった。
我慢できないほどの激痛が、丁度、飲み会の最中にやってきた。あさとは一晩たてば治ると言い張ったが、心配したマネージャーが夜間外来の病院を探してくれた。
( 俺が連れて行く)
車を出そうとしたマネージャーに、そう言ってくれたのは琥珀だった。
あさとは少し吃驚した。秋の終わりに初めて彼と唇を合わせてから 二人きりになるのは、それが初めてだったからだ。
正直言えば、あの夜のキスのことなど、まるで忘れているかのような琥珀の態度が苦しかった。態度は普段通りではあるものの、彼が内心、苦悩し、後悔しているのがありありと感じられたから……。
雅の次でもかまわない。これからも傍にいたい 半ば、琥珀の弱みにつけ込むように、そう言って迫ったのはあさとだった。
その夜、琥珀は携帯を切って、二人は一時の熱に溺れた。でも 翌日、あさとは冷静さを取り戻し、おそらく、それは琥珀も同じだった。二人の前には、無邪気に笑う雅がいて、……否応なしに、犯した罪の深さを思い知らされる。
それでも、今夜、二人になることを選んでくれたのは琥珀だった。
この一時が過ぎてしまえば、二度と二人にはなれないかもしれない。だからあさとは、病院からの帰り路、無言で運転している琥珀に、思い切ってこう告げたのだった。
( 少し、海岸を歩いてみようよ)
走行する車のフロントガラス越しに、星を浮かべた夜の海が延々と広がっている。
断られるかな、と思ったが、琥珀は何も言わずに速度を落とすと、車を海岸脇の歩道に付けてくれた。
きれいだね。
また、来ようね。
師走の風は冷たく、少し離れて歩く二人の頬も瞳も凍らせた。
歩く最中、琥珀はずっと黙ったままだった。
あさと一人が、心の中で同じセリフを繰り返し呟いている。今の二人にこの先はない。約束など、決して言葉にできないと判っているから。 。
月光に照らされた琥珀の横顔。風にあおられて揺れる髪。あまりに綺麗で、哀しいくらい綺麗で 見つめているだけで呼吸が苦しい。
「帰ろうか……そろそろ」
うつむいて、あさとは言った。
足のことを気遣ったきり、再び口をつぐんでしまった琥珀と、さすがにこれ以上一緒にいるのが辛かった。
判っている。琥珀はきっと忘れようとしているのだ。あのキスのことも、交わした会話も、呼び合った名前さえも 。
「みんな心配してるだろうし、足も痛くなってきたから」
泣きたい衝動を誤魔化すために、わざと明るく言ってみた。痛いのは……本当は、足なんかじゃない。
「……触っていい?」
「え?」
不意に言われた言葉の意味が判らなかった。それが琥珀の唇から零れた言葉だということも、しばらくは認識できなかった。
琥珀……?
琥珀は静かに砂浜に膝をつくと、湿布をあてたあさとの足首にそっと手を当てた。
冷たい指先、なのに……触れていると不思議なくらい暖かい手のひら。
あさともまた、砂の上に腰をおろし、琥珀が触れやすい体勢を取る。
「痛い?」
「う……ううん」
ドキドキする。
琥珀の指……きれい、長くて、なんだか……。
関節の様子でも見てくれているのだろうか。普通に触られているだけなのに、心臓が どうにかなりそうだ。
「むかついた」
低い呟きが足元から響いた。
「え?」
思わず聴き返した刹那、琥珀の唇が、膝の下あたりにいきなり触れた。
琥珀?
そのまま琥珀は、あさとの足首の少し上に自分の唇を押し当てる。
「や……」
冷たい唇。温かな手。こんなの 初めて。
胸、苦しい。
息が、できない。
あさとはよろめき、後ろに倒れかけた身体を手をついて支えた。
琥珀が、驚いたように顔を上げた。
「ごめん」
珍しく狼狽している。足から手を離して視線を逸らし、不自然なぎこちなさで立ち上がる。
「気持ち悪かったな、……悪い」
しゃがみこんだままのあさとに、手を差し出しながら、琥珀は低く呟いた。
そんなんじゃない、そんなんじゃないけど。
手にすがり、あさとはようやく立ちあがった。膝から、冷えた砂粒がさらさらと零れ落ちる。
まだ心臓が、煩いくらいに鳴っている。繋いだ手のひらから、自分の心音が伝わってしまいそうだ。
琥珀の顔を、見ることが出来ない。
あさとがうつむいていると、頭上でかすかな嘆息が聞えた。
「……悪かった」
寂しそうな声だった。
何か言わないと わかっているのに。
謝ることじゃない そう言いたいのに、言葉だけが出てこない。
「今夜のことだけじゃない。……本当は、ちゃんと、謝らないといけないって思ってた」
あさとは、はっとして顔を上げた。
「琥珀、それは」
「そんな顔、しなくていい」
優しい声。ゆっくりと振りほどかれて、離れていく手。
「ごめんな」
「………」
「全部、俺が悪いんだ……。だから、もう、お前は悩まなくていいよ」
その言葉をどう受けとめればいいのだろう。判っている、友達の恋人、決して恋の見返りを求められない人 だけど。
あさとは再びうつむき、そのまま唇を開くことさえできなかった。
「おい、瀬名」
翌日の午後。
稽古を見学していたあさとは、声をかけられて顔をあげた。
足は、朝になってもまだ痛んだ。試合形式で行われている通し稽古を、道場の隅のベンチに座ってぼんやりと見ていた時だった。
「お前、足、大丈夫だったか」
隣に座り、囁くように声をかけてきたのは、高山という名の男子部員だった。あさとの同期生で、昨日足をひねった時、たまたま近くにいてすぐにアイシングと湿布をしてくれたのはこの男である。
「うん、平気。ありがとね、昨日は」
あさとがそう言うと、高山は周囲を窺うようにして、さらに声を小さくした。
「……病院、真行先輩と行ったんだって?」
「え? ……うん」
昨夜、病院から戻ってみると、男子部員たちは部屋で飲み会の続きをやっていた。高山は相当酔っていたから、あさとが病院へ行ったことさえ知らなかったのだろう。
琥珀は 飲み会では、一切アルコールを口にしない。それどころか、大抵途中で退席する。昨夜、彼が車を出してくれたのはそのためだ。実質、運転者は琥珀しかいなかったのだ きっと、特別な理由は何もない。
「なぁ…」高山は、囁くような声になった。
「真行先輩、俺のことなんか言ってなかった?」
いつも優しげな童顔が、ひどく不安げな色を浮かべている。あさとは眉根を寄せて首を振った。
「? 別に、何も」
「そっかぁ」
高山は口を曲げて、溜息をついた。
「なんかさ、あの人昨日から、やたら俺に厳しいんだよ。さっきもびしびしにしごかれて、もうダメ、俺、泣きそう」
「何かしたの……?」
心外、とでも言うように高山は眉をあげる。
「思い当たることあったら聞きに来ないって。なんか俺、気に障ることでもやったかなぁ」
ぶつぶつ言いながら、高山は立ちあがった。
「お前さ、女子で唯一あの人と口聞けるんだから、俺のこと、上手く言っといてくれよ」
……。
あれ……?
それって、もしかして。
あさとは目で、道場内にいるはずの琥珀の姿を探した。どこへ行ったのか、稽古をしている部員たちの中に、ひと際長身の姿はない。
信じがたい空想で、わずかに頬が紅潮してしまっている。
足に触れた時、囁いた声。
もしかして、あの時、琥珀は……。
意識して二人になろうとしてみると、意外にその機会がつくれないことにあさとは気がついた。
琥珀はなかなか一人にならないし、あさともなかなか一人にはなれない。
合宿所にはいたるところに誰かがいるし、常に人の目があるような気がする。
その日の夜、男子部員が陣取る合宿所の大部屋で、恒例の飲み会が始まった。男子だけの無礼講の馬鹿騒ぎで、女子は自由参加。琥珀はそういう時、騒ぎを嫌って大抵途中で外に出る。
大部屋の前で待っていれば 出てきた琥珀と話すチャンスがあるかもしれない。
あさとは廊下の端で、彼が出てくる機会を待っていた。
夜は更けて、暖房の効かない廊下は身震いがするほど薄寒くなる。
しばらくそのまま待っていたが、何度かドアが開いて、賑やかな喧騒の中、トイレのために出てくるのは、別の部員たちばかりだった。
なにやってんだろ、私。
次第にあさとは、自分がしていることが情けなくなってきた。
帰ろうかな……。
足が、また痛くなればいいのに。
馬鹿なことを考えている。 そしたら、また琥珀と二人になれるかもしれないのに、と。
重い息を吐いて、階段を降りようときびすを返した時だった。
階段の下から見上げている顔がある。微かに寄せられた形良い眉宇。驚いて、少し見開かれた切れ長の眼。
「お前……何やってんだ、こんなとこで」
琥珀?
外から戻ってきたのか、厚手のフードジャケットにマフラーをひっかけ、手には重たそうなビニール袋を下げている。
階段を上がりきって、琥珀はあさとを見下ろした。どこか冷たい眼差しだった。
心臓が、ドキドキしている。 言わなきゃ。あさとは唾を飲み込む。
「戻れよ、こんなところにいると、酔っ払いにからまれるぞ」
「う、うん……」
琥珀が手にしている袋には、沢山の缶ビールが詰められているようだった。
「買い出し?」
「ああ、俺は飲まないから」
「………」
言わなきゃ。
「……とにかく、早く戻れ」
琥珀の顔が背けられる。広くて大きな背中が向けられる。
ダメ、言わないと……思ってるだけじゃ伝わらないことを。
「こ、…琥珀っ」
けげん気に振り返る顔。綺麗な眼差し、薄い唇。
駄目だ……顔を見ると何も言えない。 言えない、けど。
自分でも無意識に、あさとは彼の傍に駆け寄った。考える間もなかった。駆け寄って、驚く顔に、その唇の少し横に、思いきり背伸びをしてキスをした。
「…おま、…」
琥珀は、多分仰天している。あさとはうつむいた。多分、すごくとんでもない真似をした。恥ずかしくて、呼吸さえ止まってしまいそうだ。
その時、階下から突然人の話声がした。
「真行、えらい遅いな、何やってんだあいつ」
「駐車場に車戻ってたよな」
どうしよう、そう思うより先に、琥珀の腕に引かれ、すぐ傍にある室内に引き込まれていた。
使用されていない空部屋だった。がらんとした畳敷きの室内に、窓から漏れる月明かりだけが、仄かに差し込んでいる。
琥珀は素早く扉を閉めると、そのまま振り返った。
「今日は、真行にも飲まそうぜ、いつも途中で抜けるだろ、あいつ」
「意外と下戸だったりしてな」
夢うつつのように、ひどく遠くから、先輩たちの声が聞こえる。
抱きしめられている 苦しいほどの強い力で。
息を求め、ようやく顔を離したあさとの耳元に、琥珀の唇がかすめるように触れた。
「……馬鹿、挑発しやがって」
胸の奥が、ズキズキしている。
嬉しいのに、辛い。痛くて、苦しくて……何も言えない。
見下ろされる眼差し、頬に触れている指。
もう一度抱きしめられると思ったが、琥珀はそのまま、そっとあさとの髪に指を絡めて、頭を胸に引きよせた。
「……さわらせんな」
「え?」
「俺以外の誰にも、さわらせるな」
琥珀……。
胸が熱くなる、暖かなものが切なく満ちる。
やっぱり、そうなんだ。信じられないけど、嘘みたいだけど。琥珀が……私のために、嫉妬してくれていたなんて。
「… 瀬名」
掠れた声。琥珀の声。何度でも呼んでほしい。その声を聞くだけで、私は十分幸福だから。
見下ろしている眼に、燃えるような色がある。冷たい指先に唇をなぞられ、たまりかねたように、もう一度抱きすくめられた。
「あ……」
そのまま、気がつけば畳の上に、組み伏せられていた。
琥珀の唇が、首筋に触れている。
吐息……熱い腕。……頬に触れる琥珀の髪の香り。
背に腕を回して抱き寄せられ、身体がいっそう深く寄り添い合う。力強い手が背を撫で、腰を滑って、胸の下に触れた。
もう一度名前を呼ばれる。琥珀の声が掠れている。どうしよう、このまま……流されてしまいそう。
あさちゃん。
ふいに雅の声が頭をよぎった。
まるで冷たい楔を、いきなり胸に打ち込まれたようだった。
あさとは自分の身体が、刹那に硬直するのを感じた。
琥珀の手も、指も、唇も、きっと同じように 雅に触れたはずだ。
あさとの迷いを察したかのように、ふっと琥珀の身体から熱が引いた。そのまま静かに触れあっていた首が離れ、身体ごと離れていく。
嫌……。
途端に、切なさがこみあげる。
琥珀の腕にすがりつく。矛盾してる、馬鹿な私。それでも琥珀を離したくない。この人が好き、苦しいくらい好き。
「 ごめんな……」
やがて、月明かりの下、壁にすがって寄り添いながら、琥珀が小さく呟いた。
「ううん」
あさとはそのまま、温かな胸に顔を預けた。マフラーの毛糸が頬を指す。その痛みさえ愛しかった。心臓の音が聞こえる。……目を、閉じる。
「私が、それでもいいって決めたんだから」
「俺は……お前に、何もあげられない」
知ってる。
「心も身体も、……あげられない」
知ってるよ……。琥珀。
あれだけ苦しい抱擁をしながら、琥珀は、一度もキスをしなかった。
彼の心の底には、それでもまだ冷静でいられる部分があって……。
「琥珀……」
「……どうしたらいいかさえ、わからない」
その先に進む扉は、雅がいる限り、絶対に開かれることはない。
あさとは顔をあげた。この人と繋がっていたい。心が無理でも、身体が無理でも、別の何かで繋がっていたい。
「傍にいて……」
今だけでいいから。
「もう一度、さっきみたいに、抱きしめて」
「…………」
「他には何もいらないから、何回でもして、厭きるくらいして」
私はそれで幸せだから。
他には何も 求めないから……。
|
|