あさと!!
瞬間。
ガラスが砕けて、世界の全てが鮮明になった。
お母さん?
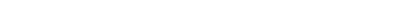
第一章 ユリウスの乙女
1
「私に触らないで……」
最初に唇から零れたのは、ひどく虚ろな、囁くような声だった。
鮮明になった視界に、ゆるやかに琥珀の顔が浮かび上がる。いや、琥珀の顔を持つ、決して琥珀ではあり得ない男の。
あ……。
愕然と目を見開いたあさとは、流れるように、 自分の意識が巻き戻っていくのを感じていた。
私……何やってた? 今まで……。
夢としか思えなかったおぼろな記憶、曖昧な意識。戸惑うほどに、それは急速に現実となり、鮮明な自我となっていく。
血塗られた結婚式。
全てが一変してしまった囚われの日々。
死者の森。邪教の館。
足元に転がってきて触れたもの。血の匂い、悲鳴、そして 。
雷鳴。
あさとは眼を見開いたまま、ほとんど間近にある その男の顔に、ようやく全ての焦点を合わせていた。
「どうした」
男 コンスタンティノ・アシュラルは、嘲るような眼差しで、かすかに口元を歪めて笑う。
「何故そんな眼で俺を見る。そんなに懐かしいか、俺の顔が」
低く通る声を聞いた途端、あさとの手も足も、無様なほどに震え始めた。忘れていた恐怖と絶望が、触れられている箇所からざわりと這い上がってくる。
背に回された腕、覆いかぶさっている顔。吐息さえも触れる距離だ。今 この忌むべき男にベッドの上で抱き支えられているのだとあさとは知った。
琥珀と瓜二つと言っていい漆黒の瞳が、疑念とさげすみにも似た冷たさを浮かべて見下ろしている。
それは 今のあさとにとっては、恐怖としか思えない顔だった。
大きな手がのびてきて、震えるあさとの顎をぐいと掴む。
「ようやく正気を取り戻したか」
手 男の手。
「それともずっと、気の触れた芝居でもしていたか」
フラッシュバックのように、あの夜の情景が蘇る。
その手で何をされたのか、身体と心が発した悲鳴。あれは あれは、夢ではなかったのだ。
「離して……」
あさとは震える声で言った。その瞬間、胃の底から冷たいものが込み上げて、ぐう、と軽い嘔吐感がした。
男の眼差し、唇の形、衣服の隙間から垣間見える胸元。
いや……。
あの時感じた絶望と痛み、恐怖と憎悪。
「なんだ? まだ、夢でもみているような顔をしているな」
蔑むような声、さらに顎を引き寄せられる。
「もう一度、同じことをしてやろうか?今度は少し優しくしてやってもいい」
「な、」
唇が、吐息がかるほど近くなる。ようやくあさとは我に返っていた。
「やめて……!」
男の胸を両手で突いた。思いっきり突き飛ばしたつもりだった。が、大きな体はわずかに引いただけで動じない。反射的に腕を振り上げている。頬を 力いっぱい叩くために。
けれど振り上げた腕は、あっさりと大きな手で絡め取られた。
「少しは元気になったようだな」
「………っ」
圧倒的な力と体格差。暗い影に覆われ、再び絶望的な思いが胸にあふれる。が、それを振りきるように、あさとは腕に渾身の力をこめた。
「離して……!」
「もちろん? それがお前の望みとあらば」
からかうような声と共に、手はあっさりと自由になる。あさとは即座に身を引いて、あとずさるように壁際に逃げた。
自分の衣服に乱れはない。まずはそれを確認して安堵する。
今って……いつだろう。
混乱の中、あさとはようやく、現実を受け入れ始めていた。
あれから、なにをやってたの? 私?
夜だろうか、昼だろうか。あの夜からどれだけ時間がたったのだろうか。
外光のない閉ざされた室内。くすんだ灰色の石壁と床。四方にはカンデラのような灯りが揺れていて、これが、この部屋唯一の照明器具らしい。
よく見れば壁際には壊れた家具の類が無造作に積み上げられていて、まるで、物置か何かを慌てて客間に作り変えたような様相だ。
あさとは、自身が座るベッドを見た。朽木を組み合わせて作ったような簡素な代物だが、シーツや枕は清潔そうだった。
アシュラルは 腕を組んだまま立っている。
刺繍をしたタブレットにレースのフラットカラー。右肩から黒いクロークが流れるように垂れている。組んだ腕、その左手の指に、怪我でもしたのか白い包帯が巻かれている。
それは、少なくとも、あさとの記憶に残る、あの夜のアシュラルの姿ではなかった。
顔つきも違う。今の彼は、先夜のような余裕のない表情をしてはいない。どこか冷めて けれど楽しそうにさえ見える冷笑を浮かべ、珍しい物でも見るような目で縮こまるあさとを見下ろしている。
実際、彼の前で、あさとは追い詰められた小動物も同然だった。
こんな奴に……。
新たな悔しさが込み上げる。あさとは顔をあげ、アシュラルを真っ向から睨みつけた。
「……出ていって」
アシュラルはわずかに眉をあげる。
「いつまでそこに立っているつもりなの? 出ていって、二度と私の前に現れないで」
握りしめた拳が、わずかに震えた。
「二度と私に触らないで!」
ありったけの憎悪をこめて投げた言葉。けれど男が動じる様子はみじんもなかった。アシュラルは目をすがめ、首をわずかに傾ける。
「それほど怒ることはない。婚約者どの、俺たちは当然のことをしたまでなのだから」
「当然の……こと?」
「婚約を交わした男と女であれば、当然、なすべきことだろうが」
意味を悟り、あさとは愕然と唇を震わせた。
「誰が、……あなたなんかと!」
「ほう、ではあれから何度も俺に抱かれたことを覚えてはいないのか?」
「………」
頭の中が蒼白になる。が、アシュラルはすぐに失笑した。
「ばかな女だ、本当に何も覚えていないのか。お前の傍にはラッセルがつきっきりで、俺が近寄る隙さえ与えてくれなかったというのに」
ふざけたように彼はそう言い、歩いて壁際に背を預ける。
ラッセル。
はっと、あさとは息を引いた。
そうだ、ラッセル、ラッセルは 。
傷口を拭う冷たい柔布。憂いを込めて見上げる繊細な眼差し。それを思いきり叩いて それから……。
それから?
混乱しながら眉を寄せる。
自我が そこから途切れてしまっている。
その後のことは、まるで夢でもみていたように曖昧だ。
まるで、ガラスケースに閉じ込められて、その中から全てを見ていたような。 嗅覚も味覚も肌に触れる感触さえも、全て他人を通しているような。……
不思議で曖昧な離脱感。
それが、ついさっきまであさとが感じていた世界の全てだった。
ああ、そうなんだ。
あさとはようやく合点がいった。
だから、ずっと思っていた。
何をされても、平気。何も感じない、何も怖くない。
私は私じゃないんだから。ここにいるのは、瀬名あさとじゃなくて「クシュリナ」なんだから。
私は 何処にもいないんだから。
私は……。
死んでしまったんだから。 。
あさと!
幻聴か空耳か、確かに覚醒する刹那、母の声が聞えた気がした。
それがあさとを呼び戻した。自我へ 夢から現実へ。
どくどくと鼓動が脈打っている。生きている あさとは胸を押さえて目を閉じた。これは私。私の身体。私の心。
私は 。
私は瀬名あさとだ。姿形はそうではなくても。多分、この世界に生れ落ちた瞬間から、ずっと 瀬名あさとだったのだ。
|
|