|
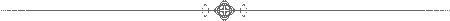
「瀬名先生」
その声に少し驚いて、瀬名志津子は顔を上げていた。
「小田切君?」
スタッフでよく利用する、いきつけのラウンジバーだった。
こんなところに、小田切が現れたのも意外だったが、彼の表情が妙に落ち着いて見えたのにも驚いていた。
「隣、いいですか」
コートを脱いでウェイターに預けると、彼は静かに歩み寄ってきた。
細身のグレーのスーツにネイビーのネクタイ。場慣れした態度。いつもと随分雰囲気が違って見える。
「下手クソ」
出されたリキュールを前に、小田切の横顔が呟いた。
「え?」
「俺、昔ホストクラブでバイトしてたことがあるから。出すときは、こう」
グラスを持ちあげ、きれいな指で、再度、志津子の前に置きなおす。
「なんだか贅沢な気分になるわね」
志津子を見下ろし、はじめて冷たい唇が微笑した。
「そう思ってもらうのと引き換えに、高い金取ってるから。多分、原価聞いたら二度と頼む気なくしますよ」
「だったら、聞かないほうがいいわね」
眉をあげ、志津子も自然に微笑している。
「恩田さんに、先生ならここにいるからって教えてもらって」
「そう」
それきり、小田切は黙る。
志津子も黙ったまま、自身のグラスを空にした。
「随分、すっきりした顔してるわね」
さほど飲んでいないのに、もう、酔いが回っているような気がした。答えない小田切の横顔は、わずかに笑みを浮かべている。
何か、いいことでもあったのかしら、と、思いつつ、志津子は、新しいカクテルをオーダーした。
私と違って若いんだから、楽しいことがあるのは当り前だ。だって、もうすぐクリスマスだし。
店内にはクリスマスソングをアレンジしたサウンドが流れている。窓の外からは、赤と緑のライトが交互に輝き、ガラス越しに彩りを添えている。
「……先生のおかげで、忘れていたことを思い出せたのかもしれない」
しばらく黙っていた小田切は、やがて静かに切り出した。
「自分の感情と向き合うのが、……こんなに辛いとは思わなかったけど」
言いさして、かすかに苦笑する。
では、小田切は、段階をひとつ乗り越えたのだろうか? でも、だったら何故、こんな時間に、彼は一人で私を訪ねて来たんだろう。
「神様って、いると思いますか?」
「えっ?」
驚いた志津子は、隣の人を仰いでいる。小田切は笑っていた。
「そういう質問こそ、奥様にすべきなんじゃないのかしら」
「答えは決まっていますから。神様はいる、そしていつもあなたを見守っている」
「クリスチャンには、愚問ね。確かに」
「先生の意見が聞きたい」
「…………」
少し考えてから、志津子は答えた。
「いるとしたら、それぞれの人の心の中ね」
「すごい、精神科医のベストアンサーだ」
横顔を見せ、楽しそうに小田切は笑った。
「小田切君は?」
「いませんね。そんなものはどこにもいない」
「………」
一転した冷めた物言いは、彼が、まだ心の底にある闇から、完全に抜け出していないことを意味しているような気がした。
「神なんていない。本当にいるなら、世の中はもっとよくなっている。信じたい気持を否定する気はないけど、俺は、これっぽっちも信じていません」
「だったら、君の心には神はいないのよ。それはそれで正解ね」
それはそれで正解。けれど、すがるものを持たない心は、いったい何を拠り所に生きているのだろう。
彼が そんなに、強い人間だとは思えない。ただ強くあろうと、頑なに心にガードを張っているだけだ。
彼の弱さを、多分誰よりも知っているから、小田切静那は、夫のカウンセラーを私に任せたのではないだろうか。
「親父……俺が小さい時に肺ガンで死んだんですけど、死ぬ前に、俺にこう言ったんです。直人、神様ってのは本当にいるんだ」
「………」
「静那は、……その意味をずっと俺に教えようとしてきたんだと思います。でも、俺には受け入れられなかった。どんなに綺麗事で飾り立てても、結局親父は死んで、あの女は生きているんですからね」
母親のことだろう。多分。
「お父様の幸福と、お母さまの存在は、関係ないと思うけど」
「父が幸福だった? 静那は必ずそう言います。でも何故? どうやって? この世の誰が、それを判断するんですか? 結局、父の気持は父にしか判らない。それを……幸福だったの一言で片づけられるのは……不愉快だ」
静那の気持も、小田切の気持も、志津子には判る。
この世はしょせん、生者で構成されている。死者の声は 生きる者が、都合よく代弁してやるしかないのだ。失ってもなお、ひるまずに生きていくために。
「……私のカウンセリングは、無意味だったってことね」
「ひとつだけ、わかったことがあります」
小田切は空になったグラスをカウンターの上に置いた。
「俺は寂しかった」
「まぁ」
「静那にも甘えていた……。反省しました。でも、もう手遅れだったけど」
手遅れ?
志津子は、隣の男の横顔を見上げている。
「先週、話し合って、これからは別々に暮らしましょうってはっきり言われました。本当は、随分前から判っていたんです。あいつが、少しずつ、俺から離れようとしているのが」
「それは、……ないんじゃない?」
だって、だったらどうして、彼女はあんなに真剣な目で、私にこの人のことを頼んだのだろう。
「先生が、静那のお眼鏡にかなったのかな?」
「え?」
「いえ……。独り言です」
僅かに視線だけをこちらに向け、小田切は形良い口元を和ませた。
「俺のわがままで、随分あいつを苦しめてきたから……。少し、距離を置いた方がいいんです。この半年、苦しかったし、子供みたいに抵抗したけど、……俺も、……やっと、静那と離れても大丈夫だって、そう思えるようになったのかもしれない」
何かを思い切るように言うと、小田切は新しく目の前に置かれた淡い桜桃色の液体を飲み下した。
「先生のおかげです」
「別れる手助けをしたつもりじゃないのよ」
「わかってますよ。そんな、責任をかぶせるつもりで来たんじゃない」
「…………」
「お礼を言いに来たんです。それと、随分困らせたから……お詫びです」
何か、気のきいたことを言おうと思ったが、全ては気休めなのだと気がついた。
今、志津子が、胸の裡で思い悩んでいることを、誰に、どう言葉を尽くして励まされても、何の意味もないように。
しばらく、無言で飲み続ける。沈黙が不思議と心地よかった。何かを話したり、気分良く盛り上がるわけでもないのに、いつまでもこのままでいたいような気持になる。
「……先生」
隣で、グラスの氷が音をたてた。
前髪が額に落ち、その表情を影で覆っている。
今日、初めて小田切の本当の声を聞いたような気がした。
「昔、静那が言ったんです。時間が、このまま止まったらいいって」
「…………」
「俺には、その本当の意味なんて何もわかっていなかった。でも、今ならよく判るんです。……静那は、恋に永遠がないことを、最初から俺に教えていたのかもしれない」
恋に、永遠がない。
そうかもしれない。どんな激しい恋も、愛も、いつかは冷めるか別のものに変わっていく。
「人の気持ちを止めておくことって、できないものなんでしょうか」
「………」
辛そうな口調に顔を上げた志津子だったが、小田切は不思議に落ち着いた眼で、静かに微笑していた。
初めて志津子は気がついていた。最初から、彼の笑顔にひそむものは、ふっきれたことから来る落ち着きできない。……一種の、あきらめにも似た悲しみだ。
私と……同じだな。
ふっと、半ばなげやりに心の鍵が解けている。
「どんなに好きになっても、いつか、冷めてしまうものなら、恋愛なんて、なんのためにするんでしょうね」
「理屈でするものなら、私だって二度と恋愛なんてごめんだわ」
「え?」
振り返った小田切の顔が、初めて心許なく見えて、一瞬、まるで子供に対するような愛しさを感じている。
「頭で考えて恋愛する人なんていないのよ。その質問は、散財するとわかっているのに、毎日パチンコ屋に通うおじさんに聞いた方が的確なんじゃない?」
「ひとときの快感ですか」
「うーん、夢のない回答ね。きっと、逃げていくお金より、価値がある何かを、その人たちは知っているのよ」
ん? と、しばし考える目になった小田切が、やがて訝しい目を志津子に向ける。
「…………先生、パチンコしたこと、ないんじゃないですか」
「あはは、適当に答えてるの、バレちゃった?」
ひどく間近に、きれいに引き締まった顔の輪郭がある。
こんなに誰かを、身近に感じたのは、どのくらい前になるだろう。
ふと、近づきすぎる漠然とした不安を感じ、志津子は、もう一杯カクテルを注文した。
「随分、飲まれるんですね」
「そう? いつもこんなものよ。まだまだこれからだから、帰るなら、どうぞお先に」
「………」
グラスに伸ばした手を、上から小田切の手が押さえた。
「 俺が、誘惑してみましょうか」
「……?」
冷たい指先だと思った。自分の体温が上がっていたのかもしれない。
「俺があの女を誘惑したら、ご主人、家に帰ってくるでしょう」
冷たい目は、愛のうつろいやすさを証明することに、むしろ喜びさえ感じているように見える。
「いいですよ、瀬名先生が望むのなら」
「なに……」
一拍おいて志津子は、「馬鹿なこと言ってるの!」
思わず大きな声になってしまっていた。驚いたように、周囲の客が振り返る。
はっとして志津子は口をつぐみ、取り繕ったように前に向き直った。
「……小田切君」
額に手をあて、志津子は軽く息を吐いた。酔いが急速に冷めていく。
言いたい言葉は沢山あった。彼を諭すことも責めることもできる。
が、そのどの言葉も、今の彼の胸には響かないだろう。
「悪いけど、うちのだんなのほうが、あなたよりいい男よ」
「 ……」
どこか澄ましていた彼の顔が、ややあって、みるみる柔和に溶けていく。やがて笑いを堪えるように、小田切は口元に拳をあてた。
「それは、……失礼しました」
「そう、随分失礼なセリフよ」
「負けました、先生には」
「一回りも年上の女に、勝てると思うほうが間違いなの」
多分、これは彼なりの、感謝の意思表示なのだろう。
馬鹿な男。……他人に上手く気持ちを伝えられない不器用な男。
「帰らないの?」
「帰っても、誰もいないから」
誘っているのだろうか。それとも、誘われているのだろうか。
「じゃ、もう少しつきあってくれる?」
「いいですよ」
多分、どこかで判っていた。
互いの手の温度を感じた時から、その夜の行き着く果ては。 。
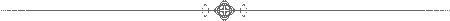
別に、彼を必要としていたわけではない。
彼もまた、上司の妻であるセラピストに特別の感情を抱いていたわけではない。
ただ、互いを包んでいた感情が、不運な形で同調してしまっただけ。
あの夜、たとえ彼が早く帰宅していたとしても、深夜の繁華街で起きた惨事は、防ぎようがなかっただろう。
それでも小田切は、あの夜のことを忘れない。自分が犯した過ちを、生涯、繰り返し責め続ける。
多分、彼が追っていたのは。 。
流れゆく景色を車窓から眺めながら、志津子は苦く両目を閉じた。
小田切が追っていたのは、門倉雅の名を借りた自分自身の姿なのだ。
|
|