|
9
「先生、どうしました?」
診療室を出たところで、恩田佳織に出くわした。
驚いた顔で自分を見上げる恩田の目から、顔を逸らすことさえできかった。
「どうしたんです? 顔色、怖いくらいに真っ青ですよ」
「別に、……少し疲れたのかしら」
「でも」
「悪いけど、冷たい飲み物を、お客様に出してもらえる?」
志津子はそれだけ言うと、廊下を隔てたサニタリーに飛びこんだ。
鏡に映る顔を見る。本当に、ひどい顔をしていた。
まだ、風間は診療室で端座している。もうすぐ午後の診療が始まるから、早く、用件を済ませて戻らなければ。
それにしても、とんでもないことに首をつっこんでしまった。
(先生、僕は、小田切と門倉雅がどこかで接点を持っていたなら、それは医師と患者、というケース以外にはないと思うんですよ。だから、お願いなんですが)
(静那さんの事件以前に、外来患者として門倉雅が訪れていたかどうか、それを確認してもらえないでしょうか)
志津子はようやく、風間潤の本当の目的がわかったと思った。
彼は最初から、自分を通して小田切と門倉雅の接点を探り出そうとしていたのだ。
まわりくどい説明をさせ、ロムを見たくなるように仕向け、完全に興味を向けさせておいてから。引くに引けなくなってから。
なんて男、見かけより相当に頭がいい、うかうかと引きずりこまれてしまったじゃない、この、私としたことが。
志津子は眉根を寄せながら考えた。
もう、後には引けなかった。志津子自身、それを確認しなければすでに落ち着かなくなっている。
外来患者の記録を調べる。それは、比較的簡単にできるはずだ。
門倉雅は、事件後しばらくこの病院に入院していた。彼女の診療記録は、過去十年間は最低でも保管される。小田切の事件は……確か、六年くらい前だったから。
「馬鹿馬鹿しい、そんなこと、まずあり得ないのに」
我に返り、志津子は頭を振ってみた。そうだ、しょせん、全ては風間の妄想ではないか。冷静になれば、あのロムの内容だけを見て、雅ちゃんが、静那の殺害に手を貸していると想像するほうが、どうかしている。
多分、あの熱心な目に、自分まで毒されかけている。
志津子はいくらかマシな気分になって、手だけを洗うとサニタリーから出た。
あり得ない、だから、それを確認してみればいい。
恩田佳織が、盆を下げて診療室から出てくるところだった。
「ああ、恩田さん、悪いけどもうひとつ頼まれて。多分、すぐに判ると思うから、結果を私に知らせてもらえる?」
志津子は、風間の依頼どおりのことを、恩田佳織に頼むと、けげんそうな彼女を置いて、再び診療室に戻った。
「すみません。お時間をとらせてしまって」
「いや、すみませんは、こちらのセリフです」
風間は、恐縮しているのか、目の前に置かれたアイスコーヒーは手付かずのままだった。
「僕が、……本当の刑事だったら、こんなお手数をとらせることもなかったんですが。なにぶん、懲戒覚悟で、有休を使っている身ですから」
その優しげな眼差しに、もう騙されない。
志津子は身構えて、対面のソファに座った。
が、しばらくたってから、風間の言葉が胸の内に響いてくる。ああそうか、今日は平日で、この男は職務としてここへ来ているわけではないのだ。
「風間さん、独身なんですか?」
ふと、風間個人のことが、聞きたくなった。
「え? ええ、独りです」
少し驚いたように、瞬きをする。
優しげで、目が綺麗だ。女性が甘えやすいタイプの顔だと思った。小田切と同年なら、まだ三十を二つ三つ、過ぎたばかりというところだろう。
「ご結婚はなさらない?」
「……そうですね。……したいと思ったことは、不思議なことに一度もありません」
「どうしてかしら」
「うーん、いいものですか、結婚というのは」
風間は逆に訊いてきた。志津子は少し微笑した。
「いいものじゃないかしら? 少なくとも、してみる前は、みんなそう思っているんじゃない?」
結婚後の苦労など、してみる前は想像さえしていなかった。
若かった、勢いで妊娠し、結婚を決めた。今は……夫への愛は、冷めてしまって跡形もない。
「それでも、僕には、いいものとは思えないんです。結婚というよりは、女性を好きになること自体が苦手なんですかね」
風間は静かな口調で言うと、アイスコーヒーを唇につけた。
「………」
女性、と言ったわよね。この人……。
冷静を装い、志津子は自分もグラスを手にした。
そうか…そういう人だったんだ。だから小田切君にこだわってるとか? まんざら小田切君も…? いやいや、それはないと思うけど……。
「? どうなさいました?」
「あ、いえ、なんでも」
微笑して、志津子は自身もコーヒーを取り上げた。
考えだすと、ますます居心地が悪くなる。
10
「好きになるのは簡単ですけど」
グラスを置いて、風間は続けた。
「気持ちはいつか冷めるでしょう。それが、僕には多分耐えられない。面倒だし、辛い、それでも人を好きになる気持ちが、僕には判らないのかな」
うつむいた表情が、どこか寂しげに見えた。
「……うちの両親は、僕が大学の時に離婚しましたからね。色々あって、決めたんです。僕だけは、そんな面倒な真似はしないって」
「それは……極端な発想ですね」
「独身もいいものですよ」
わかります。とは言わなかった。一応、人生の先輩として、また子孫を残さねばならない人類の一人として、結婚を否定することはできない。
それでも、風間の少し偏った生真面目さは、どことなく微笑ましかった。本人の雰囲気にもよるのかもしれない。
「愛情は信じられなくても、友情なら信じられますか?」
「え?」
「あ……、ごめんなさい、小田切君のことです。そんなに熱心に彼のことを考えられるなんて、ある意味すごいな、と思ったものですから」
友情というか、そこに一種の愛情を感じる とはさすがに言えなかったが。
「……あいつには、借りがあるんです」
風間は、ゆっくりと視線を落とした。
「昔の恥になりますが、……とんでもないことをやらかしたことがありましてね。高校の時です」
「とんでもない、ことですか」
「発覚していたら、僕はここにはいなかったと思います。小田切みたいに打たれ強いわけでも、頭がいいわけでもないんで……。お察しだと思いますが、何も言わずに罪を引き受けてくれたのが、あいつでした」
「…………」
「その後、色々あって……小田切が退学して、……あれだけ逃げ回ってた静那さんと両想いになってたのには、驚きましたよ。ええ、女にはだらしなくても、自分から追いかけるような男じゃなかったのに、なんていうのかな、他の男が視線を向けるだけでも許さない、みたいなね」
「ある意味うらやましい話ですね」
風間の口調が楽しそうなので、志津子も自然に微笑している。
「そうかな。静那さんは、困ってるようにしか見えなかったですけどね。なんだかんだ言ってもあの人は大人で、小田切は子供だったから。……なんでも小田切の言うとおりにするように見せて、実は彼女が、奴をきっちりコントロールしてる、みたいな」
「まぁ」
志津子は笑って、風間も笑う。が、その笑顔はすぐに消え、苦笑のような溜息がもれた。
「あの頃が……一番幸せだったような気がします。今になって思うことですけど」
「………」
「……止められないもんなんですよねぇ。……時間っていうのは」
寂しさを堪えるように、目が厳しく眇められる。
「なんだか、残酷な気がしますよ」
同じようなことを、以前、小田切が口にしたことがあった。
(教えてもらえますか、先生)
(人の気持ちを、止めておくことはできないんでしょうか)
「先生」
ノックがして、恩田佳織が顔を出したのはその時だった。
「調べてきましたよ。……あ」
風間がまだいることを知って、口をつぐむ。
「かまわないのよ、恩田さん」
「ええ、……あの、該当なしです」
恩田佳織は、手元のコピー用紙を何枚か差し出した。
「門倉雅さんが、該当年度、外科外来に来られた記録はありませんでした」
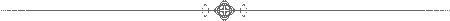
今日は、もう、こないのだろう。
瀬名志津子はそう思いながら、『小田切直人』のファイルを閉じた。
二週間前から開始したカウンセリングは、水、金の午後七時から始めることになっている。
時計の針は、もう八時前を指していた。
今日は、あさと、晩ご飯いらないって言ってたわよね。
志津子は立ちあがり、帰り支度を始めた。手早く机の上のものを片付けながら、どこかでほっとしている自分がいる。
今日だけではない、ひょっとしたら彼は、もう二度と来ないのかもしれない。そんな予感がするのは、一昨日のセッションで、初めて彼の母親のことに触れてみたからだ。
(面白いな、それを先生に話したら)
どこか皮肉な笑みを浮かべて、小田切直人は即座に切り返してきた。
(俺の人生が、劇的に変わったりするわけですか)
カウンセリングは数回に及んだが、寡黙な研修医がカウンセラーに心を開く気配は微塵もなかった。
本人に、診療を受ける気がまるでないからだろう。信頼関係がない以上、何度セッションを試みても無駄な気がする。
にしても、その頑固な小田切を、カウンセラーの所にまで行かせることができたのは何故だろう。自分では手に負えないようなことを言っていたが、小田切静那は、ある意味完全に夫の心と行動を掌握しているような……気がしてならない。
「てか、ただの夫婦喧嘩?」
だとしたら、なんだか馬鹿馬鹿しくなってくる。犬も食わない代物なら、他人を巻き込まずに夫婦で解決してほしい。
「………」
華奢なうなじ。白い背中に沁みた唇の痕。
その時想像した光景を思い出し、少しだけ頬が赤くなった。そして、初めて自覚する。
私、……嫉妬してるんだろうな。
小田切の妻に。恋とは全く無関係の部分で、一人の既婚の女性として。
どんな時でも、自分の心理を冷静に分析してしまうのは、昔からの悪い癖だ。
夫に、身体ごと 傷を残すほどに愛される。身動きできないほど束縛される。それは、一体、どんな気持ちなのだろう。
志津子には、悲しいくらい判らない。二十歳で子供を産んで、それからはあっという間だった。仕事と育児に追われ、何時の間にか、夫の女関係にも、気持ちが麻痺してしまっている。……
その時、扉が軋んだ音をたてた。
「なんだ、まだ、いらしてたんですか」
「小田切君」
驚いて、手元のファイルを取り落としてしまっていた。
長身のシルエットが、闇から浮き出すようにして現れる。
プリントが入った黒のシャツにジーンズ。彼が一度帰宅し、また戻ってきたのだとはっきりと判る服装だった。
「……いいですか、今から」
声もそうだが、ひどく暗い眼をしている。
「いいけど……」
お酒?
冷めた表情は、いつになく虚ろに見えた。いずれにしても、こんな彼を見たのは初めてだ。
「なにかあったの?」
拾ったファイルを片手にソファに腰掛けながら、志津子は訊いた。小田切は入り口あたりに立ったまま、みじろぎせずに何処か遠くを見つめている。
「……静那、出ていきました」
「………」
「もう、何をしても駄目なんだなって……どっかで覚悟はしてたけど」
言葉を切り、少しだけ男は笑った。胸が痛くなるほど、なげやりな笑い方だった。
「やっと判りましたよ。あいつにとっては、俺はいまでも、死んだ弟と同じなんだって」
「弟?」
「ええ、聞いてませんか? 静那から。俺はもともと、あいつの弟の身代わりなんです。最初からずっとね」
ソファに、身体を投げ出すようにして座る。
「男として俺を頼ってくれたことなんて一度もなかった。何をしたって、俺はあいつにとっては、まだ小さな子供なんです」
「普通、弟とは結婚までしないわ」
「……静那はできるんです。キリスト教徒だから何でもあり」
子供じみた言い草に、志津子は思わず苦笑している。
「それは誤魔化しね。小田切君。何をむきになって否定しているのかしら?」
「………」
無言になった男は、きれいな指で額を押さえる。それまでの口調とは裏腹に、苦しげな横顔だった。
「それでも……静那は……、肝心な時に、俺じゃなくて他の誰かを頼るんです。……男として、俺を見てはくれないから」
小田切に同調してはいけない。志津子は自分に言い聞かせた。
冷静に 今、彼はようやく心を開こうとしている。もう一度その心が閉じる前に、楔を一本打ち込まなければならない。
「それは、あなたも同じだったんじゃないのかな」
志津子は柔らかな口調で切り出した。
ゆっくりと顔を上げる男の目の鋭さに、一瞬、射抜かれそうになる。
「あなた自身はどうだった? 静那さんのこと、一人の女として見ていたと言える? あなたは静那さんに、お母さんの代わりを求めていただけじゃないかと、私は思っているんだけど」
小田切は微かに冷笑を浮かべると、そのまま頭を背もたれに預けた。
「なるほど? さっそく、診療の始まりですか」
「教えてもらえる? お母さんのこと」
「前も話しましたよね」
前髪をかきあげる指 志津子は知っている、それは彼が、少し苛立っている時の無意識の癖だ。
「小二の時でしたかね。学校から帰ると、もうお袋はいなくなってて、それきり二度と帰っては来ませんでした。次の日から借金取りが毎日家に来るようになって……親父は公務員でしたからね。噂になって退職しました。自宅もその時に売ったんでしょう。ちっぽけなアパートに、二人して移り住みましたから」
「お母さんがどこへ行ったか、あなたは聞かされていなかった?」
「近所の噂で」小田切は肩をすくめる。
「男と一緒に仙台のほうに逃げたんだろうって。親父は、お袋の愛人だった男の保証人になっていたんです。二千万。自分の妻を寝とられてることなんて何も知らずに……ある意味、バカだな、と思いますけど」
「…………」
その後の経緯は、志津子もよく知っている。
小田切父子は職を求めて東京まで流れ着き、そして冬木静那の祖父母が経営するアパートに住居を得たのだ。
別れたきりの母親は、逃げた愛人と再婚したらしい。
小田切の父が病死した後、静那は母親を探し出し、生活の援助を申し出る。やがてそれは、母親らの脅迫まがいの言動により、強請の形相を帯びてきたのだが。……
「お母さんがいなくなったとき、あなたはどう思った?」
ふっと、彼が一時、言葉に窮したのが判った。
「まだ札幌にいた頃、あなたが帰宅するとお母さんがいなくなっていた。その時、あなたはどう思った?」
「どうって……」
小田切は、やや呆れたように眉をあげた。
「別に、何も感じませんでしたけど」
「本当に?」
「それ以前から、親父を裏切って男を作るような女ですからね」
「でも、あなたは当時、そこまで知らなかったんでしょう?」
む、と彼の表情に苛立ちが浮かぶのが見て取れた。
「いつ知ったかなんてどうでもいい。あんな女の顔なんて、二度と見たくないし、思い出したくもないんです。出ていく以前から、あいつは最低の女だった。俺に言えるのはそれだけですよ」
強い光を放つ瞳。駄目、同調してはいけない。
「お父様は、当時、随分忙しい仕事をしていたと、先日、教えてくれたわよね」
「役所が遠かったせいもあるけど、朝は六時に出て、帰りはいつも、十一時すぎでしたからね」
「じゃ、あなたは、お母さまが出て行って以来、一人で夜を過ごすようになったんだ」
話の意図が判らないのか、小田切の目が訝しくすがまる。
「あなたは、一人の夜をどう思った?」
「……一人?」
「そう、一人きりの夜、一人きりの朝をどう思った?」
小田切の強い光がわずかに緩む、緩んで、揺れる。
そうだ、予想していた通りだった。 これが、彼の核心なのだ。
「あなたは、本当はすごく寂しかった。捨てられた猫みたいに、寂しくてしょうがなかった」
多分、本当の原因はそこにある。
「馬鹿馬鹿しい。そんな、……ことは絶対にない」
多分、正式な病名をあえてつければ、軽度の不安神経症なのだろう。
強い憎しみは強い愛情の裏返しだ。小田切直人は、おそらく母親をかなりの強さで愛していた。別れた後も、裏切られた後も、心のどこかで渇望するほど求めていた。
予想していたことだが、彼の女性遍歴は、全て年上の女性で占められている。それも、無意識に母親を求めた表れだろう。
「小田切君、いい加減に認めようよ。君はね、愛した人に捨てられた記憶から抜け出せていないの。その時感じた、寂しいとか、哀しいとか、辛いとか、そういう感情があまりにも強くて、また、同じことを繰り返すのが怖くて仕方がないの」
「ちがう」
即座に否定されたが、それは、囁くような声だった。
「いくら愛しても、いつか失う。それが怖くて、不安になる。不安は畏れに、畏れは疑いに変わっていく。……悪循環ね」
「………」
「あなたは、いなくなった母親の代りを、静那さんに求めているのよ。彼女には、それが最初から判っていて、あなたの期待に応えようとしてくれている。そうじゃないかしら」
眉を寄せたまま、小田切は面を伏せる。
「なのに、そんな彼女の態度が、あなたには気に入らない。男として頼られていないのではないかと、自信をなくしかけている。そうよね?」
返ってくる答えはない。
「彼女が、君の母親の生活を支援をしていたのは、いずれ君と母親を和解させようと思っていたからじゃないかしら? きっと私よりよく知っていたのよ。失う怖さに怯えている君を、本当の意味で不安から解放させるには、何が必要だったのか」
まだ、「違う」とその唇は呟いているようだった。
志津子は、彼の肩を叩いて立ち上がった。
「もう一度、静那さんと話し合ってみなさい。彼女の求めるものも、あなたの求めるものも一緒だから。絶対に」
|
|