|
8
小田切直人は、やはり、あさとと同じように眠り続けたままだった。
志津子は重い足取りで、男の枕もとにそっと立つ。
初めて医局で会った時と、顔の作り自体は変わらない。
目元が美しく、繊細さと野性が同居した面差し。今にも眼を開けて笑ってくれるような気がした。昔のように、笑うことに慣れていない不器用な笑顔で。
伸びた前髪が額にかかり、多分そのせいだろう、ここへ来た当初より、むしろ印象が幼くなったような気がする。
志津子は目を眇め、しばらくそのままの姿勢で、立ち尽くしていた。
(静那……嘘だろ、なぁ、……なんとか言えよ)
(言えよ、馬鹿野郎! どうして俺に言ってくれなかった、どうしてだ、どうしてなんだよ、静那!!)
あの夜の小田切の、子供のような慟哭と悲鳴が、まだ耳に残っている。
彼は誰を憎めばよかったのだろう。法で罰せられなかった少年だろうか、それとも、成り行きで夜を過ごした相手だろうか。それとも。 。
「どうして、あさとに関わったの?」
志津子は呟いた。
少なくとも、彼は二度と瀬名の家には関わり合いになりたくなかったはずだ。
「もう……戻らないつもりなの?」
彼もまた、長い夢を見ているのだろうか。それが幸せな夢なら、起さない方がいいのだろうか。
胸がしめつけられるようになって、志津子は、元研修医の刑事から目を逸らした。
実際、風間という公務員の言う通りで、小田切は、自分の意思でこの深い眠りを継続させているのかもしれない。もう二度と、決して、幸せな夢から目覚めないように。
「小田切君……」
そんな風に思えるくらい、今の小田切は安らいで穏やかな寝顔をしている。
「静那さん、そこにいるの……?」
もう、心が行き違うことも、すれ違う不安で苦しむこともないの?
だとしたら。
だとしたら、このまま、あなたは。 。
9
帰路のタクシー中で、志津子は、小田切の妻だった女のことを思い出していた。
出会ったのはたった一度。 夫が企てた二組の夫婦の会食は、彼特有の夫婦円満のパフォーマンスであると同時に、院内でも噂になっていた若い研修医の妻への好奇心だったのだろう。
今でも、志津子は思っている。もし、あの夜の邂逅がなかったら。
もし、あの夜、三十分も早くホテルに着かなかったら。 。
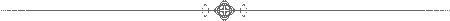
華奢な人……。壊れそうなくらい。
代官山のホテル。
最上階にある化粧室で初めてその人を見た時、志津子は、まずそう思った。
大きな化粧鏡の前で、背を向けた女性が、うなじのあたりに両手を回している。
喪服とみまがう黒のワンピース、そのせいか女の長い髪は淡いほど茶に見えた。
剥き出しになった腕は、眩しいほどに白い。スカートから覗く脚は、完璧なラインを描いて、すんなりと伸びている。
美しいのは手足だけではなかった。形良い背中、細く引き締まった腰、柔らかな丸みを帯びた腰、まるで、全てが精巧に出来た人体模型のようだ。
女は、そのままの姿勢で、手をもどかしげに動かしている。
多分、ネックレスが上手くつけられないか、外れないかのどちらかなのだろう。
不器用な人なのかも……。
ふっと、苦笑にも似た感情に誘われ、自然に足を踏み出していた。
「あの、お手伝いしましょうか」
「きゃっ、すみません」
びっくりした風に、女は志津子を振り返る。
逆に志津子も吃驚している。後ろ姿から想像しなくもなかったが、これほど綺麗な人には、滅多にお目にかかれないだろう。
潤みを帯びた大きな瞳、美しく繊細な鼻と唇、抜けるように白くて、透きとおった肌。
驚いた眼で、数度瞬きをした女は、再び志津子に背を向けた。
「恥ずかしいわ。……鎖が、髪に絡んでしまって」
息を飲んでいた志津子は、我に返って微笑する。
「お綺麗な髪ですね」
「不精なもので、ただ、切らないでいるだけなんです」
ほっそりとした白い指が、うなじの髪をかき分けてくれる。
お世辞ではなく、本当に綺麗な髪だった。艶めいて一片の癖もない、まるで上質の絹糸のようだ。
羞恥に染まった白いうなじ。細い銀の鎖が、確かに髪にからまっている。
「じゃ、いったん外しますね」
そう言って鎖に手をかけた刹那、襟が浮いた。女の背中が志津子の視界に飛び込んでくる。
なんの気なしに視線を止めた志津子は、一瞬動悸が高まるのを感じている。
見間違いでなければ、キスマーク……。それも、幾つも。
清楚な女の雰囲気には、明らかに似つかわしくない情事の痕跡。
志津子はいつものように 診療中のように、無表情でネックレスの鎖を外し、再びつけなおしてやった。
ネックレスは銀の十字架。アクセサリーにしては、いささか年季が入っている。
「ありがとうございます」
女は振り返って微笑した。子供のような幼い笑い方だった。
その笑顔を唇に刻んだまま、女は柔らかな口調で続けた。
「失礼ですけど、瀬名先生ではないでしょうか」
「え?」
「今夜、こちらでご一緒させていただくことになっている」
「……ああ」
頷きながら、内心はかなり驚いていた。そうか じゃあ、この人がもしかして。
でも、聞いていた年齢には、とても見えない。
「やっぱり……!」
寂しげな女の顔に、刹那に光が差したような気がした。
「すぐに判りました。直人が言っていたとおりの人だったから。はじめまして、私、小田切静那と申します。主人がいつもお世話になっております」
あまりに相手が嬉しそうなので、志津子も自然と笑顔になる。
「瀬名志津子です。こちらこそ小田切先生には、とてもお世話になっているんですよ」
「そうだったんですか、あなたが瀬名先生……」
いったい夫婦の間でとのような評価が為されているのか、女は、本当に嬉しそうだった。何年も別れていた友達と再会したら、こんな表情ができるのかしら、 と、志津子は内心分析している。
が、むろん、小田切の妻と自分は初対面である。
「失礼ですけど、ご年令は?」
本当に失礼だと思いながら、志津子は笑顔で返している。「今年で三十五になりますわ」
「全然そんな風には……、まだ二十代だと思いました」
真顔で驚く女を、志津子は上目使いに軽く睨んだ。
「小田切さん、精神科医にお世辞は通用しませんよ?」
「じゃ、直人より、十一も年上になるんですね」
「まぁ、それはどういう基準なのかしら?」
笑いながら、志津子は、先ほど垣間見た背中の痕のことを考えていた。
とすれば、あれは小田切君の仕業だろう。
あんな場所に痕があっては、着られる服も限られてくる。私だったら絶対に嫌だけど、この女性は平気なのかしら。お仕事は高校教師だと聞いたけれど。 。
情熱的というか、なんというか。それも若さだろうけど、さすがに目の前の人と小田切を並べて想像すると、生々しくて気恥ずかしい。
「お先に失礼しますね」
志津子は感情を隠したまま、社交的な笑顔で会釈した。
先にサニタリーから出た志津子は、待ちあわせのレストランには入らず、ロビーで静那が出てくるのを待った。
苦手なタイプかな、とは思ったが、一度顔を合わせた以上、他人行儀な振る舞いは出来ない。
化粧でも直しているのか、静那はなかなか出てこなかった。
なんの気なしに、ロビーの絵画を見て回る。
ガラスで覆われた額縁の中で、ゴヤのマハが白い裸身をしならせている。
無邪気なのに、なまめかしい まるで、先ほど見た女のようだと思った時、マハの顔に、その女の顔が重なった。
志津子は視線を止めていた。
ひどく寂しそうな顔だった。泣いた後のように悲しげで なのに、不思議な落ち着きと幸福が感じられる。初対面の女が、熱心に自分を見つめていることに、志津子は多少の気味悪さを感じながら振り返った。
「男性陣の到着がまだみたいですけど、よかったら、先にコーヒーでもいただいていましょうか」
「今日は、私までお食事に招いていただいて……」
静那は丁寧に頭を下げる。
「いいえ、主人も私も、お会いできるのをとても楽しみにしていたんですよ」
歩きだそうとすると、静那は、少し躊躇ったように志津子を見上げた。
「あの……ご相談したいことが、あるって言ったら、聞いていただけますでしょうか」
「え?」
「まだ約束の時間には、少し早いですよね」
静那はまっすぐな目で、志津子を見ていた。聖女のようにたおやかな瞳だが、激しい意思の強さを感じさせる眼差しだった。
「先生は、優秀なセラピストだとお聞きしました。先生の目から見て、小田切はどう映りますでしょうか」
「小田切、君ですか」
意表を衝かれ、志津子は咄嗟に言葉に詰まる。
「そう、ですね……。優秀な方だとは思いますけど、あまり、個人的にお話したことがないから……どうと言われましても、私にはなんとも」
「周囲とは、上手くやっておりますでしょうか」
「それは、……」
対人関係を築くのは、多少下手なほうかもしれない。多分口数が少ないのと、一人で過ごすのを好むからだ。が、問題がある行為かと言えば、そうでもない。それなりに 社会に、適応しているようには見える。
「奥さん、ご主人のことで、何か、ご心配な点でもおありですか」
答えられない質問には、質問で返すのがテクニックである。
何のための質問なのか、まずは静那の真意を聞くのが先だ。
「ええ、少し。……」
そう言うと、静那は長い睫毛を伏せて、うつむいた。
「先生。先ほど……私の背中、ごらんになりましたよね」
志津子は返す言葉を思いつけないまま黙っていた。
「自分でも不用意でした。学校ではあれほど用心していたのに。一瞬先生の手が止まったから、ああ、気がつかれたんだな、と思ったんです」
鋭い女だな、と思うと同時に、面倒だな、と内心では思っていた。
知人夫婦の悩み事を聞くのは、いつもそうだが、気が滅入る。
それでもやはり、相談を持ちかけられると、志津子はカウンセラーの顔になってしまう。
「ご夫婦の生活に、何か問題でもありますか」
「そういうんじゃないんです。だた……」
さすがに言いにくいのか、少し頬を赤らめている。相手が照れると、自然志津子も聞き難くなる。
気まずい沈黙の間、静那はうつむいて逡巡していたものの、それでも思い切ったように顔を上げた。
「独占欲、とでもいいますか、そういうのが強いんだと思うんです。私が傍にいないと不安なんでしょう。最近ますます、その傾向が強くなって……彼、私に、教師を辞めろと言うんです」
「まぁ」
驚いてみたものの、決して意外な話ではなかった。志津子の受けた印象でも、小田切には、多少の幼児性が感じられる。独占欲、支配欲、年上の女性への甘え 本人は無自覚かもしれないが、全ては幼児性の表れだと言っていい。
おそらく、幼少時の家庭環境に、なんらかの問題があったのではないか。そんな風にまで思っている。
「……正直言えば、参っています。今、教職を退くわけにはいきませんから」
では、いずれは退くつもりなのだろうか?
何か含みがありそうな気がしたが、静那はすぐに顔をあげて、悲しそうな眼差しを志津子に向けた。
「彼は、私に子供が出来れば、教師を辞めざるを得なくなると、そう思いこんでいるようなんです。だから……つまり、私の気持ちはお構いなしです。しかも、学校行事がある前日に限って、必ず私の身体に、ひどく痕をつけたがります」
「あなたは、お子さんはまだ、早いと思っていらっしゃる?」
「…………」
その刹那、静那は理解しがたい不思議な表情を浮かべたが、静かにこくりと頷いた。
「小田切はまだ若すぎます。彼には、今が大切な時期ですから……」
「そんなことはないと思いますよ。ご異存がなければ、思いきって子作りされてみるのも、いい薬だと思いますけれど」
「…………」
しばらく黙っていた静那は「まだ、……もう少しだけ……先にしたいんです」とだけ呟いた。
この人も、おそらく何かの問題を抱えている。そうは思ったが、今はそこまで深く立ち入りたくない。
「彼が、今の態度を変えないようなら、私……少しの間、離れて生活したほうがいいとさえ思っているんです」
思いのほか、深刻な事態に、志津子は内心、溜息をついた。
「別居の話は、ご主人には?」
「ええ、何度もしています」
静那は苦しそうな眼になった。
「勝手にしろと言われました。最近では、話し合いのテーブルにさえついてくれません。もう一つ恥を言えば、彼は誤解しているんです。私が、以前お世話になった人の所に、最近頻繁に出入りしているから」
「それは……どのようなご関係で?」
「児童福祉施設の方なんです。受け持ちの子のことで……どうしても、相談に乗ってほしかったものですから」
「………」
事情は判らないが、それは小田切に問題がある。が、ここにいる女性にも問題がある。
今までの結婚生活がどのようなものかは知らないけれど、少し、甘やかしすぎているのではないだろうか。
「瀬名先生、実は、無理を承知でお願いがあります。小田切の、カウンセリングをしてもらえないでしょうか」
「えっ??」
というより、過保護にもほどがある?
「ちょ、ちょっと待ってください、静那さん。それは、いくらなんでも本人の了解がないと」
「小田切は私が説得します。彼も自分の中に問題の萌芽あると、それは自覚しているんです」
静那の目は真剣だった。
「彼は、……子供の頃から実の母親を殺したいほど憎んでいます。大人になった今でも、母親への憎しみから、本質的な部分で抜け出せていません。先生、お願いです。私には何年かけてもできませんでした。先生のお力で、彼を楽にしてやっていただけないでしょうか」
「あのですねぇ……」
志津子は 本当に、困った、と思った。
10
「ふぅ……」
ため息をついて、志津子はリビングのソファに横になった。
誰もいない広すぎる家は、いつものように静まり返っている。時計の音と水槽から響く水泡の音しか聞こえない。
そんな孤独な夜にも、もうすっかり慣れてしまった。
夫は、多分帰っては来ないだろう。あさとは仕事だと信じていたけれど、もう何年も前から別宅で愛人と過ごす夜が続いている。
タクシーの中から、ずっと小田切の妻だった女のことを考え続けている。
小田切静那。
志津子が、生前のその人に会ったのは、あの夜、たった一度だけだった。
後日、彼女を見舞った衝撃的な死のせいか、わずか数時間話した相手の印象は、今でも生々しいほど鮮烈に残っている。
なのに、反面、彼女の存在そのものが幻だったのではないかと思える時がある。
あの夜の邂逅も、笑顔も、死も、全てが夢だったのではないか。 。
それくらい、六年前、志津子の前にいた人は美しく、儚かった。
まるで、この世のひとつ上のステージで生きているような。……
「美人薄命って、本当なのね」
自身の馬鹿げた妄想を振り払い、志津子は立ち上がってキッチンに向かった。
(無理を承知でお願いがあります。小田切の、カウンセリングをしてもらえないでしょうか)
「…………」
今でも志津子は後悔している。
あんな依頼さえ受けなければ、自分と小田切が深く関わることはなかった。夫の部下として、優秀なドクターとしての彼を知るだけで済んでいたはずだ。
いいえ、……そうじゃない。
冷蔵庫から出した缶ビールのフルタブを切りながら、志津子はわずかに目を眇めた。
結局、小田切はあさとと関わってしまっていた。その繋がりで、今は彼の同級生と志津子が関わっている。これはもう、どこかで繋がっていた運命のような縁かもしれない。
あれから、何度かカウンセリングを受けに来た小田切は、いつも冷めた目をしていた。
夫婦間でどのような話し合いがなされたのかは知らないが、当然、不本意だったのだろう。
小田切の態度は不遜そのもので、嫌々来ました、さっさと終わらせてくださいという雰囲気を、わざと示しているようにさえ見えた。
言ってみれば、その態度こそが、彼の持つ おそらく静那も案じていたであろう、幼児性の表れなのだ。確かに彼は、心になんらかのトラウマを抱えている。
「………」
缶ビールを一缶開けても、喉の乾きはひどくなるばかりだった。
志津子は、嘆息して立ち上がる。
他人の心の底に触れるのは辛い、そして想像以上に恐ろしい。
こちらの気持ちをしっかり持っていなければ、相手が持つ深淵に簡単に引きずり込まれてしまう。
私は……引きずり込まれてしまったのだろうか。
あの夜、なんの気なしに覗いてしまった背中の痣に。その痣を刻みつけた男の影に。
(先生は前世というか、……輪廻転生を信じておられますか?)
数時間前に聞いた風間の言葉が蘇る。
(僕だってもちろん、そんなものは信じていないです。前世が二人の接点だなんてバカな飛躍をするともりもない。ただ、前世療法でいう前世が、……今の門倉雅を反映しているのなら)
「………」
ソファの上に、置きっぱなしになっているハンドバック。
その中に、風間から預かったCDロムが入っている。管轄違いの事務員さんが、どうやって入手したのかは知らないが、当然ながら、非合法な方法だったのだろう。
てか、私の出方によっては、免職になるんじゃないかしら。
そんな皮肉を思いながらも、志津子は何度目かの重い溜息をついた。
そこに、何が記されているのかは判らない。
ただ それが小田切に関わることならば、正直に言えば、関わりあいになりたくない。触れたくない。自分の傷口をへらで抉るような怖さがある。
でも。 。
(僕は、小田切を救いたいんです。 )
志津子はソファに背を預け、目を閉じた。
小田切は、娘を救おうとしていた。何度も警告し、娘の真行琥珀への思慕を断ちきろうとしてくれた。
真行琥珀に関われば、いずれあさとが標的になると、小田切はそう思っていたのだろう。
あさとの話では、小田切は真行琥珀を疑っていたというが、それはフェイクだ。
あの時点で、彼はまだターゲットを明かせなかった。あさとの口から雅に伝わるのを恐れたのかもしれないし、彼の立場では、それは当然だったろう。
とすれば、母親だけが見抜いていた門倉雅の本質を、当時の小田切は、すでに見抜いていたことになる。……。
「………」
いずれにせよ、捜査員としての彼の立場を考えると、あさとにしてくれたことは、職務を大きく逸脱していたはずだった。
本当にお人よしね、小田切君。
瀬名家に関わりたくないのは、彼も同じだったはずなのに、それなのに。
「………」
志津子は目を開けた。
判っている。ここで逃げれば、自分の身体についた罪の烙印を消せる日は、永久にこない。
Ich kann nicht aus einem Traum herauskommen.
「私はこの夢から出られません、か。……」
門倉雅の部屋で、最後に見たあの一文が、思考の闇に滲むように浮き上がる。
あの壁には奇妙な記号が書かれていたというが、志津子が見たのは、どれも完璧なドイツ語だった。
Das Ende in der Welt
世界の果て。
漠とした不安を感じたまま、志津子はハンドバックに手を伸ばした。
|
|