|
15
手を繋いで歩きながら、小田切は驚きで眉を上げていた。
「じゃ、四月から行く高校って、男子高だったのかよ」
「あら、言ってなかったかしら」
静那の横顔はしらっとしている。
「聞いてないし、そ、そんなの、認められるかよ」
「大丈夫よ、何を心配してるのか知らないけど」
知ってるくせに……。
むっとするが、あまりしつこく言うと、勝ち誇ったように大人ぶられるので、これ以上拘らないことにした。
が、胸の中では、まだもやもや不安が渦を巻いている。
あー、知らなかったし、知りたくもなかった。俺が、こんなに嫉妬深い男だったなんて。
「私だって」
静那は顔を上げ、額にこぼれる髪をかきあげた。舞い散る桜が、髪に、肩に落ちている。
早春 山間の空気は甘い匂いに満ちていた。
「直人、本当に医大に受かっちゃうんですもの。すっごく可愛くないと思う。あれだけブランクがあったんだから、一年くらい浪人したってよかったのに」
「なっ、こ、これでも死物狂いで勉強したのに、何勝手なこと言ってんだ」
あれから、高校の編入試験を受けて、本格的に受験の準備に取り組んだ。受験まであとわずかだったから、必死になって勉強した。
もう意地を張らず、生活面は、全て静那に任せることにした。その分、絶対に今年、しかも国立に受からなければいけないとも思っていた。
本当は、六年も大学に通うこと自体、かなり気が引けている。
が、医大に行くとかつて父に誓ったのは小田切で、その約束を知っていた静那は、頑として譲らなかった。
「春になったら、当分は、離れて暮らさなきゃいけないわね」
寂しげに呟いた静那の部屋から、昨日小田切は自分の荷物を運びだしたばかりだった。
長い傾斜を登り切り、ようやく、目的の場所に着く。
小高い丘の上、そこに小田切の父の墓標があった。
「お父様が生きてらしたら、私たちのこと、どう思われるかしら」
かしずいた静那が、俯いたままで囁いた。
「さぁ……うちの親父はともかく、静那のじぃちゃんばぁちゃんは、激怒しそうな気がするけどな」
ふと、連想でもするように、小田切は葬式の時の静那の笑顔を思い出していた。
理由を聞こうとも思ったが、無神経な問いのような気がして、やめた。
それに、もしかしたら、そう思えたのは気のせいだったのかもしれない。二人で再び一緒に暮らし出してからの静那は、本当によく笑う。心の底から、憂いなど何一つないように。
「直人のお父様には、生きていて欲しかった……。もっと、いろんなことをお話してみたかったわ」
やがて静かに立ち上がり、静那はスカートの砂を払った。そして、物言いたげな目で小田切を見上げる。
「怒らないで聞いてくれる?」
「まぁ……努力は、する」
「お父様ね、口癖のように言ってらしたのよ。俺は悪いことをした、あいつから直人を奪ってしまった」
「…………」
あいつ。 もしかしなくても、母親のことか。
強張った感情が顔に出てしまったのだろう。静那がそっと寄り添ってきた。
「あなたのお父様は、本当に立派な人よ。お父様は判っていらしたのよ、本当に心が豊かな人生が、どんなものなのか」
「…………」
「直人は怒るかもしれない。でも……私は、彼は沢山の幸福を抱いて亡くなられたんじゃないかと思っているの。だって、何より愛しい、あなたが傍にいたんですもの」
直人、忘れるなよ。神様ってのは、本当にいるんだ……
まだ、父の言葉は、小田切の中に、本当の意味では響いてこない。
静那が背負った過去も含め、世の中は、理不尽な事件で溢れている。
が、脂っこい化粧を塗りたくった顔で振り返った母より、病床で、静かに微笑している父のほうが、遥かに幸福だと思えたのも、確かだった。
「だから、笑ってたのか」
「え?」
つい口にしてしまっていた。訝しく見上げられて、うろたえたが、口火を切った以上後には引けない。
「いや、静那は普段笑わないのに、親父と祖母ちゃんの葬式の日に、なんかこう、妙にすがすがしい目で笑ってたような気がしたからさ」
「…………」
静那は不思議そうな眼で瞬きを繰り返す。
「いや、俺の気のせいだったら悪いんだけど」
「ううん……、自分でも気づかない自分のこと……人が知ってるって、すごく不思議な気がしたから」
「ごめん、へんなこと言ったな」
そっと手を取る。静那は微笑し、小田切の胸に額を寄せた。
「私……笑っていたのね。……そう、……でもそれは、きっと私ではないわ」
「え?」
「私の中の……私……。私が辛い時、いつも私を助けてくれた私……。でも、もう消えてしまったみたい」
「…………」
「あの日、直人が救ってくれた。もう、怖い夢は二度とみないわ」
意味は、よく判らない。
それでも、静那の中で、過去の悪夢がひとつの終結を迎えたのなら、それでいいのだと小田切は思った。
静那……。
俺が、絶対に幸せにしてやる。
何があっても、お前を二度と離さない。
手を握る強さに閉口したのか、静那は微笑して小田切を見上げる。
「いつか、人は必ずこの世界からいなくなるわ。……直人も、私も……そこに、例外なんてひとつもない」
何故今、そんな寂しい話をするのだろう。
訝しむ小田切の胸に、静那はそっと額を寄せた。
「直人、……終わることは悲しいことではないの。悲しいのは、終わるかもしれないと畏れること」
「………」
「いつか……直人にも判るわ。判ってくれたらいいと思うわ」
不思議な気持ちのまま、小田切は、顔を上げた静那の額に唇を当てた。
現実に、俺たちは生きている。まだ 長い人生が待っている。
どうして今、そんなことを言うのだろう。
「好きだよ」
「ん……」
「……愛してる」
髪に、瞼に口づける。肩がわずかに震えている。それが愛おしくて、もう一度額にキスをした。
薄く眼を開いた静那が微笑する。そして 。
「えっっ」
なに? 今の?
ぎょっとした小田切は首を押さえて後ずさる。
噛まれた?
もしかして、今噛まれた?
「吃驚した? いつも私ばかりドキドキさせられるから、少しはお返ししようと思って」
「………。………。 」
「顔、真っ赤になってるよ」
なってねーっつーか、……マジ、やられた。
首を軽く噛まれただけなのに、心臓が爆発しそうになっている。
「愛してる……直人……」
そっと、唇が寄せられる。
「静那……」
俺も 俺のほうが、どれだけ愛しているか、判らない。
溶けるほど幸福なキスを交わし、静那を強く抱きしめながら、初めて小田切は、不思議な不安を感じていた。
なんだろう、俺は この先の続きを知っている?
これから、……これから先、俺たち二人は。
「直人……」
耳元で、静那が夢でも見ているように囁いた。
「この時間が……永遠に、続けばいいのにね」
瞳を開けた途端、冷たい滴が頬に伝った。
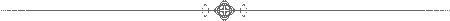
信じられないほど幸せで、苦しいほど切ない記憶。
これが夢なら、現実ではないのなら。
もう二度と、俺はこんな夢を見たくはない。 。
|
|