|
また……。
あの夢を見た。
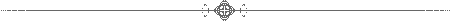
|
第五章 過ぎし日
高い空に、筋を引く灰色の煙が吸い込まれていく。
二度目だな、と空を見上げながら直人は思った。
こんな光景を見るのは、これで二度目だ。
「いっちゃったわね」
隣の人が囁いた。
見上げたその人の横顔は、空を仰いで微笑していた。
憂いのないすっきりとした笑顔を見るのも、これで二度目だと直人は思った。
「直君、人はね、みーんなああやって空に還っていくの」
五年前と同じ台詞を、彼女は言った。
「だから、寂しいことなんて何もないの。これからは、なんの悲しみも不安もない世界で、永遠に幸せに暮らしていけるんですもの」
滅多に笑顔を見せない人が、本当に幸福そうに笑っているのが不思議だった。
今日は、その人のたった一人の身内の葬儀なのだ。
「ばあちゃん、死んだんだろ」
直人は、ふてくされたように言っていた。
「もう戻ってこない。静那、俺たち二人になっちゃったんだぜ」
「二人じゃないわ」
静那は笑った。
どんな時でも、直人はこの七歳年上の人の笑顔を見るのは好きだった。
しゃがみ込んだ静那は、直人の手を握って微笑んだ。
絵本で見た、聖母のような眼差しで。
「神様はね、いつも私たちの傍にいらっしゃるのよ……」
眩しいほど白い喉には小さな十字架が輝いている。
1
「本当に、申し訳ありませんでした」
長い髪が、頭を下げるたびにさらさらと揺れる。
「この子のことは、全て私の責任です。後で、よく言って聞かせますので、今回ばかりはお許しください」
あんたには、関係ねーじゃん。
小田切直人は冷めた目で、隣に立つ冬木静那の横顔を見つめた。
「直人」
そっと振り替える白い面差し。濡れたような優しい目が、下から沁み入るように見上げている。
「あなたも、ちゃんと謝りなさい」
「…………」
「直人」
冷たい指が手に触れる。
「っせーな」
一瞬驚いたように息を詰めた小田切は、次の瞬間、邪険にその手を払いのけた。
人の気持ちも知らないで、勝手に俺にさわんな。
「小田切、お前な、この人がどれだけ心配なされたか、少しは考えてみたらどうだ」
ため息混じりに口を挟んだのは、対面に座っている学年主任の鍋島教諭だった。
生徒指導室。
狭い室内には、今、三人の大人と生徒が一人、立っている。
が、十七歳の生徒が、四人の中では一番図体が大きかった。180センチ近い長身に、骨格に秀でた身体。二人の男性教諭が、生徒を見上げる格好になっている。
「冬木先生、まぁ、そんなわけですよ。見ての通り……反省の色もないですからね」
鍋島が嘆息しながら腕を組んだ。
冬木先生。――隣町の私立高校で数学教師をしている静那は、だまったまま、うなだれている。
「相手の親御さんも、賠償うんぬんまで話を持っていく気はないみたいですから、まぁ、きちんと謝罪すれば、判ってもらえるとは思うんですけどね」
「しかしですね、これはもう、れっきとした犯罪ですよ!」
声を荒げて口を挟んだのは、クラス担任の春日だった。
「女生徒の部屋に忍び込んで、無理やり行為に及んでですね、挙句、止めに入った父親を殴りつけて逃げ出したんですから!」
「まぁ、無理とは……言い難いんじゃないんですかね、春日さん」
真鍋が咳ばらいをする。静那のようなうら若い女性の前で、するような話ではないと思ったのかもしれない。
「成田美菜が、そのぅ……小田切を追いかけ回していたことは、うちのクラスの女子でも知ってるくらい、有名な話だったんですから」
小田切は黙っていた。
隣の静那も黙っている。彼女が今、怒っているのは悲しんでいるのか――静かな横顔からは、何の感情も読みとれない。
「しかし、あれですよ。そもそも冬木さんみたいな若いお嬢さんに、こんな不良生徒の後見なんて、土台無理だったんじゃないですか?」
粘っこい目で静那を見ながら、春日が皮肉な口調で言った。
「こういう言い方はあれですがね、冬木さんの学校でも、何かと噂になっていると聞きましたよ。そりゃあそうでしょうが、こんなケダモノみたいな高校生と、あんた、二十歳過ぎたばかりの娘さんが一緒に暮らしているなんて、しかも」
うっと、そこで春日が喉を鳴らしたのは、小田切が睨んだからだ。
が、性格は臆病な小動物のくせに、やたら生徒にいばりちらす男は、途端に顔を赤くして怒りだす。
「貴様、なんだぁ? その反抗的な目は!」
掴みかからんばかりの勢いで、春日のあばた面が迫ってくる。
「ちょっとばかり頭がいいと思って、なめんじゃねぇぞ! お前なんざな、停学どころか退学にしてやることだってできるんだからな!」
「春日先生、どうか」
静那の柔らかい声が、中年教師の激昂を遮った。
「この度のことは、どうか私におまかせいただけないでしょうか」
「冬木さんねぇ」
自分より立場が弱い者にはとことん強くでる男は、あからさまな侮蔑を浮かべて静那をねめつけた。
「さっきも言いましたけど、小田切みたいなどうしようもない生徒は、あんたみたいな若い娘さんの手には負えないんですよ。授業はさぼる、教師には反抗的、他校の生徒とはトラブルを起こす、こいつ、家に帰ってますか? 澁谷あたりで商売女のマンションにいりびたってるって噂もあるくらいですよ?」
静那は無言で、小さく相槌を打ちながら、春日のヒステリーを引き受けている。
「あなたは熱心に小田切の保護者でいようとしてらっしゃるみたいですが、こいつはそんな恩義、これっぽっちも感じちゃいませんよ。聞けば、知人の子供を預かって面倒みておられるとか。ご立派な志ですがね。今回被害を受けた女子高生みたいになる前に、とっとと親元に叩き返した方がいいんじゃないですか」
春日の金壺眼に、確かにその刹那卑猥なものが宿っている。かっとした小田切は足を踏み出しかけたが、その前に静那の背が割って入った。
「確かに世間的には、他人なのでしょうが、私と直人には、神の意思によって結ばれた縁があるのです。私たちの繋がりが純粋な人類愛であることは、神様だけがご存じですわ」
ご大層な台詞を述べ、そっと手を合わせる静那を、真鍋と春日は、宇宙人でも見るような眼で見つめている。
敬謙なクリスチャンである彼女は、こんな時、他人に何を言われても動じない強さがあった。
潤んだ聖母にも似た目で、静那は天を仰ぎ、宣言した。
「私を信じてください。きっと直人には、心から反省させるとお約束いたします。天におわします、父と子と精霊の御名にかけて。……」
2
「悪いけど、俺、もう行くよ。バイトが入ってるんだ」
指導室を出た直後、静那が何か言いかける前に、小田切は先制して口を封じていた。
「夜は友達が泊まりに来るし、明日も朝早いから」
「……忙しいのね」
静かな目色で、静那は答える。
抑揚のない口調は、怒っているようには思えなかった。むろん、皮肉をいう風でもない。
「アルバイトも社会勉強のためには必要だけど、ほどほどにしないと、受験の時に苦しくなるわよ」
「…………」
「直人は頭がいいから、信頼しているけれど」
見上げる瞳に柔らかい笑みが滲んでいる。静那が怒らないどころか、本当の意味で心配さえしていないことを察し、小田切は内心、軽い嘆息を漏らしていた。
「春日の言うとおり、俺、全然反省してねぇし、これからもするつもりはないから」
「判っているわ」
にっこりと笑う。「あの方たちがあまりに御怒りでいらっしゃるから、ああいう言い方をしたけれど、私が直人をこの件で叱ったり、問い質すことは何もないわ」
「…………」
「あなたの罪も、罰も、全ては神様がご存じでいらっしゃることだから」
また神様かよ、小田切は腹立たしさを感じ、眉をしかめた。
そういうのは、責任放棄っていうんだ、よくこんなのが教師なんてやってられんな?
もし神様が本当にいるなら、世の中に溢れている犯罪者はどうなるんだ、全員、相応の罰を受けるようになってんのか。
反抗的に振り返ったものの、真っ直ぐな静那の目を見て、逆にそらしてしまっている。
「直人」
静那の声は優しかった。
「疲れたらいつでも帰ってきなさい。私のほうが、最近は仕事が忙しくて夜遅いの。いつも家が留守だとかえって物騒だわ」
「だったら、あいつに来てもらえばいいじゃないか」
「樋口さん?」
あっさりと静那は答えた。「彼も最近は忙しいのよ」
わずかも動じていない眼差しに、むしろ苛立ちをかきたてられて、小田切はものも言わずに背を向けた。
「おい、小田切!」
声がしたのはその時だった。階段を駆け上がってきた長身の男が、血相を変えて駆け寄ってくる。
クラスメイトの風間である。風間は静那を見ると、ややひるんだように足を止め、それでも最初の勢いのままに、小田切にくってかかった。
「さっき永田に聞いたけど、お前、とんでもないことに巻き込まれてるんだって?」
「そんな、騒ぐことでもないよ」
「でもお前、話聞いたけど、ありえねーだろ!」
クラスで唯一小田切を見下ろすほど背が高く、引退するまではバスケ部のエースだった男 風間潤。
父親は警察官僚、厳しく育てられたせいか、まさに絵に描いたような優等生だが、不思議と小田切とは気があった。同じ目線で話せる、唯一の相手だからかもしれない。
「で、お前、ちゃんと違うって言ったんだろうな。言い訳のひとつもしたんだろうな」
「だって、向こうが俺って言ってんだし、否定しようがないだろ」
「あのなぁ……」
「じゃ、私はこれで」
背後で、静かな声がした。進み出た静那が、風間を見上げて微笑する。
「風間さん……いつも直人がお世話になっている方ね」
「あ、いえ、俺は別に」
「ありがとう。これからも直人の友達でいてやってね」
静那みたいな美人に見つめられたら、誰だってドキマギするだろう。実際、静那が去った後、顔を赤くした風間に「お前の姉ぇちゃん、相変わらず美人だな」と、照れたように囁かれた。
「姉貴じゃないよ」
「知ってるけどさ、……静那さんの学校では、一応それで通してるんだろ?」
「…………」
黙って歩き出すと、風間が後を追ってきた。
「小田切の七不思議、あんな美人と一緒に暮らしてて、マジでむらっときたりしねぇ?」
「しねぇよ。熱心なキリスト教徒でさ、何かあれば聖書は……マタイは……そんなのばっか。それに、今は一緒に住んでるわけじゃないんだ」
「にしても、不思議な関係だよな、静那さんとお前って」
何も知らない他人から見たら、確かにその通りだろう。姉弟でもない、親子でもない。親戚ですらない。全くの赤の他人同士が、何年も二人きりで暮らしてきたのだ。 。
「結婚すんだ」
屋上 。手すりにもたれ、小田切は素っ気なく口にした。
丁度、赤い車が、校門を出ていくところだった。前もその車を、小田切は何度か見たことがある。
なにが忙しいんだか。
眼鏡面の厭味な顔を思い出し、小田切は眉をしかめている。
「結婚? 静那さんが?」
「ああ、地味ーな公務員。俺も親父って呼ぶ気はないけど、向こうもそんな気、さらさらないみたいだぜ」
(そろそろ、考えてもらえないだろうか)
(君が傍にいると、静那は自分の幸福を追うことができない。君も、判っているはずだと思うけどね)
フェンスに背を預けて、読みかけの文庫本をポケットから取りだす。
空は、染み入るように青かった。
「にしてもさ、やっぱ、やべーよ」
立ったままの風間は、まだ不安そうだった。
「丁度推薦決まる時期だし、小田切、お前S大医学部、狙ってたんじゃなかったのかよ」
「いいよ、もともと推薦なんか頼る気ねぇし」
「まぁ……そりゃ、お前は、頭がいいから」
歯切れの悪い口調で呟き、風間は憂鬱気な溜息をついた。
「にしても、あんま甘く考えんなよ。春日はお前が嫌いなんだ。もしかすると、マジで退学まで話もってくかもしんねーぞ」
「まさか」
「授業はまともに聞いてないのに、成績はいつも十位以内。今だって……何読んでんだよ」
「フォイエルバッハに関するテーゼ」
「知らねぇよ! つか、あの肉体バカが死んだって読めねえシロモンだよ! しかも、女子連中にはもてもてときてる。そんな厭味な男はな、小田切、同性にとことん嫉妬されるようにできてんだよ」
「なんだよ、お前も嫉妬してんのか」
風間は、はぁっと、溜息を吐いた。
「これ以上問題起こすなよ。まさかが、まさかじゃなくなっちまうぞ」
「………」
大学に行く気はない。地味な公務員に言われるまでもなく、これ以上、静那の世話になるつもりはない。
退学か、小田切は空を見上げた。いっそ、その方がいいかもしれない。
静那が、完全に誰かのものになる前に、この町を出ていきたいから。 。
|
|