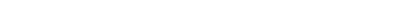 |
10
高らかに鳴り響く教会の鐘が、澄みきった空に吸い込まれていく。
抜けるような晴天の青空だった。
「クシュリナ様、お顔が」
隣のカヤノに指摘され、クシュリナは、顔を覆う黒のヴェールを指で直した。
シーニュの森の奥深く。
ここはもう、法王領だった。クシュリナには初めての領域である。
七つの折、シーニュの森には足を踏み入れたことがあるが、その先にまで進んだのは初めてだ。
長く乗っていた馬車を降りると、周囲はすでに鬱蒼とした木々に包まれていた。目の前には壮麗な建物がそびえている。
白い壁に、円形に装飾された美しい屋根。頂上には三角の旗が二枚揺れている。文様は、上が黒地に白十字、下が黄地に天秤。上が法王旗なのは判るが、下の旗の意味は判らない。
建物の周囲は、牢を思わせるほど厳重な塀で覆われており、至る所に、黒服の修道士たちの姿が見える。
カタリナ修道院。
近衛騎士が、婚礼の式を挙げる場所 。
よく 許されたものだと思うし、ある意味父の冷酷な罰なのではないかとも思う。
むろん、クシュリナの傍には、カヤノがぴったりとくっついているし、背後の馬車には十数人の騎士が同行している。
身分を隠したクシュリナは、カヤノと同じ金羽宮の女官服を身につけ、顔を覆うためのヴェールを被っていた。
「姫様、こちらでございます」
カヤノが先導してくれる。
クシュリナは頑強な門をくぐると、最初に見えた建物の脇を抜け、庭に作られた通用路を通って、さらに奥にある礼拝堂にも似た建物に通された。
すでに、その儀式は始まっていた。
はっと吐胸を衝かれたように視線を下げたクシュリナだったが、必死の思いで、強張った首をあげる。
私は、今日のこの日を、自分の眼に焼きつけるために来たのだ。もう、二度と過去を振り返らないために。 。
大きな十字の下、宣誓しているのは立会人だろう。見覚えがある というより、一度見たら忘れられない。近衛隊の隊長、加賀美ジュール。
がらんとした聖堂の内部。ジュールの他は、数人の修道士らしき者が見えるばかりで、列席者は殆んどいないようだった。
なんて、寂しい……。
その殺風景さに、クシュリナは初めて、悲しさや辛さとは別の感情に囚われていた。
以前、ダーラもラッセルも孤児だという話を聞いたことがある。とすれば、二人には、最初から結婚を祝福してくれる家族などいないのかもしれない。……
ただ、それでもラッセルには妹がいるはずだった。血が繋がっているかどうかは定かではないが、妹のことを語る時のラッセルの優しい眼が、肉親と同じ情愛を示していたことをクシュリナはよく覚えている。
が、ひっそりとした教会の中、親族らしき人の姿はどこにもないように見えた。
礼服姿も凛々しい加賀美ジュールが、うつむくダーラに声をかけている。
純白の衣装に身を包んだダーラは、ジュールの言葉に涙ぐんでいるように見えた。
やがておごそかな聖歌が、両脇に陣取る近衛隊士の口から流れだし、ダーラとラッセルは、二人で並び立って壇上に歩み出た。
耐えきれず、クシュリナは、うつむいて目を閉じた。
握りしめた手が、膝の上で震えている。
馬鹿な私、見たくないのなら、来なければいいだけのに。
それでも、来ずにはいられなかった。この現実を自分の目に焼きつけなければ、とうてい別の男との結婚など、受け入れられないと思ったからだ。
聖歌が終わる。
クシュリナは、苦しい動悸を堪えて顔を上げた。
丁度壇上の二人が、向き合うところだった。
ラッセルは、近衛隊員が式典の時に着用する金刺繍入りの黒の膝丈コートと、折り返しつきの長いブーツを履いていた。
少しウエーブを描く黒髪が、柔らかく額に零れている。
こんな時ですら、クシュリナは彼の横顔や真直ぐな立ち姿に、思わず見惚れてしまっていた。
ラッセル。 。
馬鹿げた未練だと知りつつ、この瞬間、奇蹟のような何かが起きて、全てが 全てが壊れてしまえばいいのに、とクシュリナは思っている。
彼の隣にいる花嫁は、綺麗な横顔を彼に向け、いつもは気丈な瞳を涙で潤ませていた。
すらりと伸びた背丈に、細身の白いシルクドレスがよく映えている。長身の二人が並んで立つと、まるで、絵本の挿絵のように美しい。
ダーラで、よかったんだ。
クシュリナは、懸命に自分に言い聞かせた。
他の誰でも許せなかった。ある意味ダーラだから、諦めもついた。
あんな素敵な女性が、ラッセルのお嫁さんになるんだもの。……本当に、これでよかったんだ。
壇上の二人は互いに向き合い、ラッセルがかがみ込むようにして、花嫁のヴェールを両手で払う。ヴェールの白さに負けないほど鮮やかな白い手袋が眩しかった。
わずかに身をかがめて顔を傾ける。
奇蹟は起きなかった。クシュリナは目を閉じていた。
11
「少しだけ、ここで待っていてくれる?」
外に出ると、クシュリナは背後のカヤノに声をかけた。
「ラッセルに……お祝いを言いたいの。すぐに戻るわ」
「私も参ります」
即座に無表情の女騎士が眉を上げる。
「いえ、一人で大丈夫よ。本当にすぐに戻るから」
クシュリナは、自身の胸元を強く抑えた。
もうひとつ ラッセルにどうしても会いたい理由がクシュリナにはあった。
サランナから預かった例の薬の件である。
ルシエには、今後連絡を取ることが難しくなる旨の手紙を急ぎしたためたが、もう自分にはあまり時間が残されていない。アシュラルと結婚すれば、そう遠くない時期に即位式が待っているだろう。そうなってしまえば、今以上に自由に動くことができなくなる。
「クシュリナ様」
明らかに反対の気色を見せたカヤノは、初めてその眼に、はっきりとした嫌悪をのぞかせて、クシュリナの前に立ちふさがった。
「ご存知かと思いますが、ラッセルはもう、クシュリナ様の騎士ではございません。それはダーラも同じこと」
「……判っているわ」
初めて意見されたことに戸惑いながら、クシュリナは答える。
「青百合宮殿にお仕えしている間、ラッセルもダーラも、常に命の危険にさらされていたのでございます。この上二人に、厄介事を」
そこで言葉が過ぎたことに気付いたのか、カヤノは可愛らしい顔を歪めて軽く舌打ちした。
「……二人をもう、自由にしてやってくださいませ!」
冷たい口調で鋭く言い放つと、カヤノはぷいっと背を向け、元来た道に向かって歩き出した。
二人を……自由に……?
初めてカヤノが見せた自分への嫌悪と反発、そして思いもよらない言葉に、クシュリナは動揺しながら、歩き始める。
命の危険……あの平穏な青百合オルドで……?
が、カヤノの言葉が決して大げさではないことは、すぐに想像がついた。クシュリナの死を願うものは義母アデラをはじめ、沢山いる。父は、アシュラルが旅先で襲われ続けたと言っていた。それと同じ刺客が、クシュリナ自身を襲わないと、どうして言い切れるだろう。
この薬が、もしマリスの蛇薬だったら。
胸に抱いたものの重さに、初めてクシュリナはぞっとしていた。
ラッセルはどうするだろう。そしてダーラは。
ダーラはともかく、ラッセルであれば、それがどのような危険をはらんだ任務であっても、やり遂げようとするだろう。ヴェルツ邸に同じものがあるかどうか、命がけで確かめに行くかもしれない。
そんな危険な真似を、本当にラッセルにさせてしまっていいのだろうか。
その時、扉が激しく開く音がした。
はっとクシュリナは足を止める。
目前に見える教会の裏口。飛び出してきたのはダーラだった。まだ結婚式の衣装を身につけたまま、ヴェールを手に握りしめている。
明らかに様子がおかしかった。顔は強張り、うつむいて小走りに駆けてくる。
「ダーラ」
彼女の背後から、ラッセルが現れた。駆け寄ったラッセルは、逃げようとするダーラの腕をしっかりと掴む。
「離して」
ダーラは身をよじり、抗った。その華奢な身体を、ラッセルは背後から抱き止める。
骨格の秀でたラッセルの身体の中に、ほっそりとしたダーラが飲みこまれたように見えた。
何……?
クシュリナはざわめくような胸騒ぎを感じた。これは、多分、見てはいけない光景だ。なのに足が、すくんだように動かない。
「お願い、離して」
囁くようにそう言って、顔を背けたダーラの眼がクシュリナの視界に飛び込んできた。
ダーラは明らかに泣いている人の顔をしている。
ラッセルは無言だった。
クシュリナの位置からは、彼のうつむいた横顔しか見えない。
心臓が嫌な感じに高鳴っている。早くここを立ち去らないと ラッセルが、そしてダーラが顔を上げただけで気づかれてしまう。
「どうして、こんな突然の結婚を承知したの!」
ダーラの、高い声がした。
「それが公の命令だから? 私の気持ちはどうなるの? ひどいわ、ラッセル、このままじゃ惨めになるだけよ」
あの冷静なダーラが、ここまで取り乱している。
「だって、私は、あの」
ラッセルが顔を上げた。
あ、
どこか厳しい眼差しが、クシュリナの眼を確かに捕えたような気がした。
その瞬間、ダーラの言葉が途切れた。
ラッセルが唇を塞いだのだと 二人が唇を重ねているのだと それがすぐに理解できなかった。
いや。……
目を閉じてしまいたかった。なのに凍りついたように、瞬きひとつ出来なかった。
ダーラを抱きしめ、情熱的な口づけを続けるラッセルの横顔。それは今まで見たどの彼の顔とも違っていた。
抗って顔を背けるダーラの顎を強引に掴み、また唇を寄せる。
「ラッセル……」
ダーラは切な気に囁き、細い腕が耐えかねたようにラッセルの背中を抱いた。
長い口づけが、ようやく終わった。
「……俺を信じてくれ」
こんな声。
「子供の頃からお前を大切に思ってきた、それだけは本当だ」
初めて、聞いた。
クシュリナは、二人から背を向けた。目蓋の奥が痛いほど熱かった。胸が苦しくて息苦しいほどだった。
走って果樹園まで出た時、クシュリナは改めて思い知らされていた。
自分に向けられるラッセルの眼差しも、優しさも、それは彼の全てではない。生身の男としての彼は、クシュリナの前では絶対に出てこない。
職務として、そう、忠実な騎士として、ただ 仕えているだけ。恋愛とは全く別の次元で。
私は……。
涙が、ぽたぽたと膝に落ちた。
わかっていたはずなのに、最初から知っていたはずなのに……なのに……なのに、何を期待していたんだろう。
風が冷たかった。クシュリナは顔を隠していたヴェールを脱いだ。
零れた髪を、風がさらっては巻き上げる。
今、ようやく実感していた。初めての恋を、永遠に失ってしまったことに。
でも、私は。 。
せりあげる呼吸を整えながら、クシュリナは涙を払って唇を噛みしめた。
やっぱり彼に、恋している。
今の気持ちを、どうしても忘れることなんてできない。だってあれほど、私のことを大切に守ってくれた、支えてくれた、その真実だけは忘れたくない。忘れられない……。
「姫様……」
背後で静かな足音がした。
ラッセルの声だと、不思議なほど静かな気持ちで思い、クシュリナは目にたまった最後の涙を急いで払った。
「オルドの者に聞いて驚きました。……私ごときの私用に、わざわざおいで頂くとは」
冷静な声だった。
「ご結婚を控え、姫様は大切なお身体でございます。参りましょう、馬車までお送りいたします」
丁寧な口調。振り返らなくても判る。きっと膝をつき、折り目正しく頭を下げている。
ラッセル……。
クシュリナは、激しく込み上げる感情を胸の裡で押し殺した。
「そんな真似をしないで、ラッセル。今日は、あなたにお祝いを言いにきたのに」
振り返る。上手く笑えているのか不安だった。
「………」
綺麗に澄んだ静かな目が、クシュリナを見上げている。
この真っ直ぐな眼に、ずっと惹かれ続けてきた。
「これからは、ダーラを守ると私に誓って」
でも、今日で、終わりにする。
もう二度と、彼を振り返ったりしない。
「身命をかけて、彼女を守ると私に誓って。……一生よ」
この恋は、生涯私の中に封じ込めておくから。 。
ラッセルは答えない。わずかに視線だけを下げている。
「私の最後の命令よ。今日で、あの夜の約束は終わりにします。今までありがとう、……ラッセル」
本当に。
ありがとう。 。
しばらくそのままの姿勢で、ラッセルは微動だにしなかった。まっすぐな眼差しは、こんな時でも変わらずに やはり、まっすぐなままだった。
「先日の早駆けの折り」
膝をついたままで、ラッセルは言った。
「私は申し上げました。私たちはイヌルダの民、このシュミラクール界の安寧を保つ、義務があると」
クシュリナは無言で、彼の綺麗な唇を見つめている。
「美しい宮殿も、装飾品も、数々の財宝も、食べきれないほどの贅沢な食事も、すべてその義務と引き換えに手にしているのでございます」
そこまで言って、ラッセルは少し逡巡するように目を伏せた。
「もっと、姫様とは色々なお話をするべきでした。……私が口べたなゆえ、真意が伝わらないことも多うございました」
ラッセルは深く頭を下げた。
「高貴なる者の義務をお忘れになりませんよう。……私が申し上げられるのは、それだけでございます」
「わかったわ、ラッセル」
涙が、
「それを、あなたとの新しい約束にする……」
涙が出る前に、行って。
お願いだから、もうそんな目で、私を見ないで 。
|
|