第四章 アシュラルとラッセル
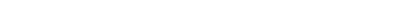
その人を見た時、クシュリナは不思議な胸騒ぎを覚えた。
1
その夜、金羽宮では定例の舞踏会が催されていた。
先日、十歳の誕生日を迎えたばかりのクシュリナにとっては、その夜が初めての社交界お披露目であった。
ずっと青百合宮殿の中で、外から遮断されるように育てられたクシュリナには、金羽宮本殿も初めてだし、舞踏会という場そのものも初めてである。
眼を射るほど豪華な装飾と、広間中に溢れかえる花々の濃い匂い。きらびやかなドレスと人の渦に圧倒され、食事はおろか、水一滴さえ喉を通らない。
客人が挨拶に寄る度に、笑顔で定例の言葉を返すだけの繰り返しに、クシュリナはやがて疲れ、助けを求めるように隣に座るハシェミを見上げた。
「私……このような場所は、苦手かもしれません」
「そのような気持は、決して表に出してはいけないよ」
ハシェミは、優しい口調の中にも氷のような厳しさをこめて、娘を見下ろした。
「よく覚えておきなさい。クシュリナ。今宵からお前はもう、イヌルダの第一皇女、次期皇位継承者なのだ。皆がお前をそのような眼で見るだろう。お前はどれだけ苦しくとも、その期待を裏切ってはならぬ存在なのだと知りなさい」
そこで、ハシェミはわずかに目をすがめた。
「皇位を巡る戦いはもう始まっている。……それも、決して忘れてはいけないよ」
「…………」
クシュリナの隣には、ハシェミが、あたかも娘を守護するかのように寄り添い、それまで数度謁見したことのある母アデラは、自身のサロンに収まったまま、夫や義娘と眼も合わせようとしなかった。
その理由を、おぼろげながらクシュリナはもう知っている。
義母にはクシュリナより一つ年下のサランナという娘がいて、そのサランナに、次期皇位を譲りたいと望んでいるのだ。
金羽宮の主ともいえるアデラとハシェミの不仲は、当然、広間に不穏な空気をもたらしている。
「ほら、あの方が、先代の女皇陛下の忘れ形見、クシュリナ様ですわよ」
「亡くなられた陛下と瓜二つでございますわ。……まるで、子供の頃のあの方を見ているような」
自分に注がれるざわめきと眼差しに、若干の躊躇いと遠慮があることに、クシュリナはすぐに気がついた。
自身の容貌が死んだ実母譲りなのはよく知っている。だからこそハシェミはクシュリナを溺愛し、継母は逆に憎むのだろう。
広間に集まった貴族たちは、そういった内々の事情すら熟知しているのか、先代女皇と生き写しの姫への態度を決めかねているようにも見えた。
眠い……。
クシュリナは、父から顔をそむけて眼をこすった。
いったい今、何時だろう。窓から見える庭園はもうとっぷりと暮れている。オルドの暮らしでは、夜は早々に床につき、朝は日が登る前に起床する。こんな時間まで起きていたのは初めてだ……。
眠気を追いやるために顔をあげた時、広間の中央、颯爽と歩いている長身の男性が目に入った。
吸い寄せられるように、クシュリナはその人の姿を追っている。
誰だろう。
綺麗な人……。
確かにその人は、際立って目立つ、美しい容姿をしていた。すでに広間の婦人たちの視線も、その男性に釘付けになっている。
レースで縁取りしたローン地のストックに、揃いの袖口。金のブレードで縁取りしたベルベットのコート。膝の位置でボタンを留めた紺藍のブリーチ。
衣装だけではない。鋭さを帯びた肩までの黒髪は、まるで、漆黒を思わせるほどの見事な艶めきを擁している。
凛々しい眉、赤味を帯びた唇。まるで、童話か、神話から抜け出した王子様のようだ。
骨格の秀でた体格だけは、大人だった。けれど、その顔はまだどこか幼く、少年のようにも見える。
何より印象的なのは、その眼差しの鋭さだった。
形の良い、切れ長の瞳。その奥には暗い炎を燃やしているような、不思議な輝きがある。
その彼の眼が、自分を捕らえていると気がついた時、言い知れない不安を感じ、クシュリナは視線を下げていた。
なんだろう、怖い。
「あの方は……」
隣にいたハシェミを見上げる。「どちらの方ですの」
なんだろう、あんなにも美しい人なのに。 怖い。
「ほう、ようやく来たか」
ハシェミは、クシュリナがそう言い出すのを待っていたかのように、目元に嬉しそうな笑みを浮かべた。
「アシュラル、こちらへ」
ハシェミは立ちあがり、その青年に声をかけた。
アシュラル?
聞き間違いだろうか。この二年、一度も忘れたことのない名前である。
まさか、あの時、倒れていた人 ?
はっと顔を上げた時、青年は、すでにクシュリナの前に立っていた。
間近で見る彼は、驚くほど端整な顔立ちをしている。
均整のとれた眉、切れ長で黒目がちな目、まっすぐな鼻筋、綺麗な形を描く唇。
決して美少年、という顔立ちではない。どこか荒削りな、 そう、彼が成長したあかつきには一体どのような凛々しい男になるかという、期待にも似た未完成の魅力。
「はじめまして、クシュリナ様」
アシュラルは立ったままの姿勢で、わずかばかりの低頭をした。
クシュリナは内心驚いていた。今宵、自分の前で膝をつかなかった者は、この青年が初めてだ。
「聖将院、コンスタンティノ・アシュラルにございます」
アシュラル。……
クシュリナは、ただ、息を飲んでいた。
霧に閉ざされた森。幻のような大樹の下。夢とも現実ともつかない世界。
あの時の 顔を忘れてしまった「彼」。
「彼」のその顔に、今、目の前にいる青年の顔が重なっていく。
クシュリナは大きく瞳を見開いて、冷たささえ漂うほどの美貌を持つ痩身の男を見つめ続けた。
あなたが、あの時の?
確かにあの時の「彼」も、まるでおとぎ話の王子のように美しかった。
今でも、その印象だけは鮮烈に残っている。あれから二年、目の前の人の容貌から推測しても、やはりこの人が、夢の中の「彼」に間違いないような気がする。
「彼は法王コンスタンティノ大僧正のご子息で、このたび枢機卿におなりになられた。年は若いが、子供の頃からコンスタンティノ家の至宝と呼ばれた神童だよ」
ハシェミの言葉に、アシュラルは睫を伏せて首を振った。
「過ぎたるお言葉にございます」
法王家の……。
クシュリナは得心した、ならば、彼が膝をつかないの理解できる。法王庁に属する者はすべからく神籍である。あくまで形式ではあるが、皇家の配下という立場ではない。
しかも、コンスタンティノ家は、シュミラクールの中でも名門中の名門だ。
それは、彼が持つ名前の特殊さにも現れている。
イヌルダの貴族にはすべからく地名からとった姓がついている。ハシェミには右京姓が、フォードには松園姓が、グレシャムには鷹宮姓が。それらは全て一族が発生した旧地名から取られた姓である。
コンスタンティノ家には、それがない。ないということは、つまり皇室と同様、地を収める者より上位の身分であったことを示している。
つまり シーニュ神を祖先に持つ皇室と同じく、創生の神々の血を引く一族の末裔ということになる。
聖将院という称号は、シーニュに仕えた四神のうち、闘神クインティリスを示す称である。
クインティリス、ディアス、アリュエス、ユリウスからなる伝説の四将は、それぞれ子孫を残してこの世界を去ったと言われるが、その血を引く一族は時代の中で淘汰され、今では聖将院の号を持つコンスタンティノ家しか残っていない。
名門コンスタンティノ家の至宝、アシュラル。 でも、彼が膝をつかない理由は、それだけではないような気がした。
なんだろう、
ドキドキする。……すごく、嫌な感じに、ドキドキする。
「クシュリナ、お前には生まれついての婚約者がいると、言い聞かせてあったが」
ハシェミの言葉も上の空にしか聞こえない。クシュリナは、見入られたように、アシュラルの眼から視線を逸らせないでいた。
暗く抑圧された闇の瞳、まるで、何かと戦っているような。
なんだろう、怖い。
「ようやく今夜、紹介できる運びとなった。まだ正式には発表していないがね」
この人の目は、ただ冷たいというだけではない。闇をも見通すような鋭い恐ろしさがある。
「彼が、そうなのだ。聖将院アシュラル。いずれ僧職を捨て、皇室にきていただくことになるだろう」
そして、最初から一度も、私を見てはいない。
「お年は……」
クシュリナは、作法として、ようやくそれだけを口にした。
婚約者を紹介されたことに関しては、戸惑いや驚きは全くなかった。
十八歳になるまでには、定められた者と結婚する。今まで、その未来に疑問や不安を抱いたことは一度もない。
ただ 彼が、自分にとってどういう意味を持とうとも、単純に、クシュリナは目の前の青年が怖かった。
もし、この人が、あの樹の下で出会った「彼」ならば。
どうしてこんなに、私は畏れてしまうのだろうか。彼の存在そのものを、ひどく不安に思ってしまうのだろうか。
あの日は……まるで、昔から知っていた人に出会ったような、……懐かしいような、……切ないような、不思議な愛おしさを感じたのに。……
「十七歳になります」
アシュラルは静かな口調で答えた。
クシュリナは少し、ほっとした。
「私より、七つもお年が上なんですね」
「そうですね」
薄い唇が、微かに笑ったような気がした。
決して暖かな笑みではなかった。しかも、彼が笑んだ刹那、確かに、その目に軽侮の感情が走るのが判った。
「あの……」
クシュリナは、胸の内が冷たくなる感情に耐えながら、訊いた。
「私たち……、以前、どこかでお会いしていないでしょうか」
何かの救いを求めて口にした言葉だったが、アシュラルは、心外そうに眉をあげた。
「私はこの年になるまで修行の身でございました。クシュリナ様とは、おそらく、初対面になろうかと存じます」
「そう、ですね」
「………」
不意に歩みより、アシュラルはクシュリナの手をとった。
冷たい唇が、そっと、手の甲に触れる。
「お早いご成長を、お待ち申し上げております」
目も合わせないまま、手はあっさりと離される。綺麗な手は、やはり唇と同じでひんやりと冷たかった。
「本日、コンスタンティノ様はおいでかな」
ハシェミが立ち上がりながら声をかけた。
「いえ、父は参りません。賑やかな席が苦手なもので」
「そうだったな。では私が、君をご婦人がたに紹介しよう」
「おそれいります」
クシュリナのことなど一顧だにせず、アシュラルは冷ややかにきびすを返した。形の良いまっすぐな背が遠ざかっていくのを見送りながら、クシュリナは暗い予感を覚えていた。
第一皇女という立場から、自身の結婚に愛や夢を抱いていたわけではない。現に、ハシェミの二度目の結婚は、政略だけで成り立っている。 だから、クシュリナも、結婚とはそういうものだと思っている。
けれど、頭で思っていた「結婚」は、実際にその相手を見た途端、「現実」となった。
しかも、恐ろしい現実となった。
ハシェミと共に広間に戻ったアシュラルは、待ち構えていた貴婦人たちに取り囲まれた。如歳なく微笑する横顔は、恋愛の対象にならない幼い婚約者のことなど、まるで忘れ去っているように見える。
ひどく寂しい惨めな気持ちで、クシュリナはその光景を見つめていた。
まだアシュラルが「彼」ではなかったら、もっと気持は冷静だったのかもしれない。
が、 「彼」はアシュラルだった。
記憶の中の出来事が、例え現実だったとしても、夢だったとしても。 。
「彼」に対する憧れに似た淡い思いは、今夜、この瞬間、跡形もなく消え去ったのだ。
クシュリナは不思議な確かさで自覚していた。私は、あの人が好きになれない……。多分、あの人もそう思ったように。
二人の結婚は、きっと、幸福とはほど遠い結末になるだろう。ハシェミと、そして義母のアデラがそうであったように。
広間の人の輪から離れ、ハシェミが再び戻ってくる。ぼんやりしていたクシュリナは、急ぎ父を迎えようと立ち上がった。
「あっ……」
初めての夜会服のせいか、それとも疲れのせいだったのか、足をもつらせたクシュリナは、つんのめるように前かがみになった。
いけない……!
父は、こういった失態を、なにより嫌う。
しかも初めてお披露目された舞踏会の席で、みっともなく転倒でもすれば、とれだけ冷たく叱られるか、想像するまでもない。
さっと青ざめたクシュリナを、背後から抱き支えた腕があった。
|
|