夢と、過去の記憶に、違いなどあるのだろうか。……
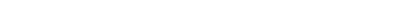
「お父様?」
声は、深い森の奥深くに吸い込まれていく。
「お父様、どこにいらっしゃるの?」
黒い森には乳白色のもやがかかり、わずか先も見通せない。
朝の日差しが、もやに薄く差し込んでいる。その、わずかな光に誘われるように、クシュリナはただ歩き続けていた。
その朝、クシュリナは、ハシェミと初めて朝駆けに出た。
従者一人をつれたハシェミは、クシュリナを抱くようにして自馬の背に乗せ、まだ明けもきらぬ金羽宮の北門を後にした。
(どこに行くの?)
八つになったばかりのクシュリナには、初めて許された外出であり、乗馬だった。
起床から就寝まで、厳しいしきたりと作法に縛られ、わずかな自由さえ許されない宮廷生活。牢獄のようなオルドから、初めて外に出ることが許されただけでなく、大好きな父と共に出かけることが嬉しくて、その気持のままに父をみあげた。
ハシェミは、薄い唇に美しい微笑を浮かべ、……そして、何と言っただろう。
(…………だよ)
確かにクシュリナは、父の唇から零れた言葉を聞いたのだが、そしてひどく恐ろしく思ったのだが、それは不思議な儚さで記憶から滑り落ち、今でも思い出せないままでいる。
(ここで待っていなさい)
やがて、馬から下ろされたクシュリナは、四方を生茂る木々に覆われ、光から遮断されたような森の只中に取り残された。
「ここは、なんという場所なの」
クシュリナは、共に残った従者に聞いた。
従者の名はガイという。クシュリナが生まれる前より、ずっと父に仕えている小柄だが屈強な男である。
以前ハシェミから、ガイの母親がハシェミの乳母であったと聞いたことがあるから、父にとっては乳兄弟にあたるのかもしれない。そのような縁があるから、クシュリナもガイを父と同じくらい信頼している。
「シーニュの森です、クシュリナ様」
赤茶けた髪を一つに括った頭を垂れ、恭しくガイは答えた。
「この森に、創造神シーニュが降臨し、そしてシュミラクールが誕生したのでございます」
世界の始まりの場所。 ―
幼いクシュリナには、ただ、枝々が彩る暗い陰と、鬱蒼とした葉の茂りしか見えない。
「お父様は、どちらにいかれたの?」
「この森の向こう側にございます」
「そこには、何があるの」
「そこはもう、我々の領地ではございません。法王領なのでございます」
「法王様の……?」
ガイはいかめしい顔に優しい微笑を浮かべて頷いた。
「シーニュの森が、天界と地界を隔てております。この先は何人たりとも通れぬ法王の禁制区。ハシェミ様がこちらをお訪ねになるのは、私が記憶しております限り、七年ぶりになるでしょうか」
「七年……」
私が、生まれた頃だろうか。
思わずガイを見上げていたが、ガイは、これ以上は何も言えないとばかりに、ただ微笑するだけだった。
その時、一陣の風が吹いた。乳のようなもやがさーっと押し寄せ、あっという間にクシュリナを包み込んだ。「姫様!」と、ガイが悲鳴にも似た声をあげる。
声はひどく近いはずだったのに、それきり二度と聞こえなくなった。
「ガイ? お父様? どこにいるの?」
驚きながら、手で障害物を防ぐようにして、クシュリナは歩き出した。もやの中、わずかに差し込む光に向かって懸命に手を差しのばす。
そんな風にして いったい、どれくらい歩いたろう。
「お父様……ガイ……」
光は確かに近くなっているはずなのに、周囲を覆う霧はどんどん濃くなって、やがて鳥のさえずりさえ聞こえなくなった。目に入るのはぼんやりとした白い世界。まるで、現実から夢の中に彷徨いこんでしまったようだ。
どうしよう。
「お父様、どこにいらっしゃるの?!」
泣きそうになった時、唐突に霧が晴れ、視界が開けた。
目を見張るような巨大な樹が、黒々とした枝を広げている。一定の間を開けて取り囲む木々が、まるでおじぎでもするかのように、大樹の前にひれ伏している。
透き通った陽射しが、大樹の上だけに降り注ぎ、あたかも光の粒子が空に向かって舞い上がっているようだった。
見えない力に導かれるように、クシュリナは、巨木に向かって歩き出した。
朝露に濡れ光る幹は、悠然とうねり、渦まくように天空に向かって伸びている。絡みあう枝はみっしりと天を覆い、そこに果てしない虚空が広がっているようにも見える。
美しい……でも、なんて恐ろしい樹なんだろう。
まるで、この世のものではないような。 ―
大樹のほうから空耳のような微音がした。風が吹き抜けるような、羽虫が震えるような、そんな音だ。
なんの、音……?
ふらっと歩み出したクシュリナの爪先に、何か堅いものがコツンと当たった。びくっとして足を止める。
「剣……?」
足元で、朝露をあびて光っているのは、細身の短剣だった。
藍の宝石が飾られた柄に、見慣れない文様が彫り込まれている。
青百合でも、黄薔薇でも、緋薔薇でもない。父の持つとも違う。初めて目にする紋章である。白い……桔梗……?
手を伸ばそうとしたクシュリナは、今度こそ驚いて、悲鳴を上げそうになっていた。
剣のわずか先に、投げ出された手があった。人だ。ホージズに包まれた脚も見える。男の人が倒れているのだ。
誰? もしかして、死んでいるの?
足を引くようにして後ずさりながら、ふとクシュリナは不思議な感覚に陥っていた。
なんだろう……私は……前も……この場所で………。
この人に出会ったことがある?
足をとめ、しばしためらったクシュリナは、おずおずと大樹に寄り添うようにして倒れている人の姿を覗き込んだ。
肩までの黒髪と白い肌。瞬間感じた美しさから、もしや女性だろうか、と思ったものの、衣服も体格も、明らかに男性のものである。
頭のあたりを地面にうねる根に預け、その人は緩く片膝を立てたまま、仰向けの状態で倒れているようだった。
顔は力なく斜めに傾き、艶やかな髪が額の半分を覆っている。
両腕は投げ出され、瞳は固く閉じられたままだ。
肌に色はなく、唇にも生気が感じられない。手足も胸もぴくりとも動かず、すでに息絶えてしまったようにも見える。
この人はまだ生きている。
が、何故かクシュリナはそう確信した。
確信というより、ひらめくようにそう思った。
そっと歩み寄り、影になった顔をのぞきこんでみる。 美しい……。その刹那天上から光が差し込み、その人の顔を照らしだした。
整った眉、薄くて形良い唇、頬に淡い影を落とす長い睫。
深紅の金刺繍のついたケープ、濃い緑のボディス、額に零れた漆黒の髪が、朝露に濡れたように光を反射して煌いている。
これほど綺麗な男の人を、クシュリナは見たことがかなった。
ふと、不安にも似た不思議さに囚われる。
ここは、本当に現実かしら。私は知らない内に、幻想の世界に迷い込んでしまったのではないかしら。 。
ざわ……。
突然、木々がざわめいた。
びくっと、クシュリナは肩をふるわせる。
何かが、胸の奥底で警鐘のように閃いた。
シーニュが、この人を連れていこうとしている。
クシュリナは、震える手で彼の肩に触れてみた。朝露を吸った衣服はひんやりと冷たかった。
「起きて……」
そっと、ゆさぶる。
「お願い、起きて」
なんの反応もない。
「起きてください、お願いだから」
蒼ざめた頬。動かない唇の端からは、わずかに白い歯が零れている。
ざわっと、再び大樹がざわめいた。それがクシュリナには「連れていくよ」と言っているように聞こえた。
「お願い……!」
クシュリナは木に向かって 見えない何かの意思に向かって声を強く張り上げた。
「お願い、この人を連れていかないで!」
その瞬間、触れていた「彼」の肩が、微かに動いた。
はっとして、覆いすがるようにその顔をのぞきこむ。
「しっかりして、眼を覚まして!」
声に反応するかのように、長い睫が震え、「彼」は薄く目を開いた。
数度の瞬きの後、確かな生気を取り戻した眼が、静かにクシュリナに向けられる。
「……君、は」
囁くような声だった。
クシュリナはどう答えていいか判らず、ただ、「彼」の冷たい手を握り締める。
何かを言おうとした彼の唇に、ふと、安らいだような微笑が浮かんだように見えた。
小さな囁きが、その唇から風のように漏れる。
え……?
それは、意味をなさない単語だった。
人の名前? 三文字の、ひどく聞き取りづらい音調だ。
彼の手が、そっとクシュリナの頬に触れ、全ての不思議さに吸い寄せられるように、クシュリナは引き寄せられている。
乾いた唇が、唇に触れた。
まるで、柔らかな羽が触れたような感触だった。
え??
ばっと顔をあげ、両手で頬を押さえたクシュリナは、飛ぶように後ずさる。
今のは、何?
今のは……お父様と交わす頬への口づけと同じで……でも、でも。
みるみる頬が熱くなるのを感じながら、クシュリナは再び彼の方を見る。
彼は、すでに瞳を閉じていた。先ほどとは違い、胸がゆるやかな呼吸を繰り返している。確かな生の息吹が、赤みを増した唇から零れている。
クシュリナはほっとして、膝をついたまま傍に寄ると、額にかかる彼の髪をそっと払った。
あなたは、誰……?
綺麗な人……。
その時だった。
「アシュラル様!」
「どちらにいらっしゃいます!」
慌ただしい声が、幻想を現実に引き戻した。
忙しない足音、入り乱れる人馬の気配。
クシュリナは、狼狽して立ちあがる。
「おお、こちらだ!」
「お気を失っておいでになられる」
駆け寄ってきたのは、僧服姿の男たちだった。中には華奢な体格の者もいたから、女も混じっていたのかもしれない。
「急げ、一刻も早く修道院にお運びしろ」
やがて馬の蹄が聞こえなくなるまで、クシュリナは、息を詰めるようにして、木の影に身を隠し続けていた。
気づけば、まだ、心臓が高鳴っている。
アシュラル……?
初めて聞いたはずのその名前に、何故か、確かな覚えがあった。
どこかで聞いた。でも、どうしても思い出せない。どこだったろう。どこか……ひどく、遠い昔……。
「姫様ーっ、どこにおいでになられますのじゃ!」
ガイの声が、クシュリナを現実に引き戻す。
「ガイ!」
叫んで走り出したクシュリナは、ふと足をとめ、背後を振り返っていた。
朝の静寂の中、鬱蒼とした木々の群れが、静かな佇まいを見せている。
天を衝くほど巨大な樹だったのに、その姿はもう、どこにも見出すことができなかった。
あれは 本当に夢だったのかもしれない。
後年、あの日のことを思い出すたびに、クシュリナはそう思うようになった。
あの日の、夢とも現実ともつかない出来事のことを、クシュリナはガイにもハシェミにも漏らしてはいない。
ハシェミもまた、何故このような場所にクシュリナを連れて来たか一言も説明しないまま、三人は黙して金羽宮に帰ったのだった。
幻のように消えてしまった大樹のことは、やがて判った。
シニフィアンの樹。
この世界に最初に生まれた命の種とも、息絶えたシーニュが変化した霊樹とも言い伝えられている。
いずれにしても、その樹はシーニュの森深くに護られ、決して人眼に触れることは叶わないとされている。
もし、クシュリナが見た樹が本当にシニフィアンの樹なら、あれはやはり、幻だったのだ。 あの樹の下で眠っていた美しい男の人も含め、全てが。
年を追うごとに、クシュリナはそう信じるようになった。
その証拠に、どうしても思い出せないのだ。
「彼」が発した名前のような言葉。
あんなに間近で見ていたはずの「彼」の顔。
どうしても、何をしても思い出せない。
まるで、夢の中の記憶のように。 。
|
|