第二部 イヌルダ 天迎十七年 |
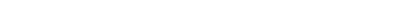 |
第一章 有栖宮クシュリナ
1
クシュリナ様……。
夢から呼び戻す、懐かしい声。
「クシュリナ様」
クシュリナは目を開けた。その瞬間、自分の中に、何かがすうっと収束していくような、そんな不思議な感覚がした。
なんだろう、今の……。
鼓動が少し高まっている。
まるで、自分の中に、他の誰かが入り込んでしまったような。
「どうなさいました」
天蓋を覆う帳の外で、再び柔らかな声がした。女官のダーラ。クシュリナの朝は、いつも彼女の声で始まる。
「夢でも、見ておられましたか」
「うん……夢なの、かな」
なんだろう、ドキドキする。クシュリナは胸を押さえた。 なんだか、……すごく、嫌な気持ち。
起き上った途端、髪が、さらさらと肩に流れる。その感触に、嫌悪にも似た違和感がした。何故だろう、夢で感じた毒々しい感情が、まだ身体の奥に淀んでいるのだろうか。
「まぁ、どのような夢をご覧に?」
「うん……」
クシュリナは曖昧に言葉を濁す。
わからない。もう……何を見たのか忘れている。感情の断片だけは、ひどくはっきりと残っているのに。
ふと、不安になって、繻子の帳を手で払った。
寝台の脇で跪いているほっそりとした長身の女性。訝しく瞬きをするその人の顔を、身を乗り出すようして、まじまじと見つめる。
「どうなさいました?」
ダーラ……。
凛々しい女騎士は、戸惑ったように切れ長の目を細くする。
腿の半ばまでの銀灰の上着。すらりとした足は、長い皮長靴で覆われている。腰に煌めく短剣には青百合の紋章。宮家直属近衛隊、その中でも、有栖宮を称するクシュリナの宮殿を護る証である。
「何か、私の顔についておりますか」
不思議そうな眼で、ダーラは寝台の上の主人を見上げる。
髪を後ろで束ねているせいもあるが、女性というよりは華奢な男の人、という感じだ。
「不思議……」
クシュリナは呟いた。
「お前が、すごく懐かしい」
「まぁ」
一拍おいたダーラは、眼を見開いて薄く笑う。
「おかしな姫様、私なら、毎日お傍におりますのに」
「そう、……そうよね」
なんの夢を見ていたんだろう。どうしても思い出せない。夢で、私は、なんと呼ばれていたんだっけ? おかしな名前……、喉元まで出かかっているのに、どうしても続きが出てこない。
「さぁ、クシュリナ様、今日は忙しい一日になりますよ!」
ぐずぐずするクシュリナを促すように、ダーラが、颯爽と立ち上がった。彼女の背後には、いつもの朝の光景が広がっている。
「おはようございます、クシュリナ様!」
一斉に放たれる女性たちの声。ずらり、と居並ぶ麻のドレス姿は、いっそ壮観でさえある。
女たちが被る白帽子には青百合の刺繍。フラウ宮殿に仕えるクシュリナ付きの侍女たちは、着替えや洗面や髪結いの支度を整え、主人の目覚めを待っていたのだった。
「クシュリナ様、急いで朝のお支度をなさってくださいませ。今日は、姫様にとっても、とても特別な日でございましょう?」
「特別な日……?」
足を下ろすと、柔らかな絨毯が素足をふんわりと包みこむ。この感覚でさえ、なんだかひどく懐かしかった。
「特別なことが、今日、何かあったかしら」
「ま、もうお忘れですか」ダーラは、呆れたように眉を上げる。
「あれほど、楽しみにしておられたのに、今日は、青州のユーリ様がお出での日ではありませんか」
「あっ」
頭の中で、何かが不意に弾けたように、いきなり記憶が鮮明になった。
「おかしな姫様、二年ぶりのご再会でいらっしゃると、昨夜はあれほど興奮していらっしゃったのに」
そうだった。
クシュリナは、慌ててかけ出そうとする。
「まずはお着替えを」
「お湯をお使いくださいませ」
「御髪を整えませんと」
たちまち、侍女たちの輪に取り囲まれる。
「姫様、ユーリ様のご到着は、夕刻でございますよ」
輪の外で、ダーラは、くすくすと笑っている。
「その前に、大切な催しがあることを、お忘れになりませんよう。今夜は、姫様が戻られて以来、初めてとなる五公揃っての大舞踏会、お支度は万全になさいませんと」
「わかってるわ」
四方から伸びる手に、衣服を脱がされながら、クシュリナは、自分の頭を叩きたい気分だった。
本当にどうしたのかしら、今朝の私。あれだけ楽しみにしていたことを、綺麗さっぱり忘れてしまっていたなんて。
鷹宮ユーリ。
十二の年から十五歳まで、青州の城で共に過ごした幼馴染。この二年間、ずっと彼との再会を心待ちにしていたのに。
「お食事をお済ませになられたら、今朝は、乗馬をされてもようございますよ」
「本当に?」
洗面と着替えを終え、髪結いに入っていたクシュリナは、歓喜に眼を輝かせた。
微笑むダーラは、てきぱきと侍女たちに片付けを指示し、あれほど騒然としていた室内は、今は静けさが戻りつつある。
「公のご許可も得ております。明日から公務で忙しくおなりなのですから、今朝くらいは思いっきりウテナを駆けさせてやりましょう」
「うれしい、ありがとう、ダーラ!」
立ち上がって、背の高いダーラを抱きしめて、キスでもしたい気分である。
むろん、そんな真似ができるはずもなく、クシュリナはうきたつ気持を静めながら、長時間の髪結いと、化粧、苦手な香水の攻撃に耐え続けた。
起床から礼拝に至る朝の儀式は、日の出前から日が半ば登るまでの長時間に及ぶ。
昔からクシュリナは、この退屈な時間が、憂鬱でたまらなかったのだが、二年前、斎美ダーラが青百合宮殿の第一女官として傍につくようになってから、さほど苦手ではなくなった。
万事が合理的で、頭のよいダーラは、朝の行事から一切の無駄を取り除き、その分、クシュリナの好きな乗馬や読書、刺繍の時間などにあててくれる。
全ての支度を終え、廊下に出ようとしたところで、クシュリナは足を止めた。壁に埋め込まれた大きな鏡に、見知らぬ女がよぎったような気がしたからだ。
驚いたものの、すぐにそれは、自身の顔だと気がついた。
……私?
ふと、釣られるように、鏡のほうに歩み寄っている。
「クシュリナ様?」
追いついたダーラが、けげんそうに背後で足を止める。
「ねぇ、ダーラ」
「なんでございましょう」
並んで鏡の前に立つと、二人の身長差は頭ひとつほどもある。鏡に映るダーラの微笑みを見つめながら、クシュリナは今朝の夢の 不思議な感覚を確かめるように、自身の顔を、指でなぞった。
「……私、こんな顔してたのかしら」
「まっ」
吹き出すようにして、ダーラは笑う。笑うと、普段凛々しい顔が別人のように優しくなって、ますます彼女が美しく思える。
「クシュリナ様は、誰よりお美しくていらっしゃいますよ」
「お世辞はやめて、ダーラに褒められても嬉しくない」
クシュリナは頬を膨らませる。お世辞というより、厭味じゃないかしら、とも思っている。
「……本当でございますよ」
ダーラの眼が、優しくなった。優しくて、なのにどこか寂しげな眼差しが、染みいるようにクシュリナを見つめている。
時々、そんな視線を向けてくる七歳年上の女の気持が、いつもそうだが、クシュリナにはよく判らない。
再び歩き出しながら、クシュリナはふと呟いていた。
「今朝見た夢ね……気のせいかもしれないけど、前も、見たような気がするの」
「それがどのような夢なのか、姫様は、一度も教えてはくださいませんよ」
ダーラが、いたずらっぽく口を挟む。
「だって、憶えていないんですもの。でもね……でも、夢から、覚めた時」
「覚めた時?」
「………」
すごく不思議な感覚がする。夢が現実なのか、現実が夢なのか、よく判らなくなる時がある。
目覚めてしまえば、しょせん夢の記憶は彼方に消えてしまうのに。
「……ううん」
理解を得るのを諦め、クシュリナは淡く睫を伏せた。
多分、現実から逃げたい気持が、そう思わせているのだろう。
もし、私が、イヌルダの第一皇女でなかったら。もし、私が、全てを自由に選択できる身だったら。 。
それは、物心がついてから何度も想像しては諦めた、決して叶わない夢だった。
|
|