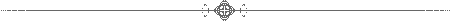 |
「どうして何度言ってもわからんのだ!」
お前は私の子供だろう!
やれば出来るはずなんだ、なんだって本気でやればな!
続けさまに響く怒声。
またか……。
真行琥珀は、ため息をついて窓を閉めた。
こんな風に、門倉雅が、父親に叱責されるのはいつものことだった。
琥珀の部屋は、門倉篤志の書斎に面している。扉を開けていれば嫌でも騒ぎが耳に入る。
門倉篤志は、中学生の娘に対して、厳しすぎるほどに厳しかった。
それは琥珀の目から見ても常軌を逸しているように思える。眼をつりあげて何度も机を叩く様は、温厚篤実な選挙ポスターのイメージとは程遠い。
しかも 時に、耳を塞ぎたくなるような音を聞く時がある。
鞭の音だ。そして泣き叫ぶ雅の悲鳴。
「琥珀さん」
声と共に、扉をノックする密やかな音がした。
琥珀は立ち上がってドアを開ける。門倉祥子が目を伏せたまま立っていた。
雅の母親 痩せて骨がつきだした肩、化粧っ気のないそそけた顔、何より不気味な、一切の感情が欠落した瞳。
思わず、顔をしかめて目を逸らしている。
「琥珀さん、お父様を止めてきて」
抑揚のない声がした。
「あれじゃ、雅ちゃんが可哀想。琥珀さん、お願いだから、早く行ってきて」
これも、いつものパターンだった。
琥珀は、この養母が雅以上に苦手だった。哀願するでもない、激昂するでもない。ただ 淡々と、それがあなたの仕事よ、と言わんばかりの口調で、仲裁の役目を命じに来る。
琥珀は無言で祥子の脇をすり抜けると、扉を開けて部屋を出た。
「雅! 返事をせんか!」
途端に、耳に飛び込んでくる怒声と啜り泣き。
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい……。
気が滅入る。こんな雅の声を知っているのは、おそらく自分くらいだろう。
あの雅が、父親の前では、驚くほど素直で恭順なのだ。むしろいいなりと言っていいほどに。
「おじさん」
琥珀は半開きの扉をノックして、声を掛けた。
「琥珀か」
ふっと、力が抜けたような声がする。
「おばさんが、食事の支度が出来たって、呼びに来てますけど」
「そうか」
扉の隙間から、床にうずくまって顔を伏せている雅の背中が見えた。
「琥珀、全国少年剣道大会、都の代表に選ばれたらしいな」
扉から顔を出した篤志は、薄い唇に、わずかな笑みを浮かべていた。ポスターやテレビでよく見る、とりすましたような笑顔をしている。
「私も後見人として鼻が高い、頑張りなさい」
「………」
琥珀は何と答えていいかわからないまま、曖昧に頷いた。
雅には、子供の頃から異常に厳しい篤志だったが、琥珀に対しては、一転して、舐めるように優しい。
門倉家に引き取られてこのかた、琥珀は、篤志から叱責されたことが一度もない。テストでどんな成績を取ろうとも、友達と喧嘩しようとも、一度も、だ。
その優しさに、逆に寂しさをかきたてられたこともある。しかし、琥珀は自分の立場をよくわきまえていた。しょせん、自分は門倉の実の子供ではないのだ。養子ですらない、単に学資と居住の世話になっているにすぎない。
事故で死んだ両親は、夫婦で門倉篤志の政策秘書をしていた。自分はその縁で、こうして恵まれた生活を送っている。 それは、とてもありがたいことなのだ。
が、そう思う一方で、琥珀は焦れるほど強く、門倉家を出る日を切望していた。
一日も早く生きる術を身に着け、この家を出ていきたい。
幼い娘に対し、過酷なまでに厳しい父親。人形のように夫に従い、娘を庇うことのない母親。
そして 表では明るい優等生を演じながら、裏では、全く別の顔を見せる雅。
門倉家は歪んでいる。この家は、正常の家庭とはどこかが違う。
年を追うごとに、雅の嫌がらせや悪意を持った挑発は、ひどくなる一方だった。
両親が見て見ぬふりを決め込んでいる雅の暗黒面は、全て、琥珀一人が引き受けている。
息が詰まるような日常の中、いつか家を出る日が来ることだけが、琥珀の唯一の希望だった。
その日の夕食に、雅は姿を見せなかった。
琥珀は滅入る気持ちを抱いたまま、自室に向かう階段を上がった。
明日から篤志は地方遊説に出かける。そうなれば雅は、それまでの鬱憤を晴らすかのように、様々な難題を琥珀にぶつけてくるだろう。
稽古や授業の最中に、なんくせをつけて呼び出されるのはまだいい方だ。
いきなり食器をぶつけられたり、風呂を覗かれたと騒ぎたてられたり、床の間の壺を割って、それを琥珀のせいにされたり。 執拗で巧妙、時に幼稚な嫌がらせの数々に、正直、琥珀はなすすべもない。表情に出さないように努めてはいるが、ほとほと疲れ切っている。
なのに雅は、時折、なんとも言えない寂しげな目で、琥珀を見つめる時がある。
頼りない仕草で、琥珀の袖を掴んで離さない時がある。
そういう時の雅は、不思議なくらい愛しくて、琥珀も、ふと心の警戒を解いている。
今まで雅に感じたものは、全て誤解だったのではないか、本当の雅は、出会った頃の昔のまま、優しくて可愛い、無邪気な女の子なのではないか。 そう思えた時に、凄まじいしっぺ返しが待っているのだ。
いってみれば、雅と琥珀の関係は、信頼と裏切りの連続だった。
琥珀にはもう、雅という存在そのものがよく判らない。
出会った頃は、可愛らしくて大人しい、むしろ優しいとさえ思える少女だった。
両親が急死し、わけがわからないままに門倉家に引き取られた後も、雅はいつも親切で、まるで姉のように、一人ぼっちの琥珀を慰めてくれたりもした。
そうだ、いったいいつから、雅は変わってしまったのだろう。 。
「……?」
扉の隙間から明かりが漏れている。
琥珀は扉を開け、そして声を出さずに驚いていた。
室内は、目茶苦茶に荒らされている。机の抽斗は全て引き出され、中にあったものが絨毯の上に散乱している。
机の上に広げられたノートが、赤ペンで塗りつぶされている。考えるまでもなかった、雅の仕業だ。
黙って片付けはじめた琥珀は、あることに気がついて、眉を寄せた。
ひっくり返された鞄の中身をもう一度確かめる。
ない 。
今日の午後、瀬名あさとから借りたノートだけが、なくなっている。
「武は矛を止むるの義なれば、少しも争心あるべからず。兵は凶器といえば、その身一生用いることなきは大幸というべし……神道無念流の心構え」
雅の背中が、蝋燭明かりに揺れている。
やっぱり、ここか……。
琥珀は、眉を嫌悪でしかめたまま、揺れる雅の背後に立った。
締め切られた蔵の地下。
庭の隅に、忘れられたように建立されている土蔵にも似た建物。定かではないが、明治から続く門倉家に、最初からあったと言われている。
数年前までは、記者の待合に使われたというだけあって、外装と上階部分は綺麗に改装されている。
が、地下だけは、なんら手をつけられず、明治の名残をそのままにしているようだった。
不思議なことに、雅は何故だか、この、ぞっとするような陰気な場所をひどく好む。
琥珀が知る限り、父親に激しく叱責された後など、必ず一人で、地下に閉じこもっている。
(あの場所は、子供の頃の雅ちゃんの遊び場だったの。だから琥珀さんは、余計な心配をしなくていいのよ)
祥子は意にも介さないようだったが、琥珀には、どうにも理解できなかった。
電気も通らないこんな地下に、いったい何の用があるのか 中にまで足を踏み入れたことはないが、どことなく入ることが躊躇われるような何かが、確かに室内には満ちていた。
雅は、懐中電灯を手にしている。
足元には、幾本かの蝋燭が揺れているようだった。
「なぁに、これ、なんであさとのノートが、ここにあるの」
ゆっくりと振り向いたその顔は、薄い笑みを浮かべていた。唇の端が、蒼く腫れ上がっている。
琥珀は目を逸らしていた。娘を殴る篤志も理解できないし、殴られて怒りもしない雅もまた、理解できない。
「この間、稽古を何度か休んだんだ」
琥珀は後ろ手に扉を閉め、囁くような声で言った。灯りを漏らさないためだった。この地下に二人きりでいる所を祥子に知れれば、今度は琥珀が困った立場になる。
「瀬名が、師匠の講釈をまとめたノートを貸してくれた、明日には返さなきゃならない」
「ね、どういう意味なの。これって」
「それは……」
琥珀とあさとが通う剣道の道場は、通常の剣道教室とは別に、幕末から伝わるという神道無念流そのものを特別に教授してくれる。
神道無念流とは、実践で使う修羅馬に強い剣法であり、いわゆる、型どおりの剣道とは全く異質のものだ。使いようによっては非常に危険な剣術のため、誰もが習えるというわけではない。道場の中から選ばれた何人かが、特別に教えてもらえる。
「剣とは、平和の世を実現するためのもの、使わないで済むのなら、それが一番の幸せであるという……そういう意味だ」
「ふぅん……」
雅は、無表情な目で琥珀を見つめると、手にしていたノートをゆっくりと目の位置まで持ち上げて、それから、一気に引き裂いた。
細かく、細かく、執拗な執念深さでノートを破って行く雅を、琥珀は、静かな気持ちで見つめていた。
驚きも怒りもない。もう、そんな感情には慣れすぎてしまっている。
ただ ひどく気が滅入った。何もかも、どうでもよくなってしまうほどに。
「琥珀は、知ってる?」
手に残るノートの断片を細かく切り裂きながら、雅は歌うように口を開いた。
「どうしてお父様、琥珀にあんなに優しいのか、知ってる?」
長い髪が、窓から吹き込む風に揺れていた。
「どうしてお父様が、あれほど私に辛くあたるか、本当の理由、琥珀は知ってる?」
「…………」
本当の理由?
「ふふ……ふふふ」
何が、言いたいのか。琥珀は無言で、風に揺れる雅の髪だけを見つめ続ける。
「琥珀のお父さんはねぇ、うちのパパに殺されたんだよ」
琥珀は眉根を寄せた。何か言いたいのに、言葉は何も出てこなかった。
両親が死んだ理由を、琥珀はよく知っていた。
事故である。そう聞かされていた。仕事で移動中、ブレーキミスで、車ごと海に落ちたのだと。
「琥珀、本当に知らないの?」
雅は、不意に弾けたように笑いだした。
「ねぇ、本当に? 本当に? あれだけ頭がいいのに、そんなことも知らなかったわけ?それでパパに可愛がられて、それなりに幸せ感じてたわけ?」
雅がにじりよってくる。後ずさった背が、壁に当たった。
ぞっとした。いつも奇異に思っている 雅であって、決して雅ではない女の眼。
信じられない。女とは、感情次第で、こうも別人になれるものなのか。
「パパにはね、あの時、大手ゼネコンからの献金疑惑が持たれていたの。新聞には伏せられていたけど、内情は逮捕寸前。金の流れを全部把握してたのが、琥珀のパパ。ね、その意味わかる?」
「…………」
黙る琥珀を見上げ、雅は再び弾けるような笑い声をあげた。
「嘘だと思ってるでしょ、あり得ないと思ってるでしょ。だったら調べてみたら? 当時のスクープ記事、琥珀に見せてあげようか?」
心臓が、嫌な動悸をたてている。
琥珀自身、両親の死に、多少の政治めいた疑惑を感じたことがないわけでもなかった。が、いつもその度に打ち消してきた。だとしたら、自身の罪の証の遺児を、こうして世話ができるはずがない。門倉厚志とは、そういう意味での篤志家では、決してない。
むしろ、邪魔で、役に立たないと断ずれば、あっさり切り捨てる冷酷な精神の持ち主だ。
(君の父は、私にとっては無二の親友だったのだ。君の面倒を見たいという私の気持ちは、ただ、君の父への友情から来ているんだよ)
琥珀は、その言葉を信じている。
「ねぇ、琥珀」
「よせ」
伸びてきた腕を、琥珀は振り払っていた。
「琥珀は頭がいいのに、自分のこととなるとからきしだね。ねぇ、O型とB型の親からは、A型の子供は生まれないって知ってた? 当然、知ってるよね、優等生の琥珀なら」
「……なんの話だよ」
「パパの失敗は、事故に琥珀のママまで巻き込ませちゃったことだろうね」
………。
「大好きな大好きな、琥珀。可愛くて愛しい琥珀。まるで恋人を見るようだもの、琥珀を見るパパの目って」
それは……、どういう。
よろめいた琥珀は、壁で自身を支えている。
「ねぇ、じゃあ、あたしたちって、兄妹なのかな?」
手も足も動かない。
「ふふふ、うふふふ」
この女は、一体何を言っている……?
いつの間にか、雅の身体がぴったりと密着している。
「琥珀がいるから、私はパパに愛されないの。琥珀のせいよ、何もかも琥珀のせい、ねぇ、さっさと死んじゃってよ。琥珀なんて、消えてなくなっちゃえばいいのに」
「…………」
「死んじゃえ!」
ぞっと寒気のするような声だった。が、その声は次の瞬間甘い、大人の女のような色を帯びる。
「可哀想な琥珀、可哀想な雅……。ねぇ、琥珀、琥珀だけは、雅のこと、何があっても裏切らないでね……」
この女は。 。
そこで眼が醒めた。
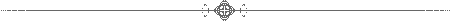
夢で、俺は、なんと呼ばれているんだろう。
わからない、その名前だけが、欠落している。……
|
|