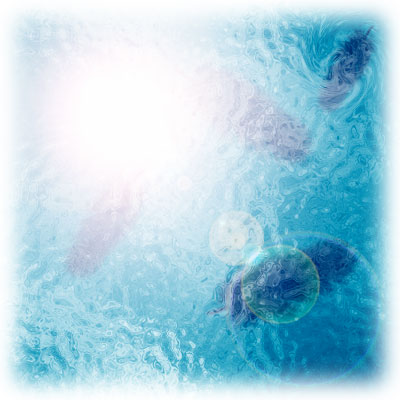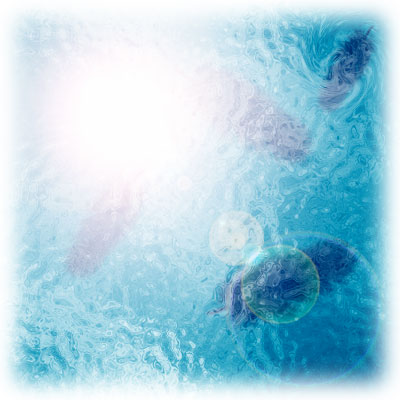三
・
・
振り返る女の表情は、流れるライトに幻惑されてよく見えない。
御守は名状しがたい胸の悪さを感じ、しばらく無言で、風にあおられる柔らかな髪を見つめていた。
けれどすぐに、思考は現実に立ち帰った。
――――これで、いい。
「そうだな……俺は現金を余り持ち歩かないから、何か、買ってやろう」
「ううん……現金がいいな、できたらだけど」
わるびれない瞳。これが真実で、これが現実なのだと御守は静かな気持ちで考えた。
ひとときでも、莫迦な幻想に囚われていた。自分の甘さに腹が立つ。
「……では、持ち合わせをやろう」
コートの内ポケットから本皮製の財布を取り出し、中身を確認した。
現金は余り持ち歩かないと言いながらも、緊急時に備えて二十万程度は常に用意している。
それをそのまま掴み、御守は無言で有紀の前に差し出した。
「……こんなに?」
「俺にとっては、たいした額じゃない、好きに使え」
わざと冷たい口調で言った。
有紀の眼にわずかな逡巡の色がかすめたような気もしたが、それはほんの一瞬だった。
「ありがとう」
女は満面の笑みで、それを受けとると、束ごと手づかみにしたまま、たんっと軽やかにきびすを返した。
逃げたのか……?
そう思えるほどの身軽さで雑踏に消えた背中を、一瞬、御守は見失っていた。
けれどきわだつ美貌はすぐに確認できた。
ほんの数メートル先、有紀が立っていたのは、交差点で高校生たちが呼び掛けている、交通遺児への街頭募金箱の前だった。
彼女を見守る高校生たちが驚愕している。
ようやく追いついた御守は、有紀が手にしていた札全てを募金箱に投げ入れるのを―――眉をひそめたまま見守った。
―――なんの真似だ……?
冷たくした自分へのあてつけなのか、けれど、明日の住処さえ定まらないこの少女にとって、二十万というお金が意地や見得だけでぽんと寄付できる金額だとも思えない。
「お待たせ」
有紀は息を切らして掛け戻ると、そう言って何事もなかったかのように微笑した。
疑問を口にしかけた御守は、かろうじてそれを思いとどまった。
互いの私生活には干渉しない、それがルールだ。少なくともこれ以上、この女の内部に立ち入るのは危険な気がする。
「篤志家だな」
ただ、皮肉交じりにそう言った。
御守自身は街頭募金に寄付したことは一度もない。
義理と慣習で多大な寄付を各団体には施している。それでもう十分だと思っていた。
「……独り占めは、よくないことだから」
有紀は低い、けれどはっきりとした口調で言った。
「沢山持っているものは、誰かに分けてあげなきゃいけないんだ、……そうだよね、御守さん」
「………」
御守は、自分の眉が自然に曇るのを感じていた。
――――そのフレーズを、どこかで聞いた記憶が……ある……?
「私、お腹すいちゃった!」
有紀の笑顔が、御守の思考を遮った。そして子供っぽい仕草で自分の腹部を撫でた。
「御守さんは、お腹空かない?ご飯食べたの、随分前になるよね」
「……そろそろ車に戻るか」
確かに軽い空腹を感じてはいた。
六時に食事を一緒にとったが、仕事で頻繁に携帯電話が鳴ったせいもあり、余り食が進まなかった。
「ね、ちょっとここで待ってて」
ほっと白い息を吐き、有紀は笑んだまま背を向けた。
そして、女はすぐに戻ってきた。
「はいっ」
差し出された腕、その先で湯気を立てているのは、暖かなコーヒーとホットドッグのプレートだった。
「たまには私におごらせてよ、屋台が出てたから買ってきちゃった」
「……どこで食うんだ」
「ここで」
有紀は、視線で傍らのベンチを指し示すと、白い歯を見せてきれいに笑んだ。
「好きじゃなかった?……ね、ここに座って食べようよ」
「それは……いいが」
自分と有紀の着ている衣服を交互に見る。
上質のシルクスーツにチーフ、皮製のコート。有紀は、薄緑のパンツスーツにアンゴラのショートコートを羽織っている。
今から夜会にでも出られそうな衣装のまま、ベンチで、ホットドッグ。
―――ものすごい、違和感があると思うんだが……。
「ほら、御守さん」
「あ、ああ」
うながされるまま、仕方なく緑地帯の一角に設けられたベンチに腰を下ろす。
冷たく冷えたベンチの感触。暖かなコーヒーと、空腹を刺激する香辛料の香り。
さきほどまで感じていた違和感が、不思議なくらいゆるやかに解けていく。
「懐かしいな……」
思わず呟いていた。
「え……?」
「いや、なんでもないよ」
戸外で飲食するのは、随分久しぶりのことになる。
まだ専務になる前の室長時代、徹夜で取り組んだ「東風新都」プロジェクト以来のことだ。
あの頃は仕事に夢中だった、若くて――今ほど恋を恐れてもいなかった。
「………私、御守さんのこと、もう少し知りたいな」
コーヒーに息を吹きかけながら、有紀が呟くように言った。
「ルール違反?でも、少しだけ…駄目?」
「何を知りたいんだ」
「色々…全部。年とか、生年月日とか、血液型とか、星座とか、好きな女性のタイプとか」
思わず吹き出しかけていた。
まるで、女子高生の会話のようだ。
「今年で三十二になる。お前の倍近い年齢だな」
コーヒーを一口飲み、御守は短くそう答えた。「後は好きなように想像しろ」
「秘密ってこと?」
「立ち入らないのがルールだろう、お前の決めた」
「まだ若いのに…えらいんだね。専務って、会社でもすごくえらい人なんでしょ」
―――それは……。
言いかけてやめた。
御守の父は理光グループの母体、理光証券の名誉総裁、そして理光不動産を始めとするグループ企業の総帥でもあった。
長男の御守は、実質その後継者と目されている。
それゆえに、若くして理光グループメイン事業の室長に抜擢され、当然のように昇進を重ねて専務になった。
実力だと誰もが言うが、それだけでは決して今の場所を手に入れられなかったことを、御守自身が嫌と言うほど自覚している。
それをいちいち自嘲交じりに説明しても始まらない。
「……兄弟は…いるの?」
「想像しろと言ったはずだ」
少しの間、有紀はふてくされたように無言だった。そしてふいに空を見上げ、手をかざしながら小さく言った。
「御守さんの部屋にあったあの写真、……あの女の人、お姉さんなんでしょう?」
「………」
正直、驚きで、手にしていた紙コップを取り落とすところだった。
書斎に置いていたフォトフレームのことだ。
「……どうして、そう思う」
「んー、なんとなく」
あの写真。
夏の一日。姉と一緒に写った、たった一枚きりの写真。
あれは自分への戒めだった。決して――あの夏、自らが犯した罪を忘れないための。
けれど、中学生の男女二人が並んで写った古ぼけた写真。あれで――どうして姉だとわかったのだろうか。身長も高く、大柄な御守は、いつも兄だと間違われていたのに。
「なんとなくじゃ判らない、どうしてそう思うか言ってみろ」
有紀が黙っているので、御守は同じことをもう一度聞いた。
コップの中身は、外気の寒さであっという間に冷たくなっていた。
指先がわずかに、かじかむ。交差点で激しく鳴らされたクラクションが、二人の会話を一瞬遮っていた。
振り返った有紀は、薄っすらと笑んだ。
「二人の雰囲気がなんとなく似てるし……御守さん、本当はすごく甘えん坊だって気がするから」
「………」
「……それにね、あなたは時々うなされてるよ、とても辛そうなの、……とても悲しそう」
有紀はわずかに首をかしげる。優しいまなざしが、じっと御守を見つめている。
「そんな時ね、私、傍についててあげてたんだよ、気づかなかった?」
「…………」
御守は初めて、夢から覚めたような思いで、目の前の女を見つめた。
「……あなたはうわごとにように呟くの、……サクラコって、……許してくれって」
「…………」
「……サクラコって……あの人の名前?……何が、御守さんをそんなに苦しめてるの?」
「…………」
「……その人、ひょっとして、死んじゃってるの?」
御神は立ち上がっていた。
有紀が驚いて顔を上げる気配がする。
「半分は当ってる……でも、半分は外れだな」
耳の奥で、あの日の海の囁きが聞こえる。
「桜子は異母姉だ。いわゆる妾腹ってやつだ。十の時俺の母親が死んで、親父の妾だった女が――桜子を連れて、後妻としてやってきた」
どこかで、感情の抑制が効かなくなっている。
(……こんにちは、蓮君)
やさしい声、玲瓏とした美貌。
(……私、今日からあなたのお姉さんになるの……よろしくね)
溢れ出す回想を遮るように、御守は口早に言葉を繋いだ。
「桜子も、実の父が不動産会社の社長で、こんな、くそ生意気な弟がいるなんて、まさか夢にも思ってなかったろう。俺は、お前とは逆の立場になるのかな。……いきなり現れた一つ上の姉を認めたくなくて、なにかにつけては、子供じみた嫌がらせばかりしていたよ」
何か言いかけた有紀を目で制し、御守は続けた。
「頭も悪いし、運動もできない、身体も弱くて、……何も出来ない女だった、挙句に、殺されたんだ、十三の年に」
「………殺された…?」
「俺が殺した、……俺が殺したも同然の死に方だった」