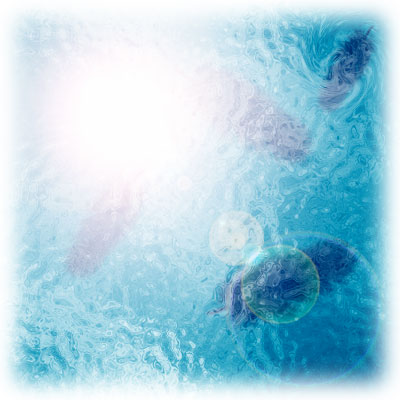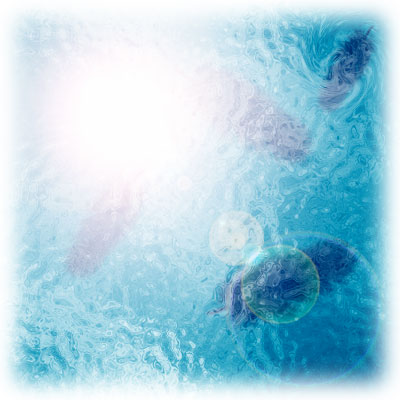一
・
「まるで海の中にいるみたいだね」
同じことを繰り返す唇を、御守は少し暖かな気持ちで見つめていた。
青い影が、時々光に揺らぎながら女の白い肌に反射している。床から天井まで一面のガラス張り、その向こうに人工の海が広がっていた。
「………わっ、すごいっ、これってエイだよ、エイ、面白い顔してるから、ね、見て見て」
はしゃぐ声、青みを帯びて輝く瞳。
「夜の水族館って初めてだよ、御守さん。静かで…誰もいなくて」
長い睫、柔らかな赤味の浮いた唇は、下唇だけがふっくらとしている。
「まるで本当に海の底にいるみたいだね……」
静かすぎる通路には二人の足音、そして影、あとは青い世界が光に彩られて広がっている。
通り過ぎる魚の群れ。それが淡い闇となって二人の身体を横切っていく。
―――海の底か、
有紀の背後をついて歩く御守の中で、ふと嫌な記憶が蘇えりかけていた。
"――私のこと……好きでしょ………?"
"――蓮……キスしよっか……"
「御守さん…?」
有紀の声で我に返った。
「どうしたの…?つまらない?」
御守が無言のままでいたせいか、明るかった相貌がかすかに翳っている。
「………ごめんなさい、私一人、子供みたいにはしゃいでるね」
しゅんとして伏せられた睫。
小さくて華奢な手がそっと御守の手に重ねられた。
たったそれだけの接触で抱き締めてやりたい衝動にかられる。
それが御守には信じられなかった。
出会ってからまだ数日。なのに――もう、こんなにも心の中に入り込まれている。
――――本当に……俺としたことが、どうかしてる、こんな子供相手に。
少し苦い気持ちで、眼を細めた。
一週間前、冷え切った車内で有紀の身体を抱き上げた時から、自分の中の欲望が明確になったような気がする。
いや――。
御守はすぐさま否定した。
最初から、そういう意味では惹かれていた。女を一目見た瞬間から、欲情していた。
それを気づきたくなくて、気づかせたくなくて、わざと距離を置いていたのかもしれない。
――――なんにしろ、俺らしくはない。
何故だろう。地位も名誉もある自分にとっては、危険すぎる恋愛ゲーム。
成り行きとはいえ、どうして――どこかで、降りるという選択ができなかったのだろうか。
「……御守さん……?」
「なんでもない」
その迷いのような疑念が、少し邪見に有紀の手を振り解かせていた。
「お前はまだ子供だろう。いくらでもはしゃげばいいじゃないか」
「子供じゃないもん……」
「大金をはたいて借り切ったんだ、そんなつまらなそうな顔をするな」
有紀の希望。
夜の水族館を借り切って、二人でデート。
そんな冗談のような望みを、叶えてやる気持ちになったのは――それもまた、ゲームの延長のつもりだったのかもしれない。
いわば、罰ゲームだ。……思いもよらない相手に心を奪われた――自分への。
「御守さんが楽しくなきゃ、私だってつまらないもん」
有紀は、きれいな唇を尖らせて不満げに呟く。
「俺も十分楽しんでいる」
「嘘……」
疑い深そうな眼。
御守は無言で、深海を擬似した青みを見つめた。
その奥に広がる魚たちの競演ではなく、澄み切ったガラスに映る美しい少女を見つめた。
自分の言葉に嘘はない。こうして――隣に立つ人形のような美貌を見つめているだけで、御守は十分楽しめていた。
透き通る肌、柔らかな髪、繊細で甘い目元と、きれいな鼻筋。
青い影に覆われた姿は、海の底で月を見上げる人魚のように寂しげに見える。
――――きれいな子だ、
御守は改めて感嘆の思いに囚われていた。
――――でも…どこかで、見た顔だ、
そんな気がするのは何故なのだろう。今まで見知った者の顔と、どこがどう似ているわけではないというのに。
一目見た時から、磨けばかなりのものになると思ってはいたが、実際は予想以上だった。
知り合いの美容師に頼み、中途半端に伸びていただけの髪をカットさせ、アッシュにカラーリングをほどこさせた。
それだけで一段と垢抜けて見える。脚も手も、爪は全てネイルケアさせて、綺麗に磨かせ、服もコートも首に掛かるクロスも全て、御守の見立てで買い与えた。
何を着せてもさまになるし、有紀は見事に着こなした。しかも、それが、どこか彼女らしくアレンジしてある。――もともとセンスはあるのだ、と御守は思った。
「御守さん、あっちに熱帯魚がいるよ、行こうよ」
当たり前のように御守の手を引き、そして無邪気に見上げる半透明の瞳。
――…可愛いな、
「御守さん…?」
「あ……いや、先に行っててくれ」
「でも」
「悪いな、電話をしなきゃいけないんだ、すぐに追いつくから」
「…………」
去っていく背中を見ながら、御守は、自分の感情に戸惑っていた。
―――莫迦じゃないのか?俺は……中学生のガキじゃあるまいし。
あんな子供に見惚れていた――そして、その感情を見抜かれるのが怖くて、先に行ってくれと、嘘までついた。
(―――あんな子供に夢中になるなんて、蓮さんらしくもない)
長瀬の言葉は、今となっては、的確な予言としか言いようがない。
いまだに肉体的なつながりがない――それが、余計にやっかいなことのように思える。
―――いっそのこと、抱くか。
そう思う。夜毎、顔をあわせる度にいつも思うし、今、この瞬間にも思っている。
そして、女もまた、それを期待して、待っているのが判る。
目で、唇で、声で、眼差しで、彼女はいつも、無意識に、そして意識的に、同居する男を誘惑している。
でも―――。
御守はあらためて、先を行く女の影を見つめた。
三月には結婚を控えている自分。その上で関係を持てば、間違いなく、この娘を傷つけることになる。
まだ、男を知らないなら、なおさらだ。
胸の深淵で、忘れていたはずの黒衣の女が微笑している。
<――――いつか……必ず罰が下るわ、私にも、……あなたにも>
御守はきつく眉根を寄せた。
もう――。
―――もう、あんな思いを誰かにさせるのは、二度とごめんだ。
二
「御守さんの、仕事してるとこ、行ってみたいな」
帰り道、有紀は楽しそうにそう言って振り返った。
「それは無理だ」
御守はそっけなく言った。まだどこかで自分の感情を持て余している。
「御守さんのベッドで、一緒に寝たいな」
「それも無理だ」
さらに冷たい口調で言った。
「……なんだか、意外だったなぁ」
少しの間、むっとしたように黙っていた有紀は、やがて肩をすくめながら呟いた。
「……いっぱい遊んでる人のように見えたのに、まるでセイジンクンシって感じだね、御守さん」
「……」
「スエゼンクワヌは武士の恥って知ってる?」
「お前、……意味判らずに言ってるだろ」
さすがに苦笑を噛み殺しながら、そう言って――ふと、記憶の底にかすめるものがあることに気がついた。
―――――まるで聖人君子だな、
数年前、それと同じ言葉を、自分は――誰かに向かって言ったことがある、それは……。
「…………」
「御守さん……?」
「……え?……ああ、何だ」
「どうしたの、怖い顔になってるけど」
記憶の底から浮き上がってきた面影が、ちらつく残像のように視界の端に見え隠れしている。
御守は首を振り、現実に隣に立つ女を見下ろした。
―――そうだ……。
その面影が鮮やかになると共に、胸の中で、はっきりとした決意が固まりつつあった。
やはり――有紀とは、一線を超えてはならない。
「……お前、男と寝たことがないだろう」
「ある……って言っても、もう信じてもらえないよね」
有紀はちらり、と舌を出した。
その横顔から眼を背け、御守は続けた。
「セックスとは麻薬に似ている。一度踏み込んでしまえば、その快感を忘れられない。言っとくが、精神的な快楽という意味だ。……男と女は、身体を繋いだ途端に、心のどこかも必ず繋がるものだからな」
「……そーなの?そうとばかりも言えないんじゃない?」
「……いや、そうだよ。……心がない行為でも、……そうだな、自分の中に、人の気持ちが入り込むっていう感覚、お前には判らないかな」
「…………」
「で、俺の気持ちの一部も、その時に持っていかれるんだ。……そういう繋がりを断つのは……結構辛いことだから」
「…………」
有紀の横顔は動かない。
自分の言った言葉に戸惑い、御守は誤魔化すように苦笑した。
「ま、そういうことだ。お前だって、三ヶ月後にほかの女と結婚する男と、そんな関係にはなりたくないだろう」
「えっ、なに?それって、御守さん、超テクニシャンってこと?」
「……………………おい」
「だって、そう聞こえるんだも〜ん」
そう言って、有紀は声をたてて愉快そうに笑った。
―――だめだ、こいつにまともな話は通じない。
御守はあきらめて歩みを速めた。
「ね、ひょっとしたら、昔、そんな風に、忘れられない快感を覚えちゃった相手がいるの?」
「……知るか」
「その人につきまとわれて、迷惑しちゃったの?それとも別れたのが辛かったの?だから、私のことも怖いんだ、ねっ、そうでしょ」
「……お喋りな口だな」
「だったら、黙らせて」
「人前だ、莫迦なことを言うな」
御守は眼を細めた。
有紀の勘の鋭さに、内心冷たいものを感じていた。
過去、たった一人だけ、自分の手でその麻薬の味を教え込んでしまった女。
彼女のことを、その言葉を、面影を、否応なしに思い出す。
犯しがたいほど美しかったあの黒衣の聖職者は、今どうしているのだろうか。
"――ずるい男…卑怯な男……。"
哀願のような声が、今も耳に残っている。
その面影に、一人の男の顔が重なる。
――――まるで、聖人君子だな。
御守がそう言って揶揄した男。
常に黒い法衣をまとい、真直ぐな目と、澄み切った眼差しを持つ男。
(―――妻になる女です)
(―――私たちは、身体ではない、心で結ばれているのです)
(―――あなたが……お姉さんを殺したと、そう思う本当の理由を教えてあげましょうか……)
「もうすぐクリスマスだねぇ」
有紀の声が、その回想を遮った。
御守ははっとして顔を上げた。
いつの間に、人通りの多い通りに出たのか、街は行き交う人の喧騒で溢れかえっていた。
街路樹を飾る色鮮やかな瞬き、賑やかな音楽がいたるところから漏れ聞こえてくる。
吐く息は凍えるほど白いのに街を行く人々の顔はどこか明るい。一足早いクリスマス気分が街並みのいたるところに溢れているからかもしれない。
車で移動することに慣れている御守には、人ごみの中を歩くことがひどく新鮮に感じられた。凍える吐息も、かじかむ指も、久しぶりに味わう感覚だった。
有紀は御守とは距離を置き、少し先に立って歩いていた。
のびやかな背中。細い足首。コートの上からでもはっきりと判る、形の良い肩と腰。
「ね、私たち、恋人同士に見えるかな」
先を歩く背中が、楽しそうに振り返る。
「さぁな」
「見えるよ、だって、御守さん、若く見えるもん、二十代でもいけるんじゃない?」
「お前が、どう見ても二十代には見えないからな」
軽口を叩きあいながら、こんなに楽しい気分になるのも――久しぶりだと思っていた。
「えーっ、じゃあ、兄妹とかかなぁ、まさか、親子には見えないよねぇ」
「見えてたまるか」
「やっぱりカップルだよ、こんなに美形カップル、なかなかいないよ、超可愛い子供が生まれそう」
―――……触れたいな、
唐突にそう思った。今ここで、触れて、壊してしまいたい。
前を行く背中が、ふいに止まった。
「ねぇ…御守さん」
交差点の手前、ひときわ賑やかな通りだった。通り過ぎる車のヘッドライトが少し距離を置いた二人を照らし、そして一瞬の後にかすめ去った。
「今さ……私があなたにお小遣いをねだったら…いくらくれる?」
有紀は、甘えたような声で言った。