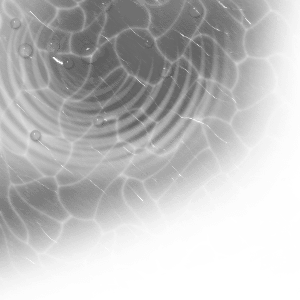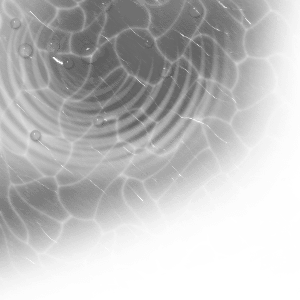――――それは四年前。
理光不動産は、グループ発足以来初めてと言っていいほど大規模な――ある巨大プロジェクトに取り組んでいた。
山陰に位置する、とある地方都市で、行政の依頼と資金を得て、ひとつの街づくりを一から計画し、三年がかりで造成することになったのだ。
過疎化が進む地方都市で、そのプロジェクトは、都市の生き残りをかけた行政の賭けでもあった。
新都市の名前は、すでに公募で決っていた。
――――「東風新都」。
当時の御守は本社の開発営業室長をしており、地方都市への強いパイプを持っていたことから、プロジェクトの担当責任者に任命された。
御守は、すぐに現地に飛んだ。
それから二年、プレハブの事務所を拠点に現地で暮らし、計画から土地買収、住民への説明から折衝まで、全ての仕事につきっきりで専従した。
有名建築家に全てのデザインを委託した、景観重視の街づくり。当時としては画期的な案は、全国的にも注目を集め、「東風新都」プロジェクトチームは、たちまち理光不動産の花形部署へと成長していった。
若かった御守は燃えた。入社して以来初めて、心血を注げる仕事に巡りあえたのだと思っていた。
寝る間も惜しんで仕事に没頭し、その都市の完成に、全てを賭けていた。
けれど――まさにその完成直前、御守はいきなり、本社企画担当専務取締役に任命されたのだ。
昇格とは言え、あまりにも唐突な人事は、当人だけでなく周囲の者も同様に驚かせた。
当時、まだ御守は二十台だった。その若さで取締役につく――それが社内に物議をかもしたのは当然で、反対の声も多かったと聞いている。
それが押し通されたのは、やはり――理光グループ会長の息子という立場の功罪なのだろう。
結局、不本意ながら、御守は現場から撤退することになった。
―――そして、リーダーの撤退と共に、プロジェクトチームも解散され、残された事業がそのまま、「理光リビングサポート」に引き継がれる事になったのだ。
当時、理光リビングサポートでは、出向した紳司が、総合企画室長に昇格したばかりだった。
そうなって、ようやく御守にも、――特例人事の、もうひとつの意味が理解できた。
端的に言ってしまえば――「花形の仕事」が、そのまま「紳司」に引き継がれたことになる。
まずは御守を取締役につけ、先便をつける。
そして紳司に実績を積ませ、いずれは取締役に就任させたいという――会長の思惑が透けて見える人事だった。
けれど、皮肉なことに、事業がリビングサポートに引き継がれた途端、街のトラブルが絶えなくなった。
トラブルは、住環境全般に広く及び、街を管理する中央管理センターのプログラムが何度も修正されたが、問題は一向に改善されなかった。
住民からの苦情が続発し、それがテレビの特集にも取り上げられたことから、マスコミの取材合戦に火がついた。
今となっては、実質グループ本社である理光不動産でも対応を検討せざるを得ないほどの――社会問題になりつつある。
それが、たった今、電話で「この件はお前に任せた」と無責任に父に投げられた課題だった。
「トラブルか……原因は、何でしょうね」
広げた書面に目を落としながら、長瀬は、眉根を寄せて呟いた。
「……水が止まる、逆流する、汚い、臭い、頻繁な停電と、……セキュリティーシステムのダウン……ひどいですね、これは」
「原因は判っている、都市の人口の問題だ」
御守は短くそう言うと、手元のファイルを閉じた。
「人口……ですか?」
それには答えず、デスクパソコンを起動させる。新しい仕事が入ったのなら、今後のスケジュールを修正しなければならない。
「長瀬、八日の帝国劇場の観劇をキャンセルしておいてくれ。その日にH市の都市計画局長に会えるようアポを頼む。それから十日には国土交通省の宮前事務官と食事の約束を取り付けてくれ」
その他の細かい指示を出し、御守は忙しく席を立った。
「……ご帰宅ですか」
「期限付きのペットを飼ってるからな、エサの時間が心配なんだ」
「……連城有紀ですか」
嘆息と共に長瀬の声が返ってくる。
御守は黙って、背後のクローゼットから上着を取り出した。この件に関して、長瀬が不安を抱いているのは知っている。
「……八日の帝劇は、マユリさんとのお約束ではなかったですか」
「仕方ない、仕事が優先だ」
そう言いながら、今、帰宅を急ぐ自分はなんなのだろう――その矛盾に気づき、思わず御守は苦笑した。
連城有紀――あの奇妙な少女と同居生活をはじめてから、すでに四日が過ぎていた。
職場の近くに買っていたマンション。その一室を彼女に貸し与え、食費だけを援助する。御守がしているのはそれだけだった。昼間の行動に関しては、一切干渉しないことにしている。
最初は、マンションごと彼女に貸し、自分は成城の実家から通勤するつもりだった。
けれど――長瀬から、連城有紀の身元に関する調査報告を受け、気持ちが変わった。
<連城有紀>の経歴は、概ね彼女が告白したことと一致していた。
後妻に入った母の連れ子として、連城家に入ったのが中学二年の終わりの頃。
そして、翌年の春にはもう家を出ている。
(――――こんな写真しか入手できませんでしたが、)
そう言って長瀬から渡されたのは、彼女の告白どおり――暴走族をしていた頃のものなのか、片隅に、白茶けた金髪、濃い化粧をした<有紀>の顔が映っている集合写真だった。
おそらく、中学の卒業写真なのだろう。
今の彼女の、透き通るような美貌は、そのどぎついメイクと髪型でかき消されてしまっている。
(―――彼女の入っていた暴走族「メリッサ」は、ただのガキの集団じゃない、実態は新興ヤクザ、松島組の下部組織です。)
報告をしている時の長瀬の声は、苦いもので満ちていた。
(―――業界でも評判の悪い組織ですよ、確かに二年前、連城有紀は、族仲間から足を洗ったようですがね、……あんなきれいな娘を、組の連中がただで抜けさせたとは思えない)
元の職業を思い出すのか、男の口調は、荒っぽいものになっていた。
(―――きれいな娘は、それだけで巨額な利益を生みますからね。最初はAVで稼がせて、厭きられれば風俗、それで稼げなくなれば、東南アジアあたりで買い手はいくらでもいる)
その凄惨な運命が――あの無防備な泣き声を上げた女に被さってくるはずだったのだと思うと――、御守は胸が悪くなった。
「蓮さん……やっかいごとを背負い込むのはあなたの悪い癖ですけどね、今度ばかりは性質が悪いかもしれませんよ」
駐車場へ向かう道中、長瀬の声が追いすがってきた。
「やくざがらみと言う訳か、ただ……あの子は、そんな風ではなかったが」
口づけにさえ震える幼い表情。御守は苦いものを噛み殺しながら呟いた。
けれど、長瀬はゆっくりと首を振る。
「女を見かけで信用してはいけません。それに、クリスマスまでというのが、腑に落ちない、ひょっとして、あの子には、何かバックがついているのかもしれない」
その声は、まだ疑心に満ちている。
「…………」
そうなのだろうか。
あの子は、間違いなく男を知らない。
むしろ御守が心配なのは、彼女が何かに追われていて――無理やり、昔の仲間に引き戻されるということだった。
むろん、そこまで心配してやる必要がないのは判っている。
が――これも、乗りかかった船というものなのか、自分のマンションで匿う女が、知らない間に何者かに連れ去られてしまっては寝覚めが悪い。
だから御守は、ここ数日、夜には欠かさずマンションに戻るようにしている。
「……なんにしても、早々に手を切ることです」
長瀬の口調は冷たかった。
「このご時世、暴力団とつながりがあると思われたら、株主総会で槍玉に挙げられる。ただでさえ蓮さんは」
言いかける男を、御守は視線で遮った。
―――私のせいで、
長瀬はそう続けようとしたのだろう。
「とにかく、松島組の件は、もう一度調べてくれ」
ポケットから携帯を取り出しながら御守は言った。仕事のメールがいくつか届いている。
「危険があるようなら連城議員に連絡して引き取ってもらう、……それが筋だろう」
「いずれにせよ、ご結婚が近いのですから」
地下の駐車場まで降りた時、長瀬は表情を変えずにそう言った。
「……少しはご自制された方がよろしいかと思います。紳司さんも、蓮さんの動きには虎視眈々と目を光らせている」
「お前が、ここまでしつこく言うのも、珍しいな」
御守はシートに身体を静め、少し眼を細めて運転席に乗り込む男の背中を見つめた。
「安心しろ、紳司の莫迦には、親父の後釜はつとまらん」
「紳司さんだけじゃない、他にもあなたの地位を蹴落とそうと目を光らせている輩は大勢いる。北條監査役などは、今だにあなたの陰口を公然と言っている」
「………本当に珍しいな」
御守はあらためて眉を上げた。従順で決して逆らわない男が、こうも一つの話題に拘泥することなど初めてだ。
「珍しいのは、蓮さんの方です」
長瀬はぶっきらぼうに言った。
やくざの内紛でコンクリート詰めにされる所を御守が金の力で救い上げたこの男は、表情は乏しいが義理だけは堅くて熱い。
元ヤクザ……というだけで、社内の者の眼は冷たいが、御守にとっては唯一信頼できる男だった。
「……あんな子供に、いつになく夢中になっている。いつもの蓮さんらしくもない。私はそれが心配なんです」
そう言うと、長瀬は軽くため息をついた。