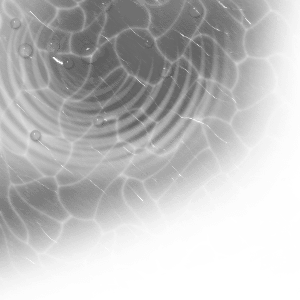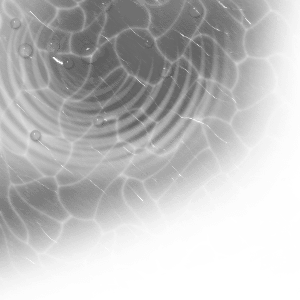一
「…その件は、もう理光リビングサポートに引き継いでいます。ええ…問題ありません」
御守蓮は、少し苛立ちながら同じ言葉を繰り返した。
立ち上がり、窓のブラインドに指を掛ける。
見慣れたオフィス街は、夜の帳に包まれていた。ネオンと、そして不夜城のようなビルの明かり。
「切りますよ、父さん。とにかく、東風新都のことは、今の俺には全く関係のない話だ」
気持ちに余裕がなくなりかけていた。
今日一日、ささいなミスばかり続いている。つまらない企画を持ってきた部下に怒声を浴びせたのも初めてのことだった。―――今朝、久しぶりにあの夢を見たせいなのかもしれない。
『まぁ、待て、蓮』
電話の向こうの声は、醒めていて厳しいままだった。
『お前が思っている以上に、市場の反応はストレートで正直だ。ことは、リビングサポートだけの問題じゃない、本社の不動産事業にも影響を及ぼしかねん』
「それは理解していますがね」
御守は辛抱強く繰り返した。
「俺は企画担当専務ですよ、苦情がらみなら、総務か営業で調整するのが筋でしょう」
『……わからんのか、蓮。それでは紳司の立場が悪くなる』
父の声からも、相当な辛抱強さが滲み出ていた。
「……紳司が、ね」
御守は肩をすくめて呟いた。
―――紳司。
その名前が、ざらついた舌に舐められたように、不快な感情を呼び覚ます。
ひとつ年下の従兄弟―――御守紳司。
中学高校大学就職と、嫌味のように自分の跡をトレースしてきた男。
実の息子の自分よりも、間違いなく父に愛されている男。
『とにかく蓮、この件はお前がなんとかしろ、紳司にはまだ、海千山千の株主連中を取りまとめられん』
「あいつは、誰よりも私の口出しを嫌いますよ」
『紳司に文句は言わさん、……確かに紳司は、お前に敵対心を燃やしているようだが、手を借りて良かったといずれ判る。これは紳司の将来のためでもあるのだから』
「……だといいんですが」
御守は嘆息した。
父の口調は、すでに、自分が引き受けることが前提になっている。いつもこうだ。この強引な父に逆らえたことは一度もない。
『今、紳司の経歴に泥でもついてみろ、取締役就任など夢のまた夢だ。頼んだぞ、蓮』
「……できるだけのことはしてみますがね」
口調が知らず重いものになっていた。
―――紳司、紳司、か……。
父の頭には、最初から従兄弟の保身のことしかないのだろう。
これ以上話し続けることに嫌気がさして、御守は電話を切ろうとした。
けれど下ろしかけた受話器の向こうで、忙しない声が響いた。
『蓮、母さんが、たまには家に顔を見せろと言っていたぞ』
「……わかってますよ」
仕方なく受話器を持ち直す。
『桜子が死んで、母さんにはお前しかいないんだ、息子としての責務を果たせ』
「………」
『とにかくこの件の始末はお前に任せた、いいな』
そう言うと電話は一方的に切れた。
「…………」
しばらく受話器を持ったまま、御守は最後に吐かれた父の言葉を逡巡していた。
息子としての責務を果たせ――それはそのまま、お前がしたことの責任を取れ、――と、言われているような気がした。
その時、軽快な電子音が、静まりかえった室内に響いた。
机の上に置きっ放しにしていた携帯電話からだと、すぐに判る。
歩み寄り、小さく震動するそれを手に取る。ウィンドウに表示された名前を見て、肩を落とした。
―――ったく、しつこいな。
そのまま、ソファに携帯電話を投げ捨て、深く嘆息した。いつもなら軽くあしらえる電話にさえ、出る気がしない。
扉を叩くノックの音がしたのは、その時だった。
「……入れ」
こんな時間まで残っているのは、秘書の長瀬涼平しかいない。
「……お電話ですが」
天井に届くのではないか、と思うほど大柄な男は、携帯電話を横目で見て、低くかすれた声で言った。
「いい、放っておけ、どうせ、愚痴と嫌味を言われるだけだ」
「……今夜のデートもキャンセルされたので」
「まぁな」
電話は、四歳年下の婚約者、本匠マユリからだった。
「少し冷たすぎるのではないでしょうか」
長瀬はソファの上の携帯電話を手に取ると、それをデスクの上に置きなおしてくれた。と、同時に、呼出音がぷつり、と途切れる。
「自分は恋人と好き勝手に遊び歩いている癖に、なんでそう俺を束縛したがるのか、……女はわからんな」
御守は、そう呟いて立ち上がった。
「長瀬、東風新都の件、お前の言う通り、結局俺がクレーム担当になりそうだ、これから少し忙しくなるぞ」
「………紳司さんの尻拭いは、いつも蓮さんがやらされますからね」
長瀬の口調に、隠しきれない苦さが滲んでいる。
御守は苦笑して、デスクの肘掛け椅子に腰掛けた。
「無能な従兄弟殿を持つと苦労する。まぁ、紳司だけの問題ではないがな。この件では、確かに俺にも、責任の一端があるんだが……」
「会長が紳司さんに甘すぎるんです。……判りませんね、どうしてあの厳しい会長が、紳司さんのような無能な男を可愛がるのか」
「………」
眼をすがめ、御守は口元から笑みを消した。
「……紳司は、死んだ祖母の若い頃によく似ている。親父も、顔を見ればどうしても甘くなってしまうんだろう」
そう言いながら、――何を言い訳してるんだ、俺は、と思っていた。
そんな回りくどい言い方をしなくても、もっと端的な理由がある。
父である御守省吾が、どうして実子である自分より、甥にあたる紳司を可愛がるのか――思いつくことはひとつで、それは多分正解だった。
「……息子としての、責務か」
「え?」
「いや、なんでもない」
御守は軽く嘆息し、長瀬にコーヒーを持ってくるよう促した。
夜のオフィス。
理光不動産本社ビルの十一階。役員専用の二十畳余りの執務室の中だった。
御守は、ふと気が付いて立ち上がると、奥にある映写室の扉を開けた。
企画担当専務という役職上、専務室で簡単なプレゼンをさせることも少なくない。映写室はそのために設けさせた部屋だったが、多忙の時は仮眠室に早代わりする。
「長瀬、これをクリーニングに出しておいてくれ」
芳香と共に戻ってきた忠実な秘書に、御守は映写室から引き上げてきたスーツを示した。
昨夜行われたレセプションパーティーで使用したイタリア製のドレススーツ。パーティー終了後にこの部屋で着替えを済ませていたため、そのまま映写室にかけてあったものだ。
「わかりました」
デスクにコーヒーカップを置くと、長瀬は慣れた手つきでスーツを手に取る。
「悪いな、いつも雑用ばかりやらせてしまう」
「構いませんよ、それが秘書の仕事ですから」
長瀬は、御守が特別に雇った私設秘書で、正式な理光の社員ではない。
会社がつけてくれた秘書は何人かいるが、御守は極力、自分の周囲から余計な人間を遠ざけるように努めていた。
派閥争いの激しい、腹黒い役員たちがひしめく本社内。ここでは、他人を不用意に信用することは命取りになりかねない。
「それにしても、やっかいだな」
長瀬が持ってきてくれたエスプレッソを口にしながら、御守はみけんに
皺を寄せて呟いた。
従兄弟の御守紳司が総合企画室長をしている株式会社理光リビングサポート。
理光不動産の関連企業で、形態としては独立会社だが、実態は子会社に等しい。
そして、この会社が、今――――空前のマスコミ攻勢にあっているのだ。
理光リビングサポートは、主としてマンションの管理、セキュリティーを担当する会社だった。理光不動産が造成、買収、売却したマンション、建物は、全て後日リビングサポートに引き継がれ、同社が管理するシステムになっている。
「東風新都か……」
御守は呟き、デスクの上で広げたままになっているファイルを手にした。
多分――、有紀が見たと言ったのは、あの街のことだろう。
「今さら、俺がかかわることになるとはな」
思い出したくもない過去、行きたくもない街。
東風新都。
御守は薄く眼をすがめ、当時のことを思い出していた。