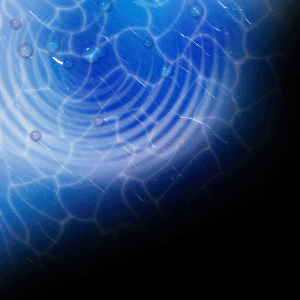第二部
―――乾いた唇が降りてきて、そっと触れて静かに離れた。
「…………」
離れた後に、初めて羞恥心が膨らんだ。
指で触れた唇が濡れている。それがひどくいけないことのように感じられた。
「―――私のこと……好きでしょ……?」
覆い被さっている女、少しかすれて、囁く声。
薄い水着越しの胸、その膨らみが目の前にある。激しい動悸で、眩暈がしそうだった。
「好きなわけないだろ」
思わず叫んで、跳ね起きていた。
起きると同時に、口の中に溜まった唾液を吐き出す。苦いような味覚を感じるのは、口づけされた後ろめたさからくる――錯覚なのだろうか。
ビーチパラソルの下を抜け出し、熱く焼けた砂浜を素足で蹴った。
「――ついて来んな」
振り返らずに、そう叫ぶ。
「いけない、駄目!待って、……待ちなさい!」
追いすがる声。それを振り切るようにして走り、水しぶきをあげて海水へ身体を沈めた。
「お前なんか、大嫌いだ!」
泳ぎは昔から得意だった。そして、追って来る女があまり得意でないことも知っていた。
――――ちくしょう……莫迦な真似しやがって、
水を掻きながら、悔しくて涙が滲んだ。
その思いを振り切るように、深く――深く、息が続く限り深く潜った。
青緑の深海の果て。
ふと顔を上げると、頭上に、揺らぐような人影が見える。
あの人が――追いついたのだろうか、ついてきたのだろうか、こんな深くまで?泳ぎの苦手なあの人が?
その時、細かな気泡が突然足元で弾けた。それは勢いよく立ち上り、視界一面に広がっていった。
頭上にたゆたう人影が蠢く。
こちらに向かって伸ばされる腕、海草のようにうねる黒髪。認識できたのはそれだけで――それは、人というよりは、海に棲む人外の生物に見えた。
―――人魚……?
その姿が、泡に飲み込まれるようにして、視界から消えていく。
追おうとした。なのに、身体が動かない。
手も、足も、しびれたように動かない。
酸欠のせいなのか、眠りに落ちる前のように、意識が朦朧となりかけている。
全身の力が抜けかけた時、ふわり、と身体が持ち上がるのが判った。
海流に抱かれるように押し上げられ、そのまま水面へ弾き出される。
「……っはぁっ」
激しく呼吸し、まだ重く痺れる両腕を使い、必死になって水を掻いた。
砂浜には誰もいない。
投げ出されたビーチサンダル。あの人の――履いていたサンダル。
当然出てくるはずの、もう一人の顔は、いつまでたっても海面に浮かんでは来ない。
時間だけが――虚しく、冷酷に過ぎていく。
誰かの声がする。幻聴のように耳元で響く。それは父親の声だった。
――――蓮!……蓮、しっかりしろ、眼を覚ませ!
} -->