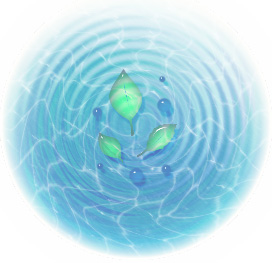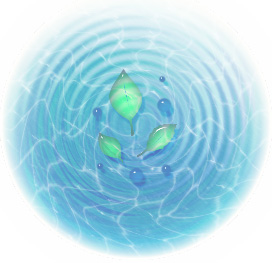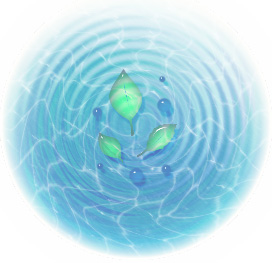六
ホテルの最上階にある部屋に連れて行かれた時には、もう十時を大きく回っていた。
さすがに少し眠たかった。
夕方からずっとプールにいたから――疲労と、そして、ずっと続いている緊張のせいかもしれない。
けれど、ほの暗い照明の下、手を伸ばせば触れるほどの距離で、長身の男と向き合った時、そのわずかな眠気すら、吹き飛んでしまっていた。
これから自分の身体に起きること――それを想像するだけで、胸苦しいほどの動悸を感じる。
御守は横顔を向けたまま、静かに自分の上着を脱いだ。
逞しい肩の筋肉が、上質のシャツを通してはっきりと透けて見える。想像したとおりだった、決して痩せているだけの身体ではない。
――――どうしよう。
ドキドキしながら、有紀は待った。
――――私、自分で服を脱いでもいいのかな、この人に脱がされるのを待たないといけないのかな。
御守は何も言わない。ネクタイを外す指。関節は無骨なのに、バランスの取れたその長さが意外なほど綺麗に見える。
「来い」
ようやくこちらを向いてくれた男の手が、ゆっくりと伸ばされる。その手には、外したばかりのネクタイが絡んでいる。
有紀は、棒のように立ちすくんだまま、指に絡まるネクタイだけを見続けていた。動けなかった。
男の声に、苛立ちが混じる。
「何をぐすぐずしてる、お前が言い出したことだろう」
「べ、別に……」
「それとも、怖気づいたのか、やめるなら今のうちだぞ」
「………」
その言われ方にむっとして、睨むように前に足を踏み出した。
肩を抱かれ、男の香りに包み込まれる。
御守の指が、ベルベットの上着を脱がせはじめる。近づく髪から、指から、かすかに甘い香りがする。
「背は……あまり高くはないんだな」
「百五十七……くらい」
上着が柔らかく床に落ちる。
有紀は震える目蓋を閉じた。
「もう五センチ伸びれば、俺の理想だ」
「クリスマスまでに伸ばすよ」
「面白いことを言うな」
上着一枚脱がせたきり、男は何故か、そのまま動こうとしなかった。
緊張で足が震える。こんな、突き放したような状態で立たせていないで、早くどうにかして欲しい。
「痩せているようで……水泳をしているだけはあるな、綺麗な骨格をしている」
煽るような声が頭上で響いた。
「首から肩が特にいい。……腰もよく締まっている、そそられるな……」
「………スケベ」
「言っておくが、何をされても文句は言うなよ、お前は俺に、金で買われた女なんだからな」
「何をされてもって……、何するつもりなの?」
ふいに冷たくなった男の口調。不安に駆られて顔を上げた途端、ネクタイを首に回された。
「や、やだ、何するの」
驚いて後ずさった。その弾みでバランスを崩し、そのまま背後に腰をつく。そこは、もう柔らかなべッドだった。
「最終テストだ」
御守は冷たく言うと、ゆっくりとベッドの上に膝をつき、仰向けに倒れた有紀の上に被さってきた。
「……テスト……?」
自分の声が、無様なほど震えている。
「心配するな、首を締めるとでも思ったのか?」
その声に、愉快そうな笑みが滲んでいる。
「もっとも、そういう趣味の奴もいるがな。……俺はやったことがないが、お前で試してみてもいいな」
「…………」
男の指が、首に掛かったままのネクタイをすくい上げる。それが視界を塞いだ時、ようやく有紀にも、御守の意図がはっきりと判った。
「……どうするつもり……?」
返事はない。
目元を覆われ、頭の後ろで、ネクタイがきつく結ばれる。
被さってくる男の重み。息遣いと、そして香りだけが、感じられる全てになる。
膨れ上がる不安の中、今度は身体を横向きにさせられ、両腕を後ろにもっていかれた。
「……御守さん……?」
両手首を同じように、タオルのようなもので拘束されて、有紀ははじめて恐怖を感じた。
怖い、――――ドキドキして、心臓が壊れてしまいそうだ。
「ねぇ、……テストって何?何をすればいいの」
その問いに、答えてくれる声はない。
身体に触れていた指と、彼の香りがすうっと消える。
―――御守さん……?
わずかな間をおいて、唐突に視野全体が暗くなった。
照明を全て落としたのだとすぐに判った。――何も、見えない。暗黒の世界にたった一人取り残されたような不安が広がる。
「御守さん?」
焦燥にかられ、有紀は叫んだ。
「――御守さん、どこにいるの?」
怖い、身体の自由さえ利かない、真っ暗な世界。自分がどこにいて、誰といるかさえ判らない。
「今から、君を抱くのは俺ではない」
距離感の掴めない声がした。
声の先を求め、有紀はもどかしく首をめぐらせた。
「俺はそれを見物させてもらう。君の反応、声…ひとつひとつ、あますところなく、じっくりと見させてもらう」
「何言ってんの……?……冗談でしょう?」
有紀は首を振る。―――そんなの、絶対に嫌だ。
「相手をするのは、先ほど車を運転していた男だ。彼はヤクザあがりのボディーガードで、逆らえば、痛い目に合うのは君の方だから、大人しくした方がいい」
有紀は息を引いた。
あの冷たい眼をした人相の悪い男、長瀬と呼ばれた男のことを言っているのだ。
―――冗談じゃない。
身体を反転させ、膝をついて立ち上がろうとした。けれど両手が使えない上、距離感が全くつかめない。バランスがとれず、そのまま再びベッドの上で転倒する。
「……お前がいずれ、あさましく私につきまとわないとも限らない。私も得体の知れない相手を、無防備に身近には置いておけないからな。安心しろ、撮影したテープは用が済めば返してやる」
―――テープ?撮影って……、何のこと?
「口止めだよ、……女は口が軽いからやっかいだ」
「待って、御守さんっ」
「余り、大人をなめるもんじゃない、一度は痛い目にあってみろ」
それを最後に、声さえも聞こえなくなった。
扉がわずかに軋む音。そしてゆるやかに閉まる音が、ひそやかに響く。
「………御守さん?」
有紀は半身を起こすと、羞恥すら忘れて子供のように叫んだ。
「いやだ………いやだよ、そんなの嫌だ、出てきてよ、御守さん!」
真っ暗な視界。身動きの取れない腕。恐怖と不安で胸がつぶれそうになる。
「金が欲しいんだろう?だったら、それも愛人の仕事のうちだ、せいぜい私を楽しませてみろ」
突き放したような声が、ひどく遠くから聞こえた気がした。
「……やだ…、」
逃れようと、縛られた腕に力をこめた。ゆるく結ばれているだけなのに、それは有紀が力を入れれば入れるだけきつく手首に絡みつく。
―――そんなの、嫌だ。
腕の戒めを解くのをあきらめ、感覚と勘を頼りにベッドからそろそろと脚を下ろした。柔らかな絨毯につまさきが触れ、ようやく立ち上がることができた。
何も見えない。方向の感覚さえ乏しくなりそうな闇の世界。ただ聴覚と嗅覚だけがひどく敏感になっている。
何かが、軋むような音が聞こえたのはその時だった。
有紀は身体を硬直させた。
柔らかな絨毯を踏んで、確かに人が近づいて来る気配がする。
「………っ」
気配の方を振り返り、それから慌てて逃れようとした。
やみくもに身体を逸らした途端、肩が何かにぶつかった。鼻先をよぎる風と鈍い音。驚いて息を呑んだ瞬間、背中から肩を抱かれていた。
「やっ…だぁっ」
有紀は驚愕して暴れた。肩を反らし脚を無作法に振り回した。けれど次の瞬間、身体がふわっと浮き上がり、かすかな息遣いが頬にかかるのが判った。
抱き上げられている。その自覚もないままに、ただもがいた。
「いやだ、離せっ、離せ、馬鹿っ、ひとでなしっ」
抱き上げる腕はひるまない。
―――うわっ、
そして唐突に浮き上がるような――放り出されるような感覚がした。
有紀は背中から柔らかなスプリングの上に落ちていた。それが先ほど、やっとの思いで脱出したベッドの上なのだとすぐに判った。
「やっ……」
即座に身体を反転させ、膝で這って逃れようとする。頭が壁にぶつかり、すぐに身動きが取れなくなった。肩で息をしながら振り返る。
「来ないで、」
ベッドが、別の人間の重みで軋む。
「………やだ…」
あとずさる。さらに軋むスプリング。
確かに何かが近寄ってくる気配。
空気から伝わる体温。
両肩を柔らかく掴まれた時には、もう、恐ろしさと緊張で、その力に刃向かうことさえできなくなっていた。
ゆっくりと仰向けに倒されて、そのまま覆い被さる圧力に飲み込まれる。
羞恥と恐怖と不快感で、閉じた眼から涙が滲み、眼を覆うネクタイに吸い込まれた。
恥もプライドも何もかも忘れ、有紀は叫んだ。
「御守さんっ、いやだっ…助けてよっ、御守さん、いやぁっ」
あとはもう止まらなかった。堪えることもできないまま、ベッドに顔を押し付けて号泣した。
どれくらい泣いたのか――身体を拘束する力が、気がつけばなくなっている。
「………?」
そのまま、急速に抱き起こされ、暖かな腕に包まれた気がした。
―――え……?
「お前、……本当に十八か?」
呆れたような声が耳元で響く。
―――御守さん……?
有紀は驚いて顔を上げようとした。
それをゆるく抱きとめられ、そのまま背中に回された男の手が、拘束していた戒めを解いてくれた。
「なんて泣き方をする、まるで子供をいじめてるような気分になった、莫迦、今言った事は全部嘘だ」
有紀は歓喜して顔を上げた。間違いなく、それは御守の声だった。
緊張していたとはいえ、どうして判らなかったのだろう。その香りも、腕の温みも、判ってしまえば最初から、彼以外の誰のものでもなかったのに。
目を覆うネクタイが外される。
見下ろす男の顔には、初めて見るような――何かの感情の欠片が浮かんでいた。
「これに懲りたら、誰かの愛人になるなんて安易な考えは、もうやめておくんだな」
―――御守さん………。
「金持ちがみんな、まともな人間だとは限らない、薬やヤクザがらみで、身動きできなくなることもある、そうなる前に、大人しく家に帰って」
有紀は、目の前にある男の身体に抱きついた。
「……おい」
安堵して、堪えていたものが急激に膨らんだ。涙があふれ、嗚咽が喉を震わせる。
「御守さん………」
「お前、俺の話、聞いてたか」
無言でうなずく、何度もうなずく。その度に、新しい涙が頬を伝った。
「……怖かったから………」
御守の手が背中に添えられている。
温みがあって乾いた手の平が、なだめるように背中を撫でてくれている。それだけのことが、不思議なくらい嬉しかった。
涙が溢れて止まらない。それは頬に落ちる前に男のシャツに吸い込まれていく。
「本当に…怖かったから………」
有紀はもう一度繰り返した。
「……俺なら、怖くないのか」
耳元で、低く呟く声がした。咄嗟に強くうなずいた。
「何故だ?……なんだかお前がわからなくなった」
その声に、初めて聞くような戸惑いの色が滲んでいる。
「あなたじゃなきゃ、嫌なんだ」
「判らないな、ただ金が欲しいだけなんだろう? お前は、俺が駄目ならほかを探すと」
男の言葉を、有紀は強く首を振って否定した。
「――あなたじゃなきゃ、嫌なんだ」
「どうして」
「――好きだから……」
「…………」
「あなたが、……好きなんだ、今判った、私……あなたが、好きなんだ」
「……あのな、俺たちが会ってから、まだ」
男の言葉も、そこで途切れた。
「…………」
「…………」
一瞬の沈黙。
ふいに、御守の腕に、肩を抱かれて引き離された。
「みか……」
何か言いかけた唇を、柔らかく、暖かいキスで塞がれる。
車で受けたキスと――同じ感覚。
今度は眼を閉じていた。
「………合格だ」
低い囁き。
「ん……」
「いいな、もうお前は俺のものだということだ」
「…んっ……」
わずかに離れて、そして角度を変えてもう一度口づけが贈られた。
「や……っ」
有紀は顔を反らしていた。
「どうした、俺が好きだと言ったのは嘘か」
「た、だって」
「だって何だ」
車の中で初めて唇を重ねられた時も驚愕した。だって――キスって、
「………キスって、口くっつけるだけだと思ってたから……」
「………」
どこか呆けたような沈黙があった。
「お前……」
その顔を見上げる前に、肩を抱かれ、広い胸元に引き寄せられていた。
「御守……さん?」
「……もういい………、莫迦莫迦しい……俺としたことが」
一人ごとのような声だった。
でも、初めて聞くような楽しげな声でもあった。
「私………愛人なったんじゃないの?」
少し不安にかられて聞いてみた。御守の声が初めて優しいものになる。
「愛人じゃなくていい」
「でも、」
「クリスマスまでは面倒みてやる、ただし、こんな真似は俺で最後にしろよ」
「…………」
肩を抱く腕が離れ、そのまま、ぽん、と頭を叩かれる。
「……たまには、子供の遊びにつきあってもいい、そんな気になっただけだ」