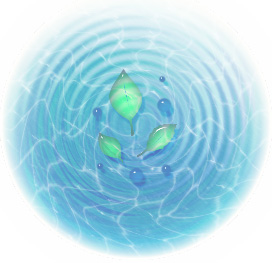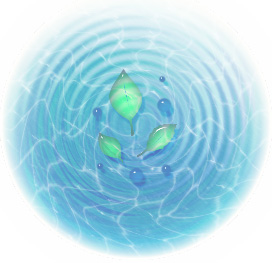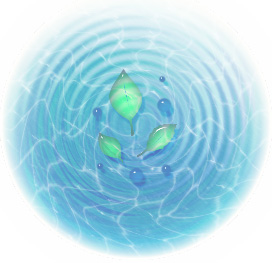四
車が滑り込んだのは、都心にある国際的にも有名な高級ホテルだった。
行き交う制服姿の従業員たちは、業界一の実績を誇る不動産会社の若い専務をよく知っているのか、御守の顔を見ただけで即座に一礼し、先回りでもするように、慇懃に先導してくれる。
「……あの」
「おどおどするな、もうテストは始まってるぞ」
御守はそれだけ言うと、後は振り返りもせずに、足早に歩を進めた。
有紀も慌ててその後を追う。
ロビーの床は柔らかな絨毯張りで、靴を履いてあがるのが気詰まりなほどだった。クラッシックなメロディとアロマの香り。
先を行く御守のまっすぐな背中を追いながら、心細さだけが募っていく。
「どこに……行くの?」
「その服をなんとかしてやろう、さすがに恥ずかしくて、食事にも連れて行けない」
男が向かっているのは、海外ブランド店が並ぶ、ホテル内のショッピングスペースのようだった。
「……って、今から?」
その質問に、答えてくれる声はない。
午後九時前。通り過ぎるどの店も、入り口は固く閉ざされ、ウィンドウ越しに仄かな照明が灯っている。
けれど御守が当然のように入った最奥の店だけは――まだ開店中の明るさが残っており、異国の面立ちがはっきりと判る店員たちが、にこやかに二人を出迎えてくれた。
「さっき長瀬さんから、連絡がありました、この子かしら?」
流暢な日本語で即座に歩み寄ってきてくれたのは、銀の髪を腰まで垂らした、痩身碧眼の女性だった。
「まぁ、可愛いお嬢さんだこと、……おいくつ?あなた」
有紀は無言で、顔をそむけた。
気のせいかもしれないが、その女の声に、目に、まるで挑発するような悪意の欠片を感じるのは何故だろう。
「悪いな、適当に見繕ってやってくれ」
御守は短くそう言うと、ようやく有紀を振り返った。
見下ろす顔の表情は読みにくい。怜悧で、そして醒めた眼差し。
「言っておくが、今はまだ、仮契約だ」
抑揚のないビジネスマンの口調。
「本契約の前に、じっくりと見極めさせてもらう、悪いが俺は、顔も頭も洗練された人間しか、身近には置かない主義なんでね」
有紀が何か言いかける前に、その形良い背中はさっさと店を出て行ってしまった。
―――ひどい……待っててくれてもいいのに。
心細いにもほどがあるが、今更逃げ出すわけにはいかない。
事前に連絡を受けていたせいか、店員たちの対応は丁寧でスピーディだった。
有紀の身体からアンダーウェアも含めた全てが取り払われ、代わりに新しいものが与えられる。
ベルベットのショートコートにグレンチェックの膝丈スカート、エナメルのイブニングシューズ。店員たちの説明によると、それらは全て、イタリア製の高級ブランドで――この冬、届いたばかりの新作、ということだった。
「君は本当に可愛いね」
靴を履かせてくれた店員から、すれ違いざま、囁くように声をかけられた。
まだ若く、髪と肌の色素が薄い、綺麗な指を持った青年だった。
碧の宝石を思わせる瞳が、熱っぽく見下ろしている。
「御守専務の新しい玩具だろう?……今度、よかったらプライベートで僕と会わない?」
「考えとくわ」
有紀は曖昧な微笑を返した。
「気をつけて」
彼は他の店員の目をはばかるようにして、さらに耳元に唇を近づけてきた。
「御守専務は燃えやすくあきっぽい人だと聞いているよ、……今までだって何人かここへ連れて来ているし、うちのオーナーも」
彼は横目で、レジに立つ背の高い女性を示した。
最初に有紀に声をかけてくれた、銀色の髪と深緑の眼を持つ女性だった。
「彼の愛人の一人だからね、……あまり、深入りしない内に手を引いた方がいいと思うよ」
――――ふぅん……。
わずかな腹立たしさを覚えながら、有紀は足早に青年の傍を離れた。
――――勝手なヤツ、人には説教じみたこと言って、自分は好き勝手なことやってんじゃん。
着替えが終わり、促されるように店の外に出ると、腕組みをして立っていたのは御守ではなく、車を運転していた長瀬という男だった。
彼は、まるで別人のようにドレスアップした有紀を見ても、顔色ひとつ変えないまま姿勢を正した。
「専務が上でお待ちになっておられます、こちらへ」
普通に見つめられるだけで、怖いような男だと思った。
少し遅れてその後を歩きながら、有紀はさりげなく彼の指を見る。もしかして小指がないのかもしれない――そんなことまで思えてしまう。
長瀬は無言のままだった。何が気に入らないのか、ずっと怒ったような顔をして、その表情を崩そうともしない。
エレベーターに乗ると、二人きりの密室は、想像以上に気詰まりだった。
沈黙よりも、喋っている方がマシかもしれない。有紀は思い切って、男を見上げ、聞いてみた。
「長瀬さんって、……御守さんの運転手をしてるの?」
「それ以外にも、色々雑用をやらせていただいております」
抑揚のない低い声は、丁寧なのに冷たく感じられる。
「ずっと、今の仕事をしているの……?」
長瀬の横顔は変わらなかったが、その質問には応えてもらえなかった。
五
エレベーターが停まったのは二十三階。
連れて行かれたのは、テレビなどで名を馳せたシェフが料理長を勤めているという――有紀でもその名を聞いたことがあるくらい、高名なフランス料理店だった。
長瀬と入り口で別れ、ボーイに窓際のボックス席まで案内され――ようやく有紀は、先ほど別れた男と再会することができていた。
「みか……」
思わず手を振りかけて、呼びかけた彼の名前を飲み込んだ。
ボーイの肩越しに見えた御守は、夜景を一望できるテーブルに一人、腰掛けていた。
所在無く椅子に背を預け、グラスを指に絡めたまま、彼は遠くを見つめている。
視線だけは、ガラスの向こうに広がる夜景を見ている。けれど有紀には、彼の眼が――何か別の、ここにはないものを追っているように、ふと、思えた。
その横顔が場違いに寂しげで――さきほど感じた腹立たしささえ忘れ、気がつくと、彼を楽しませたいという気持ちでいっぱいになっていた。
「み〜かみさんっ」
慇懃に椅子を引くボーイを無視して、有紀は御守の背後に駆け寄った。
「どう?」
立ったまま、くるりと一回転してみる。柔らかなスカートとコートが、花のように広がって揺れる。「変身って感じ?」
ようやく顔を上げた御守は、わずかに眉をあげただけだった。
感嘆なのか、失望なのか。その表情からは読み取れない。
「こんなに気持ちのいい服を着たの、私、生まれて初めてだよ」
「生地がいいんだろう」
「そうだね、でも……このコート、もう少し丈を短くして、それからスパンコールをつけたら、割と着まわしがきくと思うんだけど」
御守の目がわずかに細まる。
有紀は慌てて付け加えた。
「別にこれが不満とかじゃなくて、……私さ、古着のリメイクが得意なんだ。ううん、これは古着じゃないんだけど……つい、色々考えちゃうんだ、私ならこうアレンジするって」
「……いいとこのお嬢のくせに、変わった趣味をしているんだな」
座れ、と御守の目が言っている。
有紀は、ボーイが引いてくれた椅子に腰を下ろした。
正面から、男の眼が見つめている。やはり――どこか、値踏みするような醒めた視線で。そう思うと、自然にうつむきがちになってしまう。
「裕福な家の子供にしては、ひどいボロを着ていたな」
御守はそう言い、ようやく視線を逸らしてくれた。そして、グラスの液体を嚥下する。
少しむくれて有紀は答えた。
「わかってないなぁ、それがイマドキのファッションってものなの」
「悪くはないが、ただ、俺は好きじゃない」
「こんな服が好み?見たいのは服だけ?」
「センスのない女は嫌いだ、着こなしで、その女の素質が判る。まぁ……お前は、中の上くらいか」
低い声が淡々と呟く。
有紀の胸に、まるでこれからオークションにでもかけられるような、不快な気持ちが、じんわりと広がった。
「……随分回りくどいんだね、すぐに部屋に行くと思ってたのに」
「悪いな、この年になると、性欲より食欲なんだ」
―――この子にも、私と同じものを。
そう言ってボーイを下がらせ、御守はかすかに眼を細めた。
きれいな目―――、有紀は思った。冷たそうなのに、間近で見ると、どうしても寂しそうに見える、……何故だろう。
若いのか、老成しているのか、その顔だちからは掴みきれない。
「御守さんの年って……いくつ」
「詮索しないってのは、お前が言い出した条件だろう」
そっけない声が返ってくる。
「…………」
有紀は黙って、目の前に並べられたグラスの中から深赤の液体を選んで持ち上げた。
少し唇をつけてみる。――苦い、あまり美味しいものじゃないな、そう思いながら、一口、二口嚥下した。
喉が熱くなって、たちまちむせる。
「無理するな、アルコールには慣れていないのか」
「好きじゃないだけ」
御守は笑わない。有紀は不思議に思った。彼の表情は出会ってから一度も崩れない。
その崩れない顔のまま、男は唐突に呟いた。
「……で、本当の年はいくつなんだ」
「え、」
「オードブルでございます」
二人の会話を、ボーイの優しげな声が遮った。
前菜が並べられる。贅沢で上品なプレート。生ハムとグレープフルーツだけがかろうじて確認できた。食欲は余りない、緊張しているのと――着せてもらった服を汚すのが怖いから。
給仕が去った後、御守は再度口を開いた。
「……嘘はたいがいにしておけ、お前は『連城有紀』じゃないだろう。本物の彼女なら、この程度のホテルに怖気づいたり、ブランド物の服でいちいち感激したりはしないはずだ」
有紀は口ごもり、そして、うつむいて、上目遣いに男を睨んだ。
「…………嘘つき」
「何?」
男の眉が、意外そうに上がる。
「何も知らないふりしてて、最初からちゃんと調べてたんじゃん」
「何が嘘つきだ、嘘をついているのはお前だろう」
「……だって、詮索しないって約束したのに」
「……あのな、お前、他人のカードを持ち歩くのは犯罪なんだぞ、判ってるのか」
「………他人じゃないよ」
グレープフルーツの果肉を見つめながら、有紀は呟いた。
「そこまで判ってるなら、もっと調べてみたら?……連城家には、後妻に入った継母の連れ子がいるの。―――連城有紀の戸籍上の妹、それが私」
「……本当の名前と年を言ってみろ」
「……十八……名前は、ユキ」
何か言いかけた御守を、有紀は、視線だけで強く制した。
「偶然だけど、同じ名前なの。漢字も同じ。……皮肉だよね、できのいいサラブレッドのお嬢様と、こんな私がさ、名前だけが一緒なんて、笑っちゃうでしょ」
「……別に、笑えるような話でもないが」
御守は、眉を寄せたままで嘆息する。
有紀は再びうつむいて、囁くような声で続けた。
「……家出したのが、十五の年……中学出てすぐ。族にも入ってたし、何度も補導されたし……家族もやっかい払いが出来たとしか思ってなかったと思う。……誰も、探してもくれないから。で、家出るとき、盗んできたのが」
有紀は、両手の指で、四角いカードの形を作って見せた。
「限度額が月二十万、……ずっと使ってるし、それは家族も知ってるはずだけど、まだ解約されてないから……きっと、生活費を援助してるつもりなんだと思うことにした」
「……ふぅん」
「で、そのカードの期限……明日で切れるの、明日から私、どうやって生きてけばいいと思う?」
「家に戻るんだな」
男の声は冷淡だった。
「……私って、綺麗でしょ」
有紀は顔をあげ、冗談めかした笑顔を見せた。
「だからね、愛人やってみることにしたの。どう?しばらく、私を囲って見ない?」
御守はそれには答えず、フォークとナイフを手に取った。
彼が何も言おうとしないので、有紀も仕方なくそれに習う。
「俺が駄目なら、ほかを探すのか」
スープが下げられた時、ようやく男は口を開いた。
有紀は、手にしていたスプーンを所在無く弄びながら、曖昧に頷く。
「……ほかに、お金稼ぐ方法ないもん。……フーゾクとかって面倒そうだし」
「………」
かすかなため息が、男の唇から零れ落ちた。
「……じゃあ、条件を言ってみろ、身体を提供する見返りに、何が欲しいんだ」
「……ああ…うん、とりあえず、住むところと、……お金かな」
「お前は最初、期限付きの愛人になりたいと言ったな、それはどういう意味なんだ」
「……クリスマスには、……戻らないといけないから」
「何処へ」
「…………」
有紀は黙った。
しばらくその沈黙につきあっていた御守は、やがて諦めたように視線を逸らした。
「要は、行く当てがあるということなんだな、クリスマスには」
「……そういうことかな、……女の子には忙しいシーズンだから」
「稼いだ金で、彼氏と楽しく過ごすというわけか」
ばかにしたような口調だった。
「……そんなとこかもね」
有紀は曖昧に笑んだ。
「それで?…いくら欲しいんだ」
「お金は…そうだね」
有紀は言いよどんだ。そしてかすかに笑った。
「後で考えるよ、いくら吹っかけるか判らないから覚悟しておして」
「なるほどね……」
呟いた御守の眼に、初めてあるかなきかの笑みが滲んだ気がした。