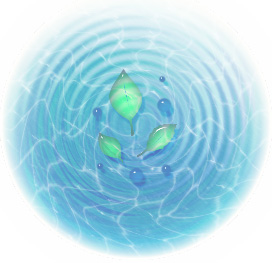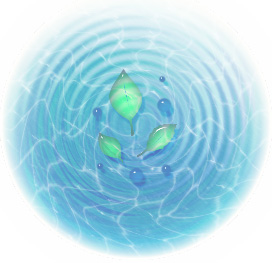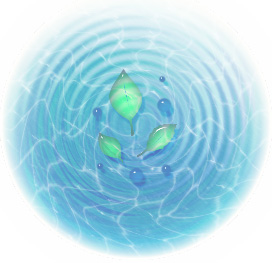二
水の中にいるのは好きだ。……地上の雑音が届かない世界。
有紀は水中に沈み込んだまま、仰向けになって眼を開けた。
水面の揺らぎ。透けて見える照明の光彩。―――もっと深く、もっと深みに沈んで行きたい。
眼を閉じて――そのまま手足の力を抜いてみる。
けれど気持ちとは逆に、ゆっくりと浮遊していく身体。
ぱしゃん、と腕で水を掻き、有紀は水面に顔を出した。
水曜日の午後八時少し前。定休日の私営屋内プール。
この時間はスイミングクラブの登録選手だけが特別に利用することが許されている。
水面には有紀以外にもいくつかのスイミングキャップが見え隠れしていた。
「よう、久しぶりに見る顔だな」
すうっと、少し離れた水面から顔を出す男。彼はゴーグルを外し、日焼けした顔をほころばせた。
「そうだったっけ?」
有紀はわざとそっけなく答え、そして、からかうような眼差しで男を見上げる。
男は逞しい腕で水を掻き、ワンストローク分距離を縮めた。
有紀は、すうっと後退する。近づいた距離だけ、後ろに下がる。
水に濡れた彼の端正な顔に、苦い笑みがかすかに滲んだ。
「相変わらずつれないな、こっちにいるなら、たまには俺の部屋に来いよ」
「どうして?」
「どうしてって」
何か言いかけたその顔めがけて、有紀は、思い切りよく、水を跳ね飛ばした。
「っ……て」
ふいをつかれた男は、戸惑ったように瞬きを繰り返す。その顔が可笑しくて、思わず声をたてて笑っていた。
「部屋に行ってどうするの?また、こないだみたいに押し倒すつもり?」
「……その続きがしたいんだよ」
三鷹庸介。五十メートル背泳ぎでは、中学時代から名を馳せている男。 このクラブでアテネを目指せる、ただ一人のスプリンター。
有紀より五つも年上のこの男は、最近は露骨な欲望を隠そうともしない。
「前も言ったけど、二度と許さない。今度同じことしたら、絶交だからね」
有紀はそう言うと、男から逃げる様に水に潜った。
三鷹も後に続き、すぐに隣に追いつかれる。
きれいなフォームで水を掻く腕。三角筋から上腕筋群にかけてスムースな筋肉がついている――スイマーとして理想的で、しなやかで美しい筋肉の流れ。
三鷹の思いを受け流し続けている有紀も、彼の研ぎ澄まされた肉体を見るのは好きだった。
水中で、三鷹の腕が有紀を捉えようとする。それをすり抜け、水を蹴って水面に逃れた。
「三鷹さん、ふざけてる暇あるの」
からかい混じりの声をかけると、すぐに三鷹も顔を上げ、立ち泳ぎに切り替えた。
「あまり、ねぇよ」
男は苦く笑い、ぶっきらぼうに水を掻いた。日本選手権が近いのだ。だから今も、一人で練習していたのだろう。
「……あれ、お前の知り合い?」
その三鷹が、あごでプールサイドを指し示した。
有紀は顔を上げた。
―――ああ……。
視線の先で、ガラス張りの壁面に寄りかかるようにして、長身の男が立っていた。
「どういう神経?プールにスーツなんて、ぞっとしねぇな」
三鷹は顔をしかめている。
「そうだね」
―――すてきな人……。
言葉とは裏腹に、有紀は、そのぞっとしない男に見惚れていた。
高い身長とバランスの取れた痩身。肩幅が広く、なのに胴体は細く締まっている。
一見非常な痩身で――けれど、腿には、しっかりとした張りがある。
禁欲的なスーツの下には、きっと確かな筋肉を内包しているに違いない。肩からウエストの流れるようなシルエット。グラマラスで上品なピンストライプのダークなスーツ。
「お前、おかしなことに首つっこんでないだろうな」
再びゴーグルを目元に戻しながら、いぶかしげな口調で三鷹は言った。
「どういう意味?」
「こないだも、スーツ着た男が、お前を尋ねてきてたんだよ。俺、その時受付にいたから、すぐに追い払ってやったけどさ。たしかそいつ、シンジさんって、一緒にいた奴らに呼ばれてたけど」
「またね、三鷹さん。日本選手権頑張って」
まだ物言いた気な三鷹に背を向け、そのまま、すうっと水を掻いた。
プールサイドに立つ男は、最初から有紀に気づいていたのか、組んでいた腕を解き、ゆっくりと視線を水面に落とす。
泳ぎ着く女に向けられた厳しい眼差し。
有紀もまた、水面から顔を上げて男を見つめる。
不思議だった。こんなに場違いな場所に立っているのに、スーツ姿が違和感なく背景に溶け込んでいる。プールが、彼の周囲だけ、オフィス街に変じてしまったようにさえ見える。
二日前に会った時と同じ空気が、男の全身から漂っている。
「………来てくれたんだ」
男の傍に泳ぎ着き、そしてキャップを外して有紀は言った。
「それって、私を買ってくれるってことだよね」
「……事情くらいは聞いてやる」
眉を寄せた男は、そっけない口調で言うと、指を内ポケットに滑らせた。
引き出されたのは一枚のカード。無造作に水面に投げられたそれを、有紀は少し驚いて拾い上げる。
「こんなものまで渡されて、放っておくわけにはいかないだろう、返してやるから、二度と不用意に他人に渡すな」
それは、スイミングクラブの会員証だった。
『連城有紀』の名前と生年月日がその表面に刻まれ、裏面には油性マジックで――まだしっかりと残っている。<水曜日の午後8時>
「安心するかな、と思って……ここのクラブ、特待生をのぞけば、いいとこのお嬢様しか入れないし」
「お前は、いいとこのお嬢様か、自分で言うならたいしたもんだ、恐れ入ったよ」
有紀はさすがに鼻白んだ。
「……だって……あなただって、素性のわからない女の子を愛人に出来ないでしょ」
「判ろうが判るまいが、俺は女を金で買う趣味はない」
「じゃあ、なんで来てくれたの?」
「そのカードは、キャッシャカードとしても使えるんだ、知らないわけじゃないだろう?そんなものを勝手にポケットに入れられて、迷惑したのは俺の方だ」
「……じゃあ、なんで来てくれたの?」
有紀は同じ質問を繰り返した。
「…………」
「本当は、少しだけ私に興味がある。だからあなたがわざわざ届けに来てくれたんでしょ」
そしてプールサイドに腕を掛け、身体を水中から引き離した。
とたんに重くなる身体。あれほど自由で軽かったものが、何かに囚われたように動けなくなる。
「だって、カード届けるくらいなら、人に頼んでもよかったわけだし」
濡れた前髪を払い、有紀は挑発するように男を見上げた。
「…………生意気なガキだな」
男は目をすがめ、有紀の身体をじっと見ている。
上から下まで、まるで金銭に換算して、これから契約するための金額を値踏みするように。
有紀も負けずに、男を見つめる。
自信はあった。先日、この人の目を間近で見た瞬間から――彼の目の奥に蠢いた感情を見た時から。この人は――――必ず来てくれると。
けれど、今の男の目は、欲望の片鱗さえなく、冷徹なビジネスマンのそれになっている。
少し恥ずかしくなって眼を逸らした途端、頭上から、呟くような声がした。
「君のことは何と呼べばいいんだ」
「え……」
「呼び方だ、どう呼んで欲しいか、言ってみろ」
「……ユキ」
そう言うと、さきほどまでの羞恥も忘れ、嬉しくなって笑みを零した。
「ユキだよ、そう呼んでくれる?さんとか、ちゃんはなくていい、呼び捨てでいいから」
「……何がちゃんだ、小学生の子供じゃあるまいし」
男は呆れたようにそう呟き、自分の胸ポケットから、一枚の名刺を取り出した。
有紀は、濡れた指に息を吹きかけ、急いでそれを受け取った。
・ みかみ れん
―――理光不動産株式会社 企画専務取締役 御守 蓮
・
「あなたのことは……蓮さん…?それとも御守さん?」
名刺に書かれた名前を見ながら、有紀は聞いた。
「好きに呼べばいい」
男はそう言うと背を向けた。間際に見せた横顔に、取りつくしまのない冷たさがある。
有紀は少しむっとして足を止めた。
「有紀、俺についてこい。お前のゲームに乗ってやる。君が俺を満足させられるかどうか、まずはテストさせてもらうからな」
御守蓮は、振り返りもせずにそう言った。