子供の頃、お婆ちゃんに聞いたことがある。
御堂の山には魔物が住んでいる。
悪いことをしたら山から怪物が降りてきて、目を食べられてしまうよ、と。
そんなの嘘だ。
私が笑って言い返すと、お婆ちゃんは真顔で私をにらみつけた。
本当だよ。
昔は何人も、女が攫われては目を食われて殺されたんだよ。
だからごらん、目を奪われた女の恨みが、ああして残っているじゃないか。
紅い雪だ。
はっと目を凝らした少年は、すぐに自身の錯覚に気がついた。
夕方にはちらつくほどだった雪は、今は牡丹のような大きさに変わっている。地面も草木も墓標も全て、暗い灰色に覆い隠してしまっている。
そこに、まるで血が飛び散ったように点在する真紅の色彩。
最初、雪が染まったのかと思ったそれは、雪の下からのぞく鮮やかな猩々木の花弁だった。
(ヨーロッパでは、クリスマスに血の色を飾る習慣があるのよ。)
そう教えてくれたのは誰だったろう。
触れれば溶ける幻のような声。
それは、ここで何年も眠り続けている女の声のような気もしたし、今しがた触れたばかりの、冷たい指先の名残のような気もした。
これでいいのですね。
自分の中の瞳に問いかけ、少年は再び、澄んだ双眸を灰色の夜に向ける。
風が強く、大降りの雪は、吹雪といってもいいほど激しさを増している。
戻らなければならない。全ての証拠を跡形もなく消し去ってから。
それでも少年は、立ち続けていた。
ただ、じっと、この雪が全てを――今夜、はからずも破綻してしまった「家族」の罪を連れ去っていってくれるのを、不思議なほど静かな気持ちで見守り続けていた。
そして頭は冷静に、これからの行動を計算する。
一言一句記憶している母の遺言を、今こそ実行する時がきたのだ。
そう、そのためだけに、僕は生まれてきたのだから。
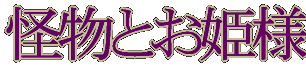

プロローグ 「怪物とお姫さま」
むかしあるところに、怪物がいました。
名前はありません。
生まれた時から一人きりで、仲間も友達もいませんでした。
怪物は、裂けた口と燃えるような緑の目玉、そしてぎらぎら光るするどい鉤爪と硬い泥色の皮膚を持っていました。
人間はもちろん、動物たちも畏れて近づきませんでしたので、怪物はいつも一人ぼっちでした。
怪物には二つの心臓があり、それには不思議な力がありました。
明るい月の夜だけ、怪物は美しい人間に変化することができるのです。
若い青年の姿になった怪物は、町に下りて若い娘を誘い出します。そして、山に連れ帰って食べてしまいます。
騒がれたり泣かれたりするのは心が痛むことでしたが、仕方ありません。怪物は、人間の肉しか食べることができないのです。
人肉の――その目の部分に、怪物が生きていくために必要な何かがあるのでしょう。怪物は好んで目を食べ、時にそれだけで事足り、残り部分には手をつけないこともあったのでした。
人が姿を消し、そして両目をえぐられた死体が見つかるたびに、町は大騒ぎです。
騒ぎが大きくなる前に、怪物は次の住処を求めて、山から山へと渡り歩いていくのですが、そんな暮らしが百年も二百年も続きましたので、ひとさらいの怪物の噂はおそろしい尾ひれがついて、国中に広がっていったのでした。
「山の人食い怪物の心臓を持ち帰ったものには、褒美をとらす」
そんなおふれが、ついに国王から出されました。
山という山に、沢山の勇者が押し寄せるようになりました。
そのため、なんどか怪物は住処をつきとめられ、刀で切られ、矢で射られたりしました。
けれど、怪物は平気でした。
怪物にはふたつの心臓があり、そのいずれかが残っていれば、決して死ぬことはないからです。
夜、怪物は、山を照らす銀色の月を見あげながら、いつも思うのでした。
僕は何のために生まれてきたんだろう。
僕は何のために生きているんだろう。
けれど、きらきらと輝く月は、何も答えてはくれないのでした。
ある夜のことです。
これまで、ふもとの町で何人もの娘をさらってきた怪物は、そろそろこの山ともお別れだと思っていました。
夕方、国王の軍隊がおしよせてきて、怪物は右足に怪我をしたばかりでした。傷口が膿んでずきずきと痛み、ひどい臭気を発しています。
この傷が治ったら、別の山に棲家を移そう。
そんなことを思いながら、足を引きずるようにして、山の頂にあるクローバー畑のほとりを通りかかったときでした。
ふと、怪物は足をとめていました。
緑の丘陵の半ばに小さな湖水があり、月の光を反射してきらきらと光り輝いています。それはいつもの光景なのですが、輝きがいつもと少し違うようです。
怪物は、そのほとりに、一人の美しい娘が倒れているのに気づいたのでした。
なんと美しいのだ。
雪のような肌、林檎のような唇、絹糸の髪が湖水に半ばつかり、ゆらゆらとただよっています。
怪物は足の痛みも忘れ、鍵爪で柔らかな身体を傷つけないように気をつけながら、そっと娘の身体を引き上げました。
さいわいなことに、娘は気を失っているだけのようでした。
なんと美しいのだ。
これは、どれだけ美味かわからないぞ。
じわり、とつばがでてきました。
怪物は、人間の娘が大好物なのです。
けれど、どうしてでしょう。どこかで見たような気がする娘です。
確かに覚えはないはずなのに、どこかで顔を見たような気がするのです。
その時、背後のしげみから人が近づいてくる気配がしました。
怪物は本能で危険を察し、いそいで湖に身を沈めました。
「姫さまがおられたぞ」
「生きておられるようだ」
現れたのは、二人の騎士でした。
水の底に届く声で、怪物は、娘がこの国のお姫様だと知りました。
どうりで、どこかで見たような気がしたわけです。
この山のふもとが王の宮殿がある町で、町にはいたるところに、お姫さまやその兄王子、そして王様の肖像画が飾られていたからです。
「お気の毒だが、とどめを刺そう」
しかし、騎士は信じられない言葉を口にしました。
「心臓を持ち帰らないと、われわれが王妃様に殺されてしまうのだ」
意味が判らないままに怪物は水から跳ね上がり、そして、するどい鍵爪をふりかざして、刀を持った騎士二人に襲いかかりました。
「うぬ、怪物め」
一人の騎士をかみ殺した時、もう一人が、背後から矢を放ちました。
それは、傷ついた怪物の足に突き刺さり、怪物は悲鳴をあげました。
爪でひと撫ですると、騎士はあっさりと二つに裂けましたが、怪物も同時に倒れてしまいました。
足が痺れ、目の前が暗くなります。矢に毒でも塗ってあったのかもしれません。
その時、かすかな呟きが聞こえました。怪物の隣で、お姫さまが小さくうめきながら、眉をしかめています。
まずいぞ、このまま目を覚まされて、もし俺の姿見られたら……。
けれど、銀に輝く月を見上げながら、あまりの痛みに怪物は気をうしなってしまったのでした。
|
|